|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
海洋エネルギーを利用した主な発電には、太陽エネルギーで温まった海の表面水と冷たい深海水の温度差を利用する海洋温度差発電及び熱供給、波の上下振動を利用して圧搾空気を作りタービンを回転する波力発電、潮流からエネルギーを取り出す海流発電、月の引力によって生じる干満の潮差を利用して発電する潮汐発電の4種類がある。日本で主に試験研究が行われているのは海洋温度差発電と波力発電であるが、外国では潮汐発電も実施されている。波力発電は航路標識用電力等の特殊な設置場所では実用化されている例がある。しかし、一般には、経済性が悪いために実用化に至っていない。外国の潮汐発電所としては、フランスのランス発電所、カナダのアンナポリス発電所などが運転されている。近年、海洋温度差エネルギーを熱供給等複合的に利用しようとする動きもある。 <更新年月> 2004年02月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
太陽から地球の表面に降り注ぐエネルギーは、大気圏外で1平方メートル当たり1.38kW、地表では、1kW程度となるといわれ、半恒久的とも言える太陽エネルギーの大部分は地球表面の約2/3を占める海の表層水を温めることに費やされている(図1参照)。このようにして蓄えられた海洋エネルギーは、波力や潮流、海流といった運動エネルギーや、海洋温度差のような熱エネルギーなど、さまざまな「かたち」に姿を変える。海洋エネルギーの利用は、1995年から内閣府のエネルギー戦略レポートの中で、中長期戦略プロジェクトとして取り上げられたが、いまだ研究開発の域をでないこと、経済的には見合わないということから、新エネルギーの定義から外れている。しかし、四方を海に囲まれた日本にとって、海洋エネルギーは期待されるエネルギーである。海洋エネルギーを利用した主な発電4種類(海洋温度差発電、波力発電、潮流・潮汐発電)を以下に示す。また、実験実施地点を図2に示す。 1.海洋温度差発電(Ocean Thermal Energy Conversion:OTEC) 1.1 海洋温度差利用エネルギー技術開発 日本周辺や熱帯・亜熱帯地域の海洋における海水の温度は、一般に海表レベルで摂氏20度から30度、約700メートルの深海では2度から7度といわれており、海洋温度差発電とは、太陽エネルギーで温まった海の表面水と、冷たい深海水の温度差を利用する発電方式である。この発電方式には、作動流体(アンモニアなど)を温海水で気化し、タービンを回転した後、冷海水で凝縮させて発電するクローズドサイクル(図3)と温水そのものを気化発電するオープンサイクル(図4)、そしてこれらのサイクルを組みわせたハイブリッドサイクルの3つに大別される。オープンサイクルに関しては、米国のNELH(Natural Energy Laboratory of Hawaii)を中心に研究開発が行われ、定格出力210kWの実証実験に成功している。淡水も副産物として得られる。 日本ではニューサンシャイン計画で、この方式の要素技術開発を進めている。しかし、クローズドサイクルを用いる方が、より経済的で大きな出力の発電が可能であることから、現在の研究開発の主流となっている。島根沖での洋上実験(1979年10月)、ナウル島の実験プラント(120kW、東京電力、1981年)および徳之島実験プラント(50kW、九州電力のディーゼルの廃熱との組み合わせた発電、1982年)、伊万里の海洋温度差発電実験設備(50kW、佐賀大学1992年4月)、富山湾での「豊洋」洋上試験(通産省工業技術院電子技術総合研究所(現独立行政法人産業技術総合研究所)、洋上係留システム、1989年)などの実証試験が実施されている。しかし、発電プラント単体では経済性を見いだせない状況で、その上、海洋温度差発電には、(1)フロンやアンモニア等の作動流体の改良、(2)ポンプの改良などの問題も多く抱えている。 しかしながら、海洋温度差発電は、深層海水を表層海水と組み合わせて有効エネルギーをとり出すばかりでなく、栄養塩を利用した海洋生物生産性の向上や、低温性を利用した海水淡水化などトータルシステム(図5参照)として有効利用を図れることから、高知県海洋深層水研究所(1989年設立)や富山県水産試験場深層水利用研究施設(1995年完成)、沖縄県久米島海洋深層水研究所(2001年完成)では、深層水を利用する研究も進んでいる。 また、経済産業省は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と協力して「エネルギー使用合理化海洋資源活用システム開発」(1999年度から5ケ年計画)を計画している。100万t/日および10万t/日の深層水を揚水することで、第1段で火力発電所の冷却などへの活用、第2段で昇温した深層水を海域に環流させ、植物生産を増加させてCO2の吸収(固定)促進などを目標に要素技術の開発が進められている。 1.2 今後の動向 ハワイ島では1993年より定格出力210KWの陸上型オープンサイクル装置が試験中である。オープンサークルは、電力のほかに副産物として淡水が得られ、このメリットは大きい。インドは佐賀大学と協定を結び、2001年より出力1000KWの洋上実証プラントで実験を行う予定であったが、建設中に大型の暴風雨に遭遇し取水管の流失のため実験開始が遅れ、2002年から実験開始の予定である。一方、フランスはタヒチ島に5MWプラントを検討するとの情報もある。 日本では、深層水を冷熱源として有効に利用する複合エネルギー利用システムについて検討中であり、一例として温熱源として温泉水を利用する複合システムの可能性がある。温度差発電は深層の栄養塩を含む膨大な冷海水を利用するため、電力に加えこの冷海水の特徴を利用して海藻や魚介類の養殖などの水産および有用物質培養等で商品化が見込まれ、すでに深層水を利用した食品や化粧品などが販売され好評を博しており、商業化されている。 一方、近年の温度差エネルギーを利用した熱供給事業として、サンポート高松(四国電力)が2001年4月より、海水温度差熱および電気を利用して熱供給を開始した。また、中部国際空港島(中部国際空港エネルギー供給株式会社)が2004年10月に、海水温度差エネルギー、コージェネ排熱、都市ガス、電気を利用した熱供給開始を予定し、中之島三丁目(関電エネルギー開発株式会社)が2004年12月に河川温度差エネルギーおよび電気を利用した熱供給の開始を予定している。 海洋温度差発電を建設したいという国は、現在50カ国以上になるという。パラオ、台湾、パプアニューギニア、ハワイ等はフィージビリティスタディ(使用可能性試験)を行っているという。 2.波力発電(Wave Energy Conversion) 日本は、四方を総延長34,386kmにも及ぶ海岸線(1989年調査値)に囲まれており、ノルウェーや英国、スウェーデンなどとともに波エネルギーの豊かな国の一つに数えられている。世界中では2000基以上の波エネルギーを利用した波力発電が使用されている。国内では、航路標識ブイや小型灯台用電源などの移動電源として1965年前後に開発され、出力100Wの波力発電ブイを中心に1000基以上の使用実績があるほか、10ヶ所以上の実験用発電施設がある。ヨーロッパでは、EUの波力発電プロジェクト「第2次ジュール計画」として大西洋にあるポルトガル領アゾレス諸島のピコ島で波力発電の研究開発が1994年から行われている。 発電原理は、ケーソン前面部に設けられた空気室に波が出入りして、空気室内の空気を圧縮膨張させ、波のエネルギーを空気のエネルギーに変換し、この空気流で機械室に設置されているタービン発電機を回転させ、電気エネルギーへ変換する方法である(表1参照)。タービン発電機には波が寄せる時も引く時も一方向のみ回転するように工夫されており、効率よく電気エネルギーへ変換できる。発電システムは、波の上下振動を利用して圧搾空気を作りタービンを回転する方式(タービン方式または水柱振動型と呼ばれる)が主流であるが、波エネルギーを受圧板の振子運動として捕捉し、油圧ポンプを作動させる方法(振子式)も研究されている。 国内では浮体式水柱振動型(沖合浮体式波力装置「マイティーホエール」、50kW-10kW×1基、30kW×3基、波力発電船「海明」、125kW×8基)、沿岸固定式水柱振動型(三瀬40kW、酒田60kW、原町130kW、鶴岡40kW、九十九里30kW)、振子式(北海道増毛1-−20kW、京都府宮津市1kW相当の噴水用動力源)等の波力エネルギー装置の開発が行われている。 山形県酒田港では、1989年度から波力発電防波堤を設置され、現地実証試験が行われた。実証試験では(1)防波堤の耐波設計・施工法の確立、(2)発電システム設計法の妥当性検証、(3)波力発電電力の利用技術の開発、(4)一般商業電力線への接続運転などの成果が得られ、経年劣化試験後、1999年7月に終了している。 また、振動水柱式空気タービン方式波力発電装置「マイティーホエール」は、1998年9月から三重県南勢町五ヶ所湾沖で実海域実験を行い、波エネルギー変換技術、静穏海域造成技術、海洋環境改善技術を中心に研究を進めている(図6参照)。1998年8月から2000年12月までの実験期間中、保守点検及び故障で装置を停止した日を除くと運転日数は701日で稼働日数は約79%になる。この間の一時間当りの平均発電量は6.04kWhであった。 波力発電には、波によって打ち寄せられる水塊(すいかい:水のかたまり)を構造物の斜面に沿って遡上・越波させ、背後の池に貯留し、池の水面と海水面との水位の差を利用して低落差用水車タービンを回す方法がある。水の位置エネルギーまたは水流エネルギーを利用する方法で、ノルウェーのタプチャン(TAPCHAN:Taped Channel Power Plant)など実証プラントはあるものの、日本では事例がない。 波力発電は建設コストが高い、発電単体では経済性に劣る(10MWの波力発電コスト試算例では17.3〜33.1円/kWh)、台風などの異常波浪時への安全対策などの問題も抱えている。しかし、離島での電力供給、防波堤を利用したコストの低下、波力発電施設の背後のレクリエーション施設や海洋牧場を併設など、地域振興との関連の実用化も期待できる。 3.潮流発電 日本近海には、黒潮という非常に流速が速く、かつ流量の大きい海流がある。これまでは、海流のエネルギー密度が小さいうえ、平均流速が1m/secもある海流中に巨大な海洋構造物を設置・係留することは困難であると考えられ、潮流からエネルギーを取り出そうという潮流発電の試みは殆どなされていなかった。しかし、近年、北海油田のリグように海洋建造物に対する技術進歩がめざましいこと、海流エネルギーを取得するのに必要な技術は水力発電技術など既に陸上で用いられている技術体系が利用できることなどから、技術環境が整いつつある。 潮流発電システムは、発電システム、海洋構造物で構成されている。エネルギー変換装置は、潮汐現象に伴う流れのエネルギーを回転エネルギーに変換するものが殆どで、ダリウス型水車、クロスフロー型水車などがある(図7参照)。潮流発電のエネルギーは潮位差があまり大きくなくても、海底地形が狭まっているところ、流れの速い「瀬戸」や「海峡」と呼ばれるところに集約される。国内では、瀬戸内海と九州を中心にいくつかの実験が行われている。また、日本近海の主要潮流のエネルギーの合計は、電力中央研究所の計算によると、年間発生電力量は60TWhと試算されている。 このシステムの開発課題としては、流速の変化に対して一定回転数を保持する機構、流れの向きの変化に対応する機構、大型構造物の係留設備、一定流速が長時間持続する地点の選定などが重要である。また、発電サイトが陸地から離れているため、電力の輸送には海底送電ケーブルが考えられているが、電気エネルギーを化学エネルギーに変換して輸送する方法も研究されている。 4.潮汐発電(Tidal Energy Conversion) 潮汐発電は、天体の運行(月の引力)によって生じる干満の潮差を利用して発電するもので、低落差の水力発電の一種である(図8参照)。 潮汐発電で得られる電力P(kW)は、ほぼ、P=9.8ηQH(η:総合変換効率)となる。 ここで、H(m)は水位差を、Q(m3)は流量を表す。 潮汐発電は、その発電方式によって、海水位と貯水池水位の落差を利用する一方向発電方式、干潮時および満潮時のいずれの場合にも発電が可能な二方向発電方式、2つの貯水池の落差を利用する二貯水池方式の3つに分類することができる。 日本では、潮位の差が少ないため(日本で潮位差の一番大きい九州有明海の奥部で、住ノ江で4.9mほど)、経済性に難点があるが、国外では、フランス北西部サン・マロ湾河口のランス発電所が24万kWの発電機を備え、1967年から30年以上にわたって商業用として大きな事故もなく稼働している。図9にランス川発電所の断面図を示す。ちなみにランス発電所の発電効率は15%、潮位差は平均で8mである。そのほか、カナダのアンナポリスの潮汐発電所(Annapolis、平均潮位差は6.4m)、中国の江厦の潮汐発電所(Jiangxia、)など、潮汐のエネルギーに恵まれた韓国、ロシア、オーストラリアなどでパイロットプラントが建設されている。 <図/表> 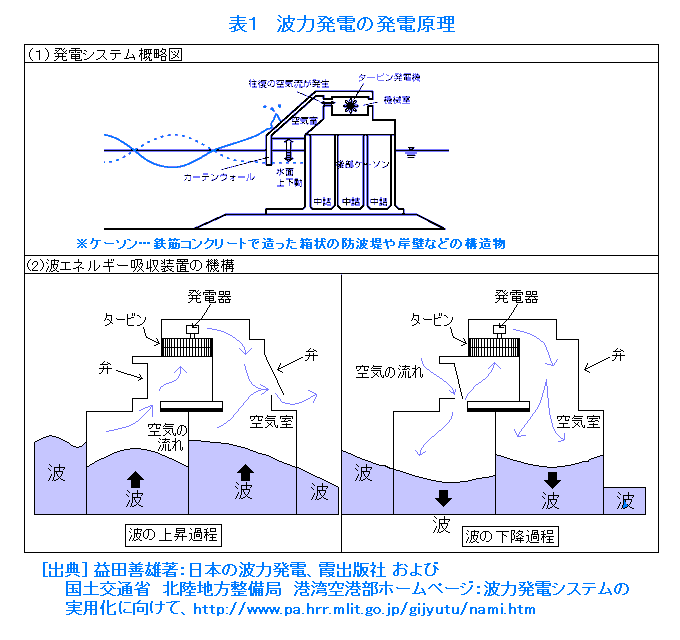
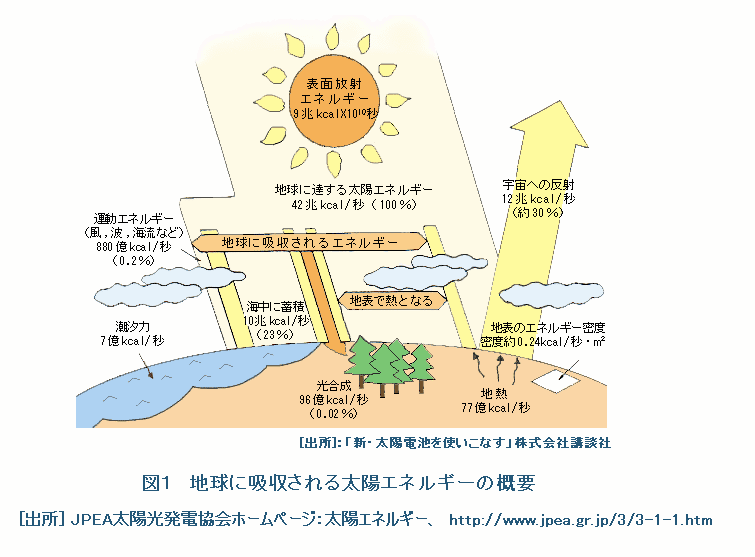
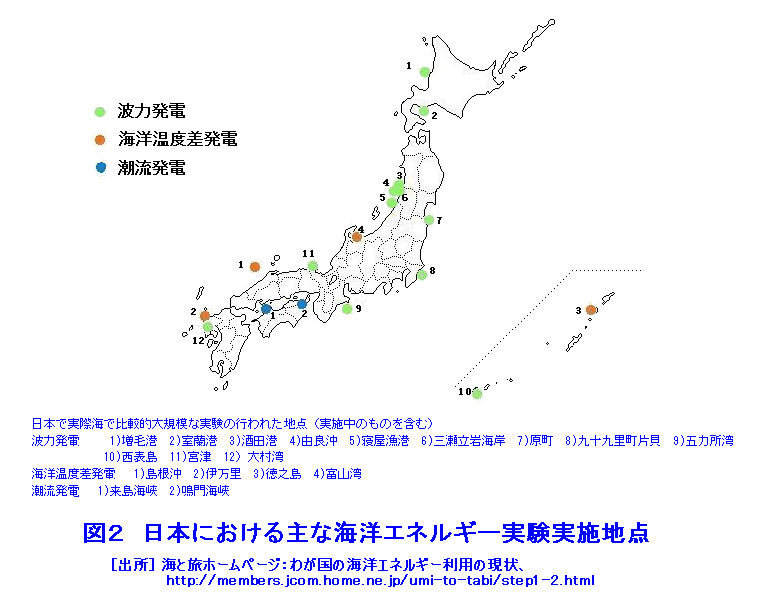
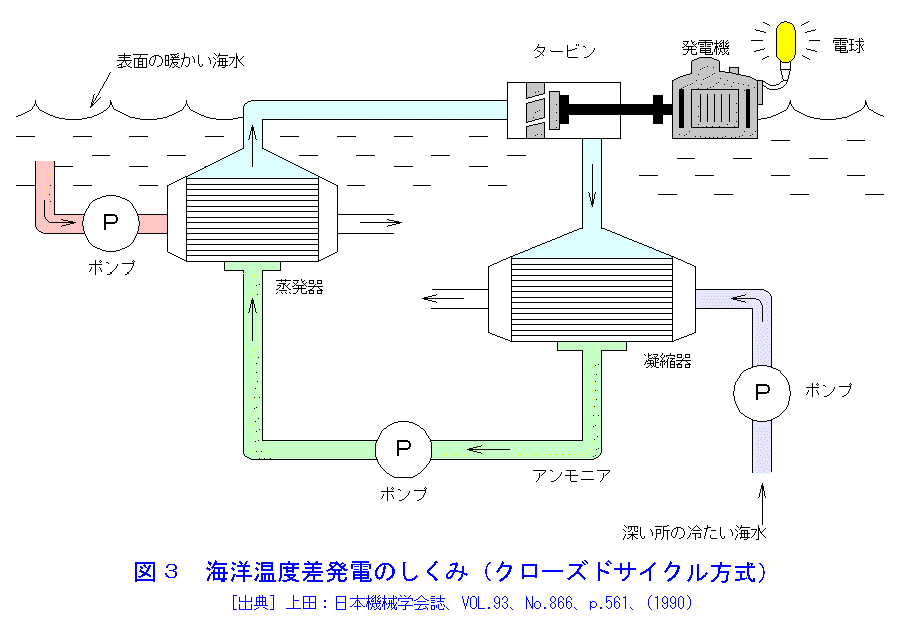
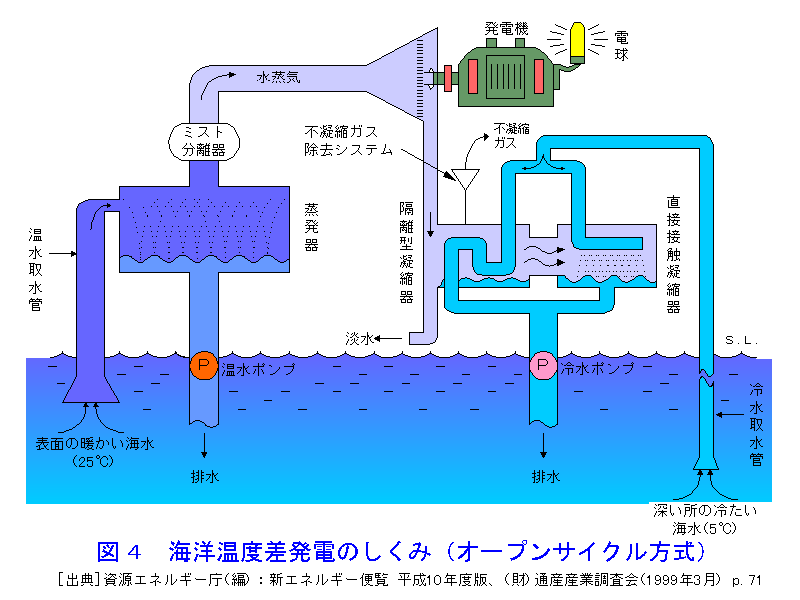

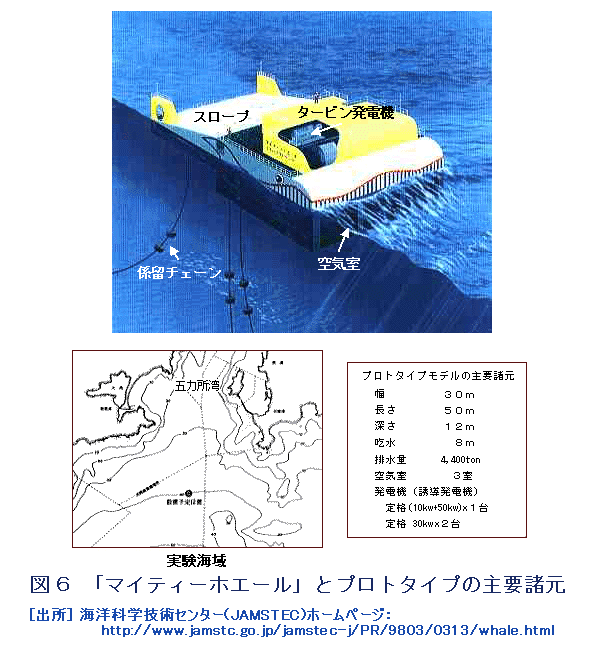
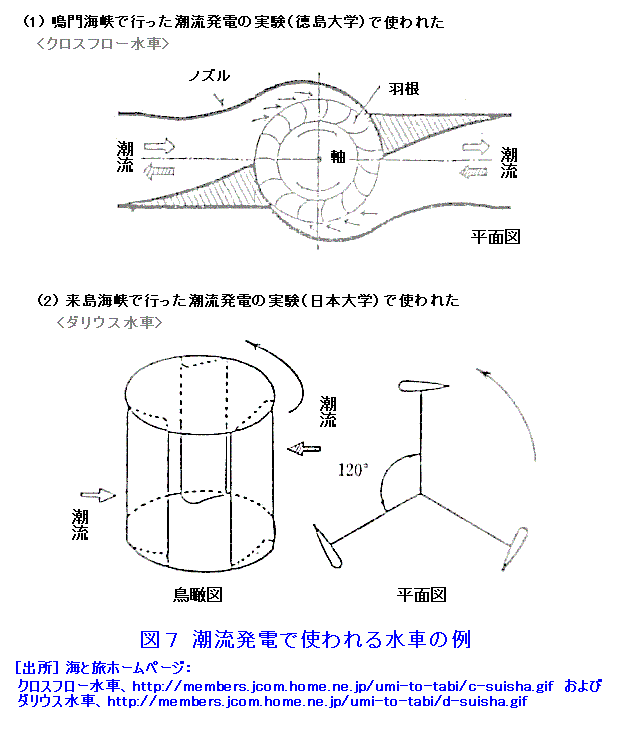
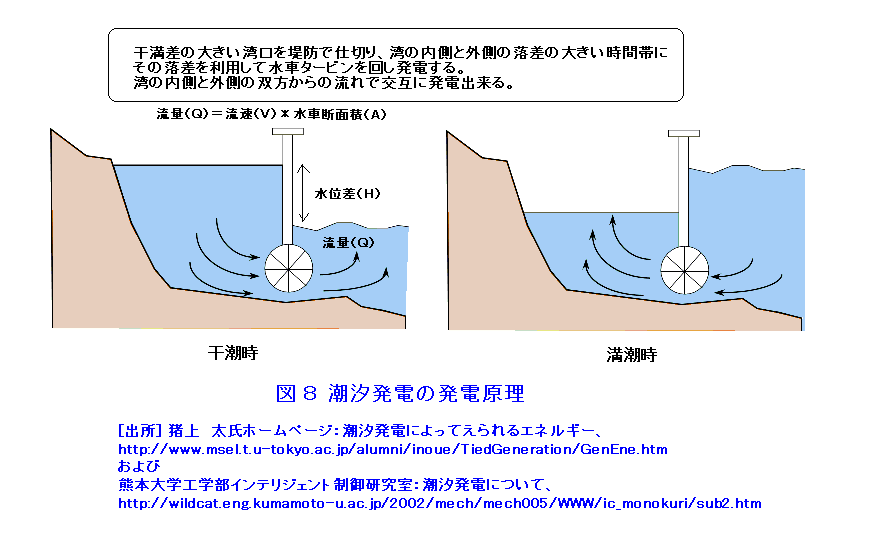
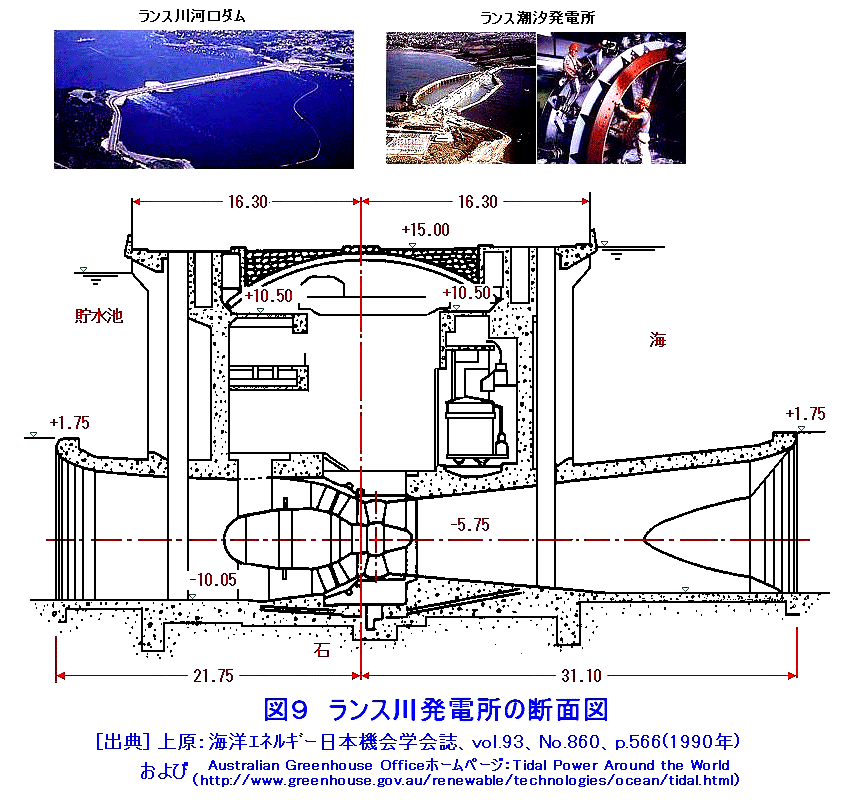
<関連タイトル> 波力発電 (01-05-01-08) 新エネルギーの導入と動向 (01-05-01-09) <参考文献> (1)益田:日本の波力発電、霞出版社 (2)渡部:日本の波力発電、エネルギーレビュー、8月号 p.8-12(1994年) (3)益田:ヨーロッパの波力発電、エネルギーレビュー、8月号 p.13-16(1994年) (4)上原:海洋エネルギー、日本機械学会誌、Vol.93 No.866 p.560-566(1990年) (5)高野:海洋とエネルギー、共立出版 (6)資源エネルギー庁(編):新エネルギー便覧 平成10年度版、通産産業調査会(1999年3月)p.71-73 (7)高柳 幹男:海洋温度差発電、火力原子力発電技術協会、505(49)、p.30-34(1998) (8)牧野 朝昭:波力発電、火力原子力発電技術協会、505(49)、p.35-41(1998) (9)牧野 朝昭:潮汐・潮流発電、火力原子力発電技術協会、505(49)、p.42-47(1998) (10)東レ経営研究所:エネルギー使用合理化海洋資源活用システム開発周辺動向調査(2003年1月)、および (11)新エネルギー・産業技術総合開発機構:http://www.nedo.go.jp/ (12)電力中央研究所有識者会議推進室 廣瀬 学(著):波力発電の現状 (13)上原 春男:海洋温度差発電の現状と将来展望、エネルギー・資源.Vol23 No.2(2002)、p.129-132 (14)NEDO:新エネデータ、温度差エネルギー
|

