|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
経済構造改革の一環として、電気事業においては国際的にそん色のないコスト水準を目指すことが重要課題とされ、一層効率的な電力供給システムの確立が求められている。電力各社の原子力発電を含めた電力供給計画(平成10年度)によれば、平成19年度までの8月最大電力需給バランスは必要供給予備力を確保し、安定した電力供給ができる見通しである。 平成9年度における発電に占める原子力の割合は、高い順に、九州電力(55.4%)、関西電力、四国電力、東京電力、北海道電力(29.9%)である。 <更新年月> 1999年03月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
経済構造改革の一環として、電気事業においては国際的にそん色のないコスト水準を目指すことが重要課題とされ、一層効率的な電力供給システムの確立が求められている。こうしたなか.平成10年度の電力各社の供給計画は,21世紀に向けての電力供給基盤の確保と経営基盤の強化を図るため「経営効率化とコストダウンの徹底」、「原子力を中心とする電源開発の推進」、「卸供給事業者の活用」、「広域運営の推進」を重点として策定されている。 平成10年6月末現在、我が国で運転中の商業用原子力発電所は51基4,491.7万kW、建設中、建設準備中を合わせると合計56基5,040.5万kWに達している。 平成10年7月、第138回電源開発調整審議会(現総合資源エネルギー調査会電源開発分科会)が開催され、平成10年度電源開発計画および長期の電源開発目標が審議され、平成10年度から平成19年度に至る電力供給の安定確保を図るため、この間に完成させることが必要な一般電気事業用発電施設の規模が定められた。設備容量は、全体で6,819万kW、うち1,128万kWは原子力である。原子力のうち5地点は、上に述べたように計画に着手しているものである。 1.供給カの確保 平成10年度電源開発計画のもとになった平成10年度電力供給計画によると、電力は、需要に応じ安定的に供給する必要があり、かつ、貯蔵することができないという特性を有しているため、常に最大需要電力の増加に対応し得るよう電源設備を計画的に開発していく必要がある。電源設備の開発に当たっては、認可出力から定期検査、水力発電の水力減少等を控除した上で、異常高気温、景気変動等の予測し得ない事態が発生した場合においても電力を安定的に供給することができるように、想定される最大需要電力に対して一定の予備力を加えた供給を確保する必要がある。 (1)平成9年度需給実績および平成10年度需給バランス 平成9年度は、7月初めに記録的な暑さとなった以降、不順な気温変動を繰り返し、平均するとほぼ平年並みの気温となった。各社別では、北海道、東北、中部および北陸が一日最大需要電力(発電端)の記録を更新したが、高気温の発生時期の違いから、電力10社合計では残暑となった9月2日に発生し、1億6,783万kWとこれまでの記録である1億7,113万kW(平成7年8月25日)よりも331万kWの減となった。 また、供給力整備の目安となる最大3日平均電力(送電端、ここでは、「最大需要電力」は「最大3日平均電力」のことをいう)は10社計で1億6,414万kWとなり、平成8年度に比べて0.6%の減となった。これに対し、供給力については、各社とも定期検査の調整や計画的な融通調整により1億8,614万kWの供給力を確保し、供給予備率は10社計で13.4%であった( 表1 参照)。 平成10年度は、最大需要電力が10社合計で1億7,291万kWと見込まれるのに対し、供給力としては、新増設電源等の供給力増加対策を着実に推進するとともに広域的な電力融通により、平成9年度実績に比べ366万kW増の1億8,980万kWを確保している。その結果、供給予備率は10社計で9.8%を確保しており、また、各社別にみても8.1%以上の予備率を確保している(表1参照)。 (2)長期電力供給バランス 長期的にも、今後10年間の電源の開発および電力の適切な調達により、14年度には2億426万kW、平成19年度には2億2,485万kWの供給力を確保する計画となっている。その結果、最大需要電力に対して、平成14年度で9.1%、平成19年度で9.5%の予備率を有しており、安定供給が確保できる計画となっている。表1に今後の電源開発量と需給バランスを示す。具体的供給力としては、現在運転中の2億1,536万kW(平成10年3月末現在)に加え、建設中の55基2,848万kW、着工準備中の49基3,652万kW、さらに、平成10年度電源開発調整審議会(現総合資源エネルギー調査会電源開発分科会)上程予定の21地点1,413万kW(水力396万kW、火力191万kW、原子力826万kW)が計画されている。今後とも、将来の電力の安定供給確保の観点から、平成11年度以降上程が予定されている電源等も含め、電源開発を計画的に遂行する必要がある( 表2 参照)。 2.電源構成の多様化 本供給計画が実現した場合の19年度末の発電設備の構成および、発電電力量の構成は次に示すとおりである。 電源構成については、非化石エネルギーの中核として原子力の開発を推進するとともに、電源の多様化の観点から、原子力に加え、石炭火力、LNG火力、水力(一般および揚水)等についてバランスのとれた開発をすることとなっている。また、石炭火力、LNG火力については、地球環境問題への対応および省エネルギーの推進の観点から、高効率発電方式を採用し、発電効率の向上に努めることとしている。さらに、国産エネルギーである一般水力および地熱発電についても、着実な開発を進めることとしている。 原子力については、今後10年間で9基1,128万kWが運転開始し、平成19年度末において5,620万kWになると計画されている。平成21年度運転開始電源として島根3号が追加されており、平成10年度には6基826万kWが電源開発調整審議会(現総合資源エネルギー調査会電源開発分科会)に上程される予定である(表2参照)。 3.平成19年度末の電源構成 電力各社の供給計画が実現した場合の他社受電分を含む10社計の電源設備構成比は、平成9年度末から19年度にかけて石炭火力が10%から16%に大幅に増加し、LNG火力が24%から25%に増加する一方、水力は20%から18%低下、原子力も21%から20%に低下、石油は23%から18%に大幅に低下し、電源の多様化を着実に進める計画となっている。表2に発電設備構成および発電電力量構成の推移を示す。 原子力については、今後10年間で9基1,128万kWが運転開始し,平成19年度末において5,620万kW(9年度末4,492万kW)になると計画されている。一般電気事業用の発電電力量について、平成9年度の電力会社別の原子力発電その他の割合を 表3 および 図1 に示す。原子力の構成比が高い順に、九州電力(55.4%)、関西電力(53.9%)、四国電力(49.6%)、東京電力(46.5%)、北海道電力(29.9%)となっている。 このような電源開発が計画どおり実現できれば、平成19年度までの8月最大電力需給バランスは必要供給予備力を確保し、安定した電力供給ができる見通しである。 表4 、 表5 、 表6 、 表7 、 表8 、 表9 、 表10 、 表11 および 表12 に電力9社の発電設備構成および発電電力量構成の推移を示す。 <図/表> 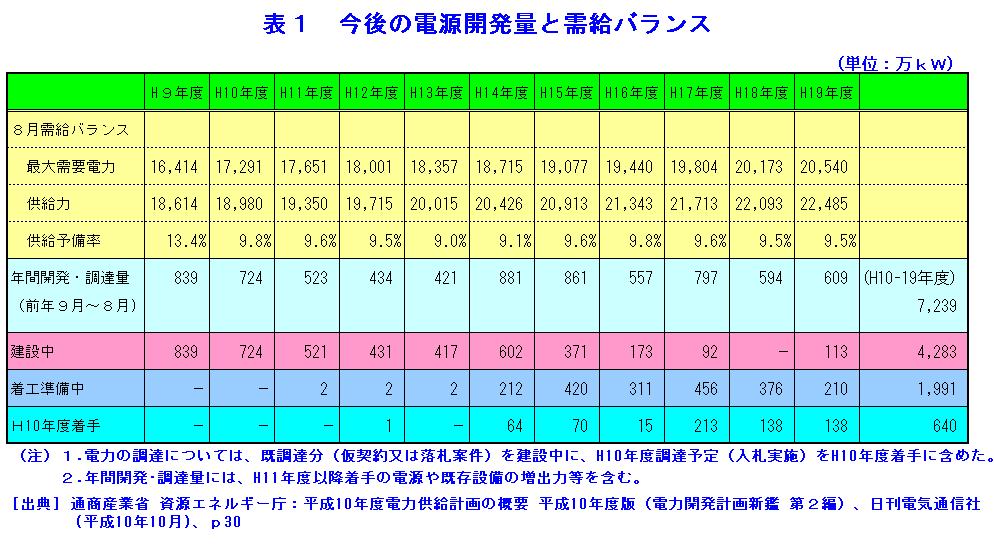
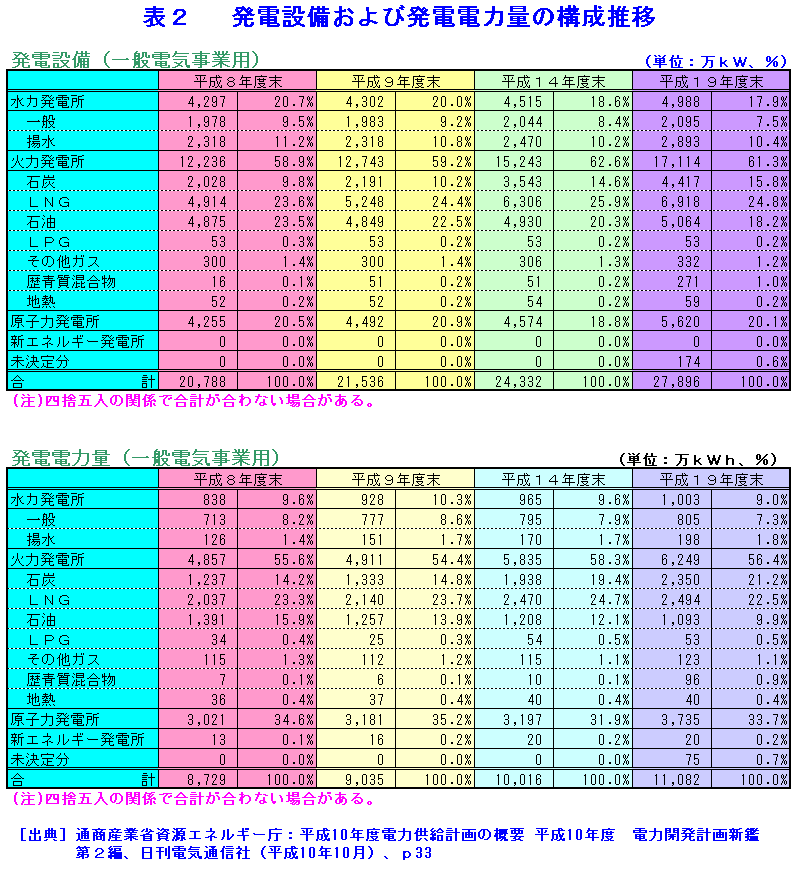
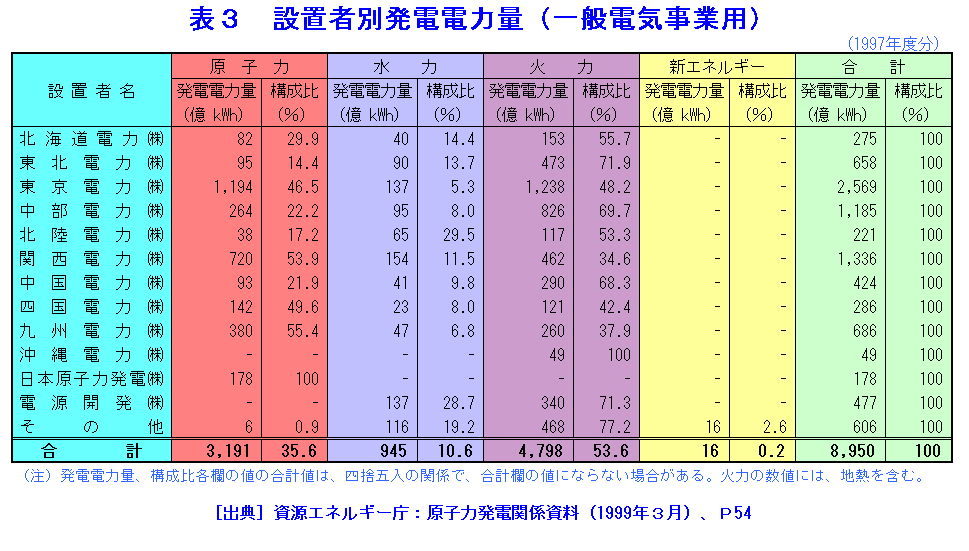
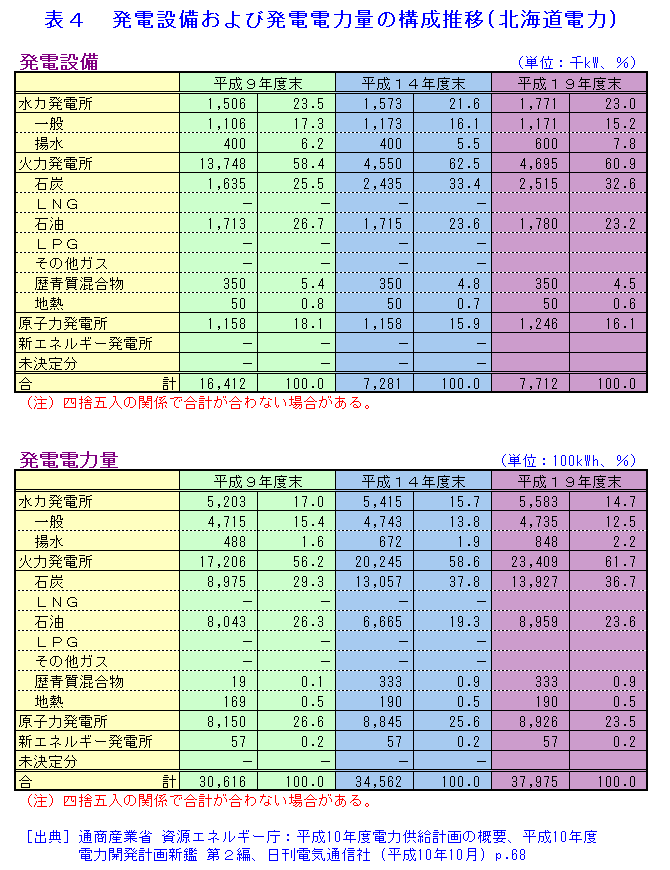
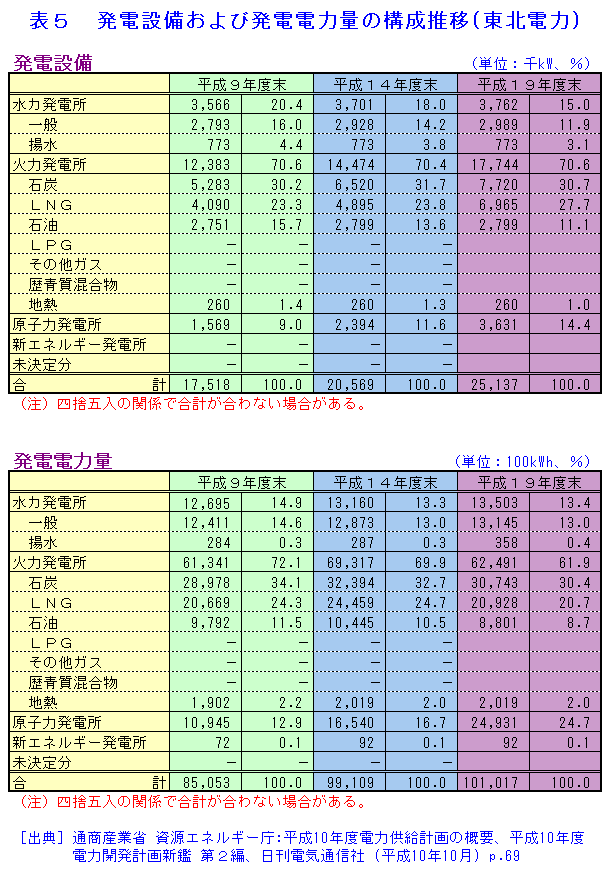
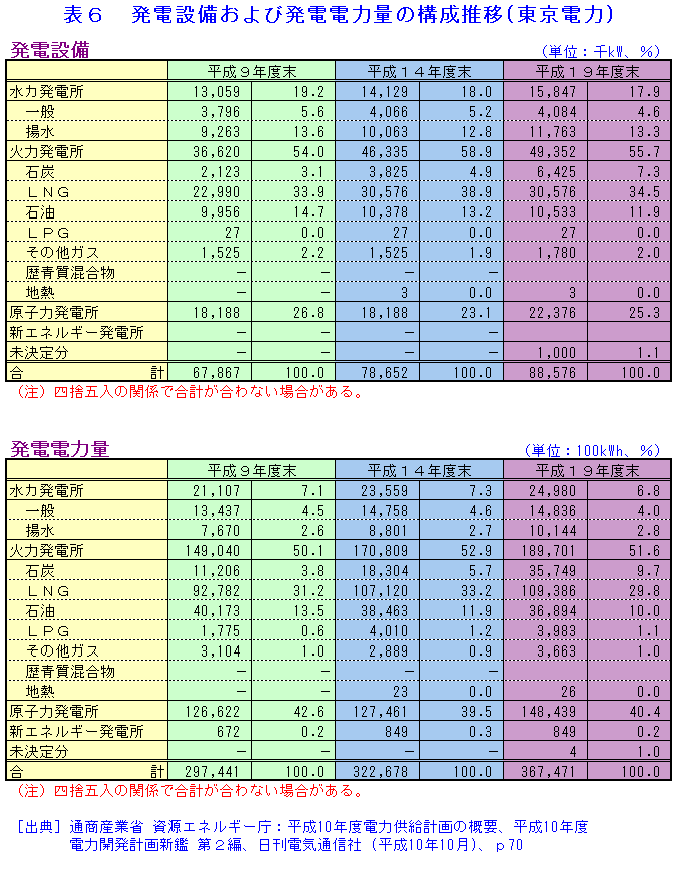
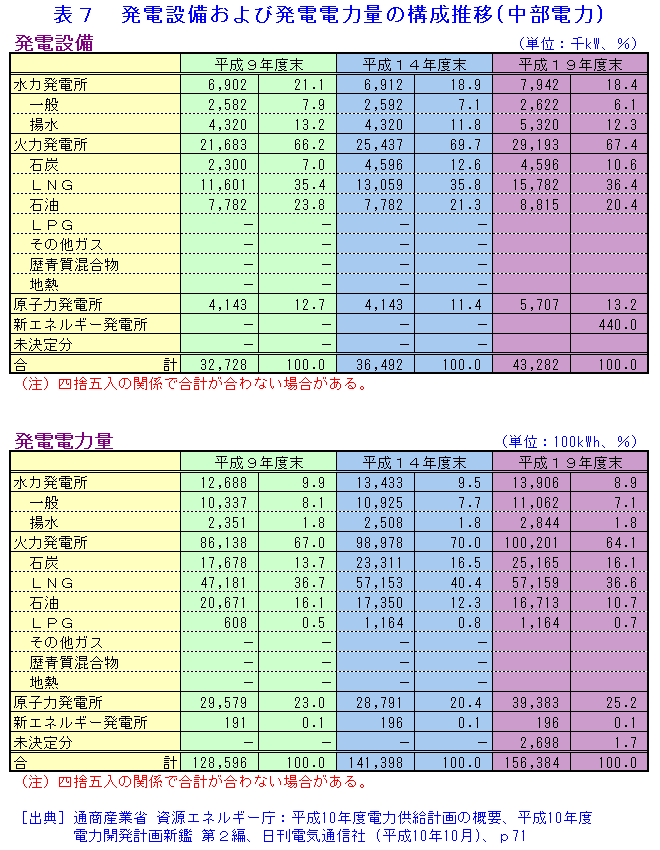
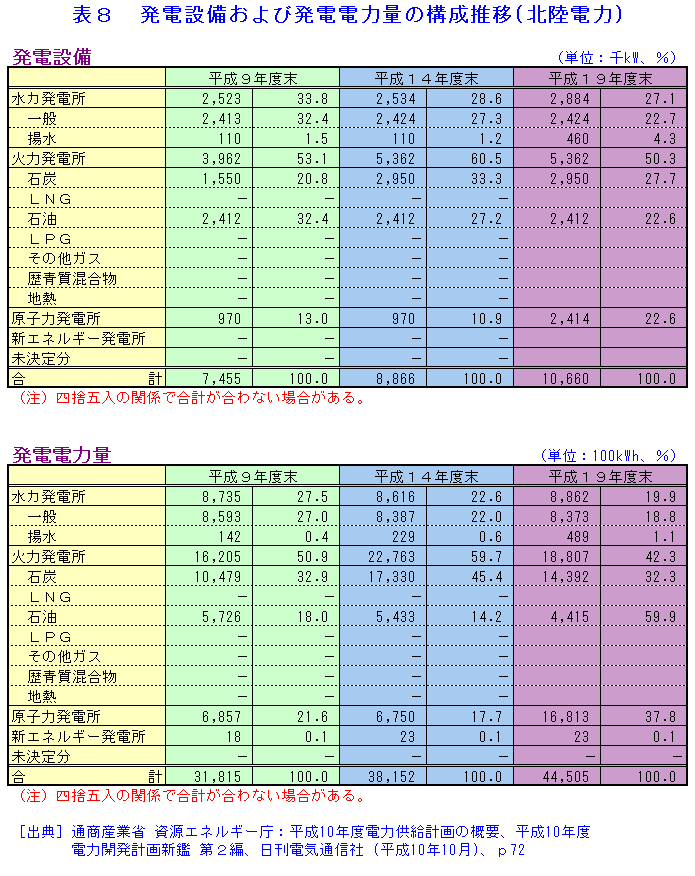
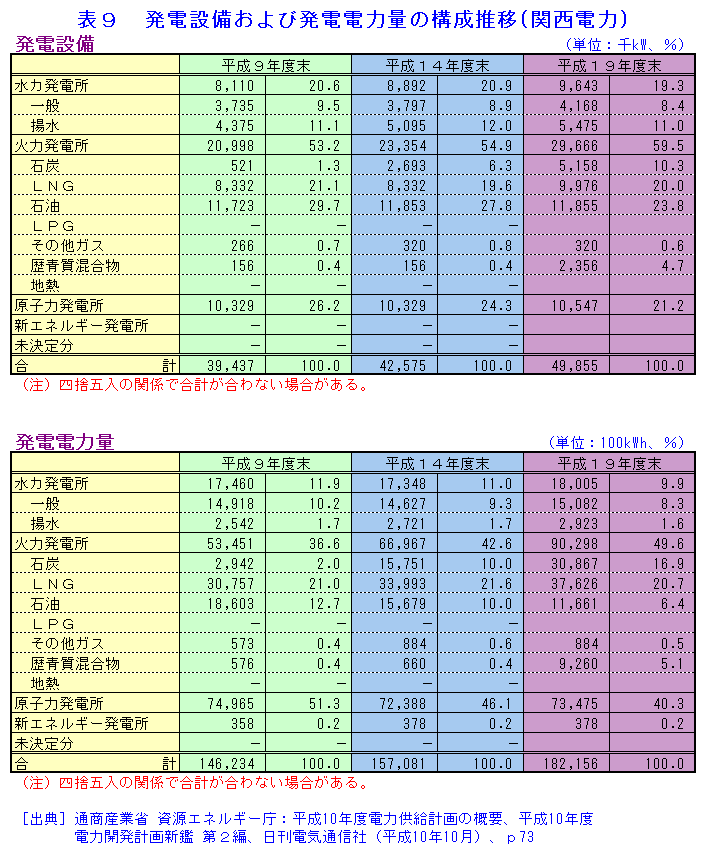
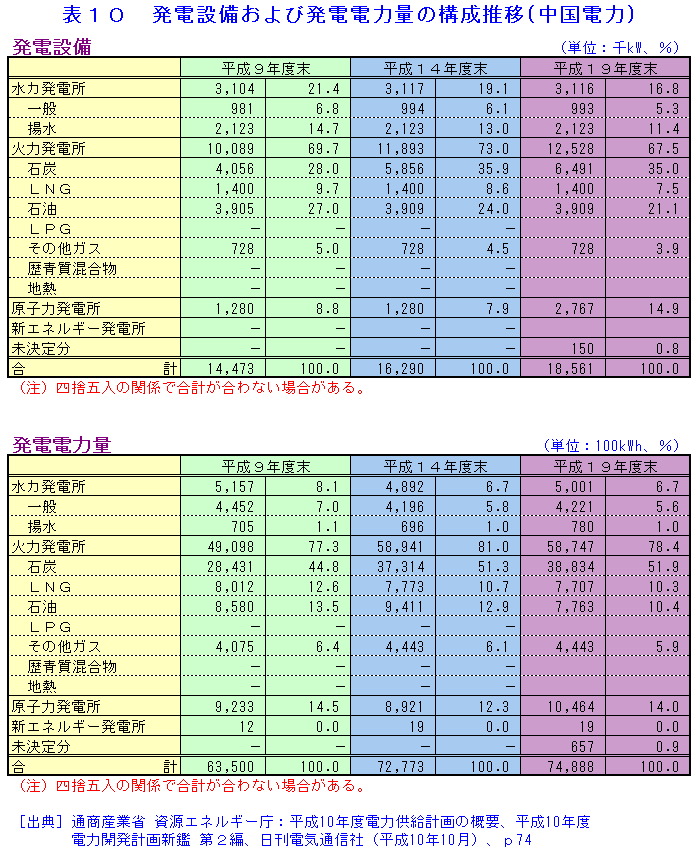
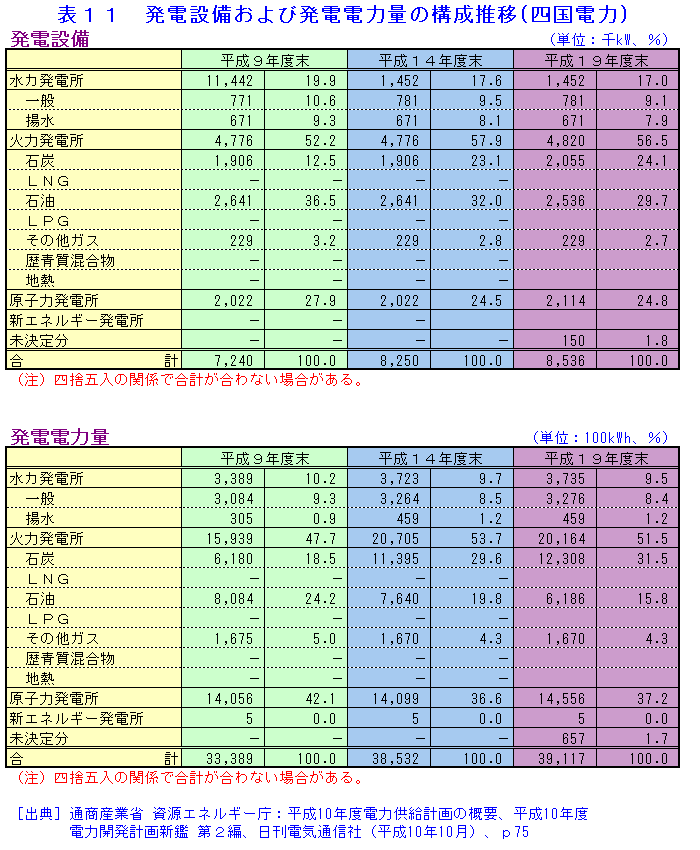
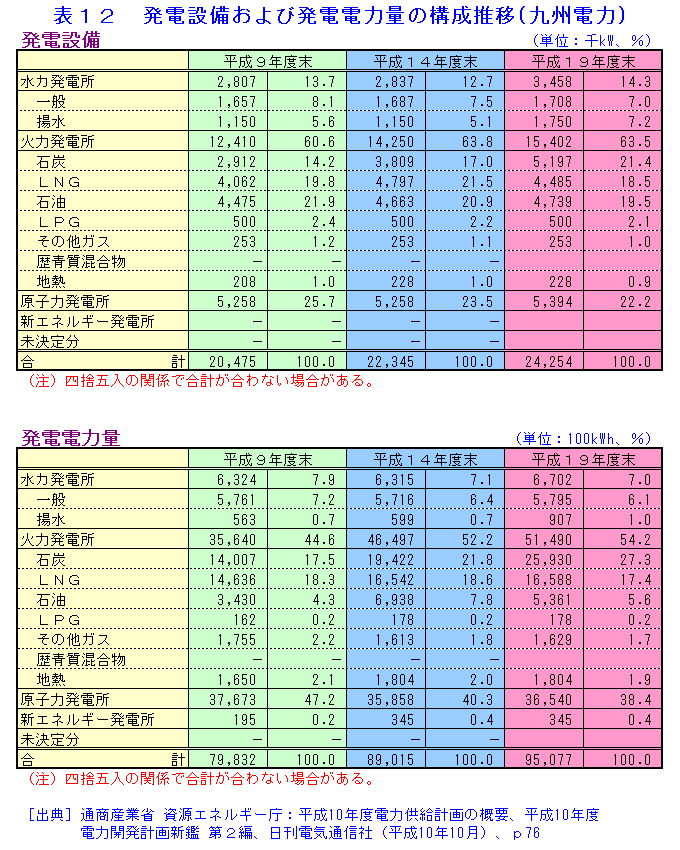
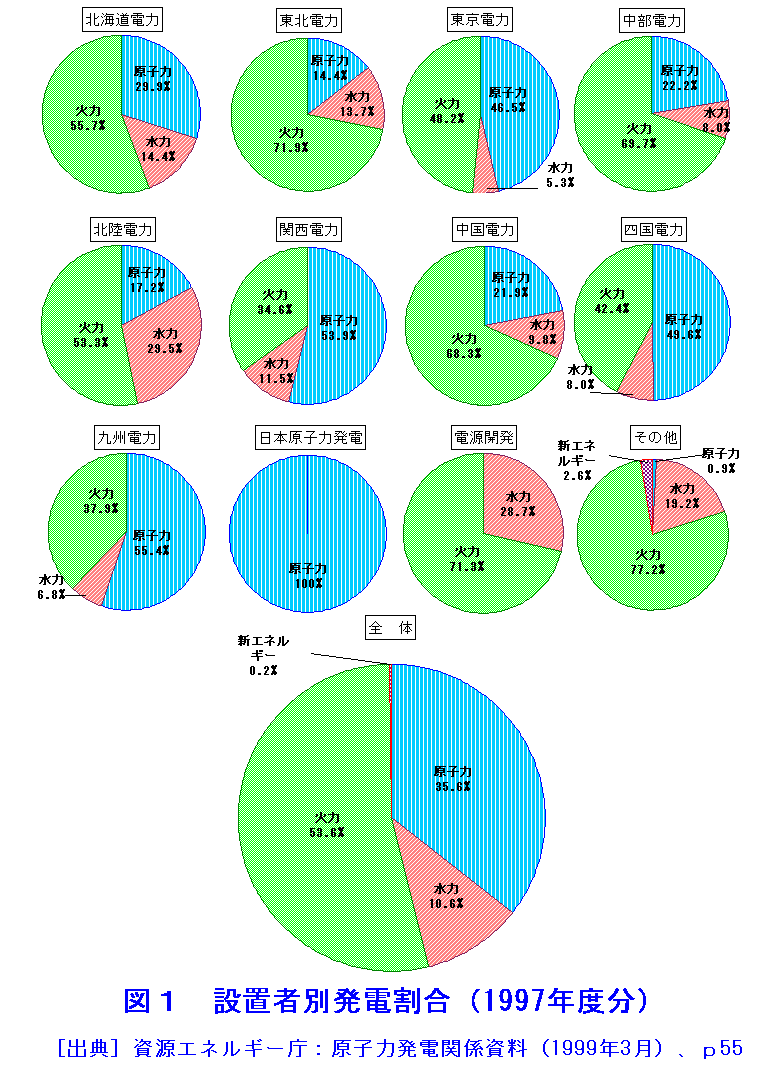
<関連タイトル> 電気事業審議会の長期電力需給見通し(1998年6月) (01-09-05-13) <参考文献> (1)通商産業省 資源エネルギー庁:平成10年度電力供給計画の概要 平成10年度 電力開発計画新鑑 第2編、日刊電気通信社(平成10年10月)、p.25-−121 (2)日工フォーラム社:エネルギー(フジサンケイグループのENERGY 総合誌)vol.31,No.6,1998、(1998年6月)、p58-77 (3)資源エネルギー庁:原子力発電関係資料(1999年3月)、p54-55 (4)電気事業連合会統計委員会:平成10年版 電気事業便覧、(社)日本電気協会(1998年9月)、p48-49
|

