|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
民生部門では家庭、業務ともにエネルギー消費量が大きく増大してきたが、1995年以降、横ばい乃至微増、2011年以降は減少の傾向が見られる。家庭部門では、家電製品の多様化と大型化、生活様式の変化などが増加要因であったが、2004年度をピークにエネルギー消費は減少傾向にあり、特に2011年度からは東日本大震災以降の節電意識の高まりなどによって更に減少が進んだ。業務部門では、床面積当たりのエネルギー消費原単位は石油危機の後に改善された。増加要因としては、床面積の急速な増大、OA機器の普及などがあげられるが、省エネ機器の普及、2011年以降の省エネ志向により減少傾向となった。運輸部門では、旅客輸送量の急増および乗用車へのシフトにより旅客輸送のエネルギー消費が増大したが、2004年をピークに省エネ法におけるトップランナー制度による高効率輸送機器等の導入が徐々に効果を発揮して個別輸送機関の原単位が改善されたことにより減少傾向となっている。貨物輸送は、旅客輸送よりは緩やかであるが、トラック輸送の増加によりエネルギー消費は増加してきたが、産業構造変化により輸送量の伸びは鈍化している。なお、2010年よりトラック輸送について軽トラックは対象外となり、以降輸送量は減少の形となった。運輸部門における、トラック単体の低燃費化や輸送効率の向上により、エネルギー消費は減少傾向である。特に、2011年の東日本大震災以降、エネルギー消費はどの部門についても、減少傾向である。 <更新年月> 2017年02月
<本文>
経済成長とエネルギー需要との関係については、これまでの多くの専門家等による実証的分析により、以下のことが明らかにされている。 ・経済成長とエネルギー消費の間には、相関関係がある。 ・エネルギー需要の対GDP弾性値は、省エネルギー等の努力をしなければ、長期的には1に近くなる。 ・弾性値は、高度成長期には高くなり、低成長期には低くなる傾向がある。 わが国の過去のGDP成長率とGDP弾性値の推移は、四つの期間に分けることができる。第一期は、GDP弾性値がすべて1以上なっている期間、第二期はGDP弾性値が非常に低い、エネルギー消費の伸びが低い時期、第三期は、省エネルギー等の努力が全体として少なく、GDP弾性値が1に近い時期。第四期はいわば第三期以降であるが、GDP弾性値はマイナスの傾向である(日本の部門別エネルギー消費(産業部門およびエネルギー転換部門)<01-02-03-06>の表1参照) 第一期から第二期への移行は、各消費部門でのエネルギー消費原単位を減少させる省エネルギー努力が行われたことによるが、大きな役割を演じたのは、産業部門である。第三期においては、民生及び運輸部門のエネルギー消費の対GDP原単位は、増加の傾向があることが特徴となっている。第四期の分け方については、定説はないが、再度の省エネルギー効果の発揮や省エネルギー意識の向上等により、エネルギー弾性値はマイナスとなることが多い。 1. 民生部門 民生部門は、自家用運輸を除く家庭部門と、事務所ビル、ホテル、病院、学校、理容業、店舗等を対象とする業務部門に大別される。また、産業部門の中で、第二次産業の事務所と第三次産業の大部分(運輸業、エネルギー転換事業を除く)が業務部門に含まれる。2011年度の民生部門のエネルギー消費は94.625×1013kcalに対して、2014年度ではエネルギー消費は88.273×1013kcalで対前年度比3.3%減、最終エネルギー消費の約28.2%と減少傾向である。 (a)家庭部門 家庭部門のエネルギー消費(図1)は、所得の向上、生活様式の変化とともに、1965年以降2002年頃までは増大傾向であるが、機器の省エネ性向上や2011年の東日本大震災以降は省エネ意識の浸透により、近年は減少傾向となった。消費量は1965年度に10.696×1013kcal、2002年度に54.256×1013kcalであり、2014年度は48.761×1013kcalである。1965年度から2002年度までの年平均伸び率は約4.7%である。用途別にみると、厨房用を除き、どの用途も増加してきたが、伸び率では特に冷房用と動力・照明用が大きい。 燃料種別にみると(図2)、電力、都市ガス、LPGの増加が大きいが、特に電力の伸びは顕著である。電力は、2000年度の家庭用エネルギー消費の42.8%を占めていたが、近年オール電化住宅の普及拡大もあり、2009年度は電気のシェアは50%を超え、2014年度は50.9%となった。太陽熱利用は、1980年代における温水器の普及が進展したが、1990年代に入って伸び悩んでおり、2000年度以降、減少傾向である。太陽熱の家庭用エネルギー消費に占める割合は1%以下である。1995年以降は、長引く不況の影響もあるが、家庭用機器のエネルギー消費効率が大幅に向上したことから、全体として家庭部門におけるエネルギー消費の伸びは見られなくなってきた。更に、2011年の東日本大震災以降、省エネ意識も高まり、エネルギー消費は減少傾向となった。 (b)業務部門 業務部門のエネルギー消費(図3)は、家庭部門に比べてエネルギー価格や経済状況の影響を強く受ける。消費量は1965年度に8.004×1013kcal、2002年度に48.046×1013kcalである。この間、高度経済成長期には急増したが(1965〜1973年度で平均年率15%増)、第一次石油危機(1973年)以降1980年代半ばまで平均年率1.3%とほぼ横這いとなり、1980年代後半からのバブル経済期には再び増加傾向が強まった。その後は2000年代後半からのエネルギー価格の高騰や2008年の世界金融危機を背景に、業務他部門のエネルギー消費量は減少傾向に転じた。 用途別に見た場合、動力・照明、冷房、給湯、暖房、厨房の5用途に分けられるが、動力・照明用のエネルギーが、OA化などを反映して高い伸びを示した。その結果、動力・照明用の業務他部門のエネルギー消費全体に占める割合は、2014年度では44%に達した。 燃料種別には(図4)、電力の割合が増加傾向にある。ガスもコジェネレーションシステムなどの普及拡大に伴い増加傾向を示している。一方、主として暖房用に利用される石油は減少傾向にある。業務部門の2014年度における最終エネルギー(39.497×1013kcal)のうち、59.7%が電力(23.411×1013kcal)である。 (c)エネルギー原単位 民生部門の「エネルギー消費原単位」の推移を図5に示した。これは、家庭部門については世帯当たりの、また業務部門については床面積当たりのエネルギー消費量を表したものである。1973年の第一次石油危機までは、同様なペースで上昇しているが、それ以降は業務部門の原単位が低下したのに対して、家庭部門ではなお若干の上昇傾向を示している。 住宅断熱の普及・強化、家電製品単品の効率改善等の省エネ対策にも関わらず、生活の利便性・快適性を追求する国民のライフスタイルの変化、世帯数の増加などの社会構造変化の影響を受け、個人消費の伸びとともに著しく増加した。1973年度の家庭部門のエネルギー消費量を100とすると、2000年度には216.9まで拡大した。その後、省エネルギー技術の普及と国民の環境保護意識の高揚に従って、家庭部門のエネルギー消費量は低下傾向となり、2014年度は196.1まで低下した。業務他部門のエネルギー消費の推移を見ると、2000年代後半から空調機器の普及は一巡したこと及び機器のエネルギー消費効率の上昇により、低下傾向に転じた。また、暖房用のエネルギー消費原単位は、ビルの断熱対策が進んだことや「ウォームビズ」に代表される、様々な省エネルギー対策が進展したことなどから、減少傾向で推移し、2005年度から2014年度の9年間で平均3.8%の減少を示した。 2. 運輪部門 運輸部門は、乗用車やバスなどの旅客部門と、陸運や海運、航空貨物などの貨物部門に大別される。2014年度、運輸部門は最終エネルギー消費全体の23.1%を占めており、このうち、旅客部門のエネルギー消費量が運輸部門の60.2%、貨物部門が39.8%を占める。輸送サービスの規模を統一的に表す概念として、旅客の場合は人km、貨物の場合はトンkmが用いられる。 (a)旅客部門 これまでの旅客輸送量の推移(図6)をみると、増大期と停滞期を繰り返しながらも、同期間の実質GDPの伸び率4.3%に伴って上昇してきたことが分かる。1965年度(415.827×十億人・km)から2000年度(1,419.695×十億人・km)までの年平均伸び率は3.5%であった。その後、旅客、貨物ともに輸送量は横ばい傾向になったが、2011年以降、旅客は増加傾向、貨物は統計変更により減少となった。 輸送機関別には、自家用乗用車の伸びが著しく、輸送量全体に占める割合は、1965年には15%であったが、1998年度には約60%に達した。その後、2014年度では61.3%となっている。鉄道は、第二次石油危機(1979年)の後に再び徐々に増加し始め、2000年代に入って微増の状態が続いている。航空は国内飛行場及び路線の急速な整備とともに、伸び率で増加してきたが、航空は長距離旅客中心であるため、輸送量全体に占める比率は6%以下である。 旅客輸送のエネルギー消費量(図7)は輸送量よりもさらに急速に増大してきた。1965年度(7.911×1013kcal)から2014年度(49.245×1013kcal)までの年平均伸び率は2.8%である。2004年度をピークにトップランナー制度の導入効果による改善効果もあり、減少傾向となった。旅客輸送用エネルギー消費の中で乗用車の占める割合は、2004年度88%、2014年度は約84%である。 (b)貨物部門 貨物輸送は、景気の変動、産業構造の変化(輸送商品の変化)等の経済活動の影響を大きく受ける。これまでの貨物輸送量の推移(図8)をみると、高度経済成長期には急速に輸送量が増大した。その後は経済状況に応じて変動しながら、2002年度までの緩慢な増大傾向の後、横ばいとなった。全体として緩慢な増大をしている。1965年度(186.421×十億トン・キロ)から2002年度(570.733×十億トン・キロ)までの年平均伸び率は3.2%である。 輸送機関別には、トラック輸送が大幅に増大し、鉄道輸送が減少してきた。トラックは2002年度に貨物輸送全体の約54.7%を占めている。船舶による輸送は1973年の第一次石油危機当時は輸送全体の約51%を占めていたが、2002年度には41.3%に低下した。なお、航空輸送は急速に増加してきているが、貨物輸送全体からみるとまだきわめて小さく、2002年度の構成比率は0.2%弱で、以降、横ばいである。 輸送機関がエネルギー原単位の悪いトラック輸送にシフトしてきたものの、個別輸送機関の原単位の改善で、貨物輸送のエネルギー消費量は、輸送量と同程度の速度で増加してきた(図9)。1965年度(11.146×1013kcal)から2002年度(32.069×1013kcal)までの年平均伸び率は2.85%である。2002年度のエネルギー消費に占めるシェアはトラックが80.8%、船舶が17.1%であったが、2014年度はトラック(24.664×1013kcal)が87.5%と増加し船舶(2.833×1013kcal)が10.7%と低下した。 (c)エネルギー原単位 旅客輸送と貨物輸送の平均エネルギー原単位の時間的推移(図10)をみると、旅客輸送が一時的な低下はあるものの、長期間にわたって上昇し続けているのに対して、貨物輸送では短期的変動をしながらも概ね一定の原単位で推移してきた。旅客輸送の一貫した上昇は、他の輸送機関に比べて原単位の大きい乗用車へのシフトによるが、2004年度をピークに減少傾向となった(表1)。この要因、トップランナー制度による乗用車の効率改善、高速道路システムなどによる道路渋滞の解消などが挙げられる。 一方、貨物輸送においては、個別輸送機関の原単位がかなり改善したため、平均原単位の増大が抑制されているが、2010年度以降は貨物自動車の統計から自家用軽自動車が除外されたこと、原単位の大きいトラックへのシフトなど、平均原単位を増加させる要因となっている。貨物輸送の場合には、積載効率の向上など輸送方法の改善で原単位を下げる余地があり、さらにETCシステム、カーナビの普及、物流の効率化など人と道路と車両の情報をネットワーク化することなど、新しい交通システムの導入により、今後は原単位の改善が期待できる状況にある。 なお、旅客、貨物ともに自動車輸送へのシフトが進んだため、運輸部門のエネルギー消費に占める石油の割合は1965年度の83%から2002年度には98%まで高まったが、2014年度では95.3%となった。また、運輸部門は同年度の最終消費部門石油消費量の44.6%を占めており、産業部門とほぼ等しい(参考文献(1)のp.216−217、p.470−471、参考文献(2)参照)。石油消費量の低減がエネルギー安定供給の確保と、環境保全に不可欠であり、運輸部門における石油代替エネルギーの確立が今後の大きな課題である。 (前回更新:2005年2月) <図/表> 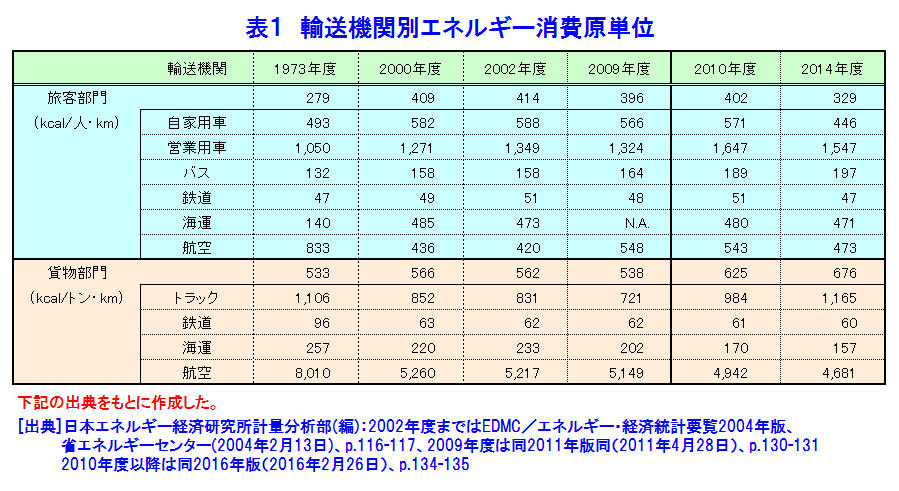
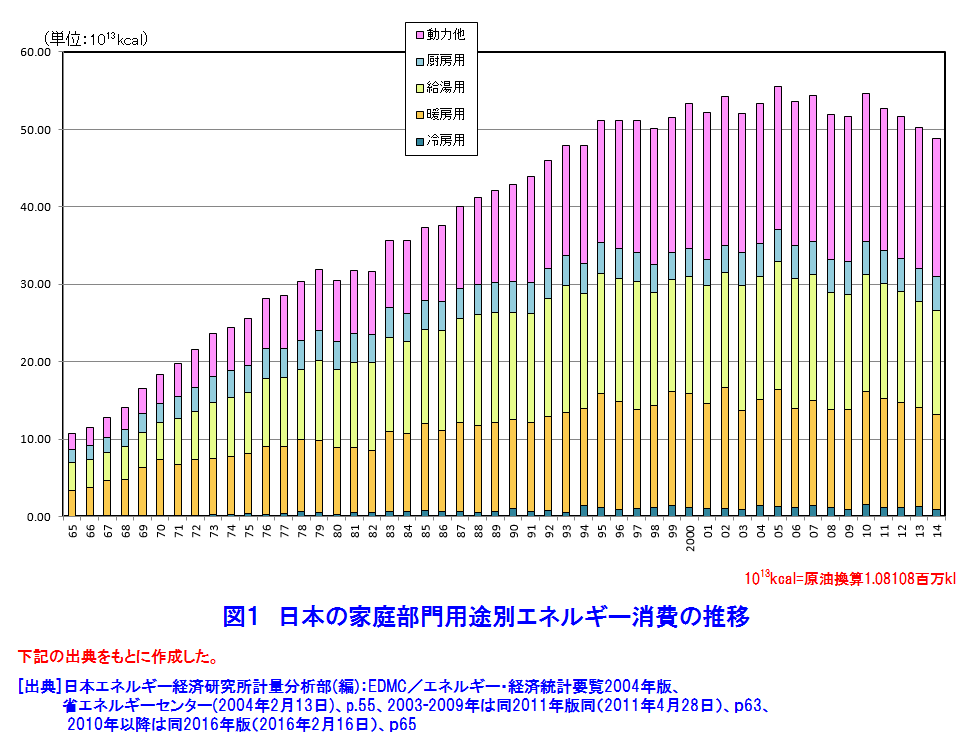
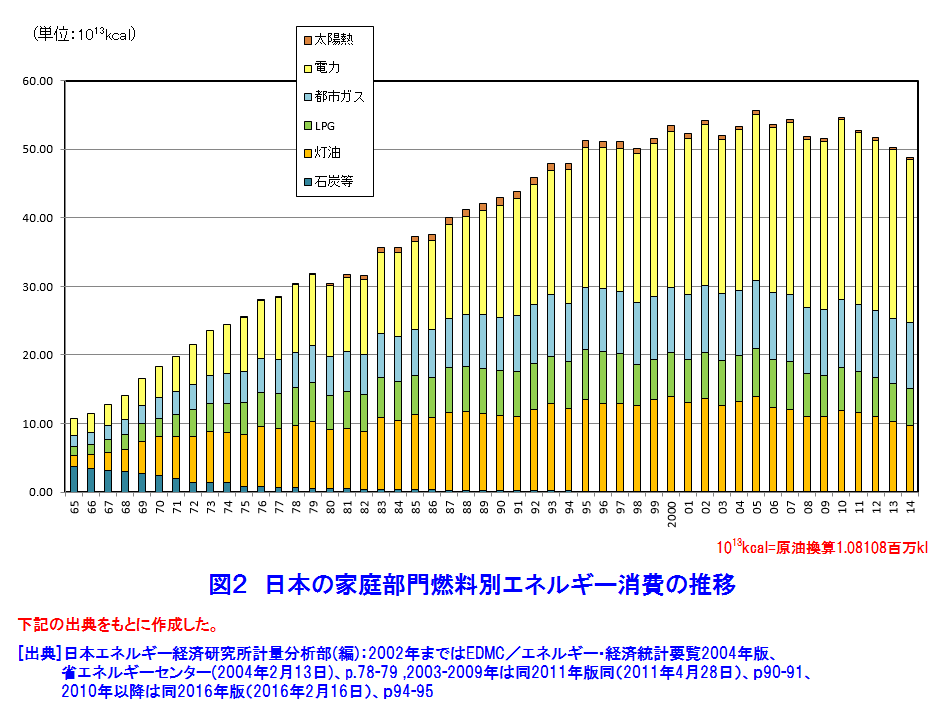
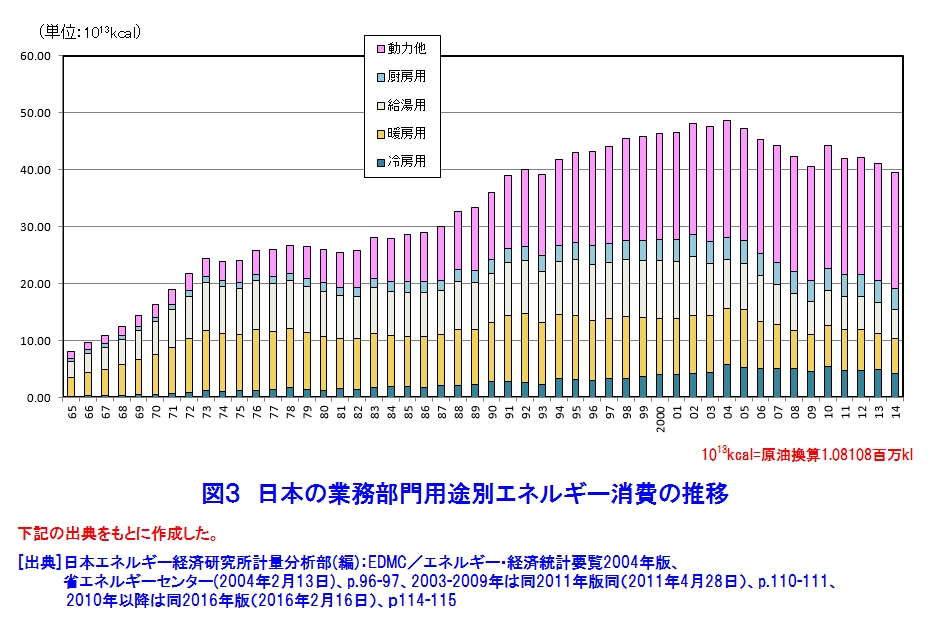
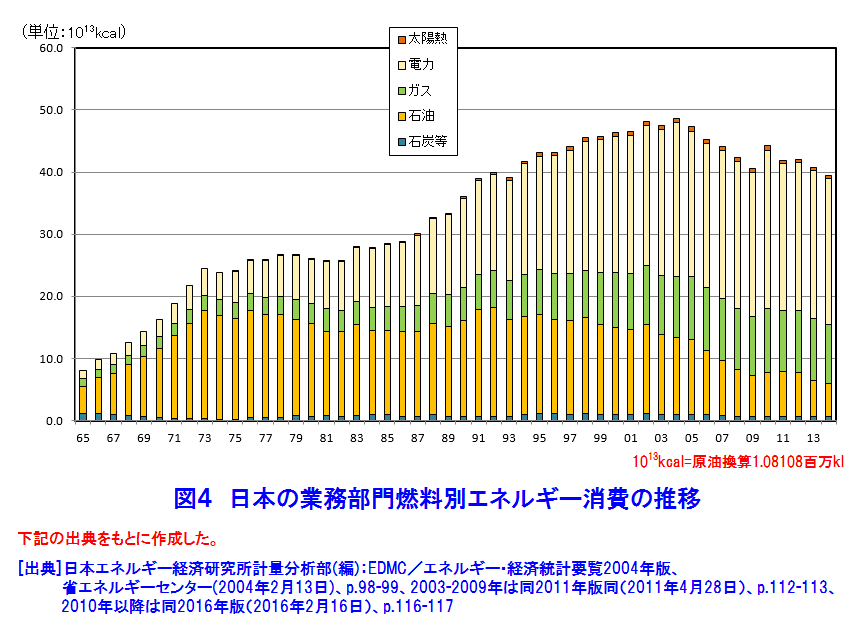
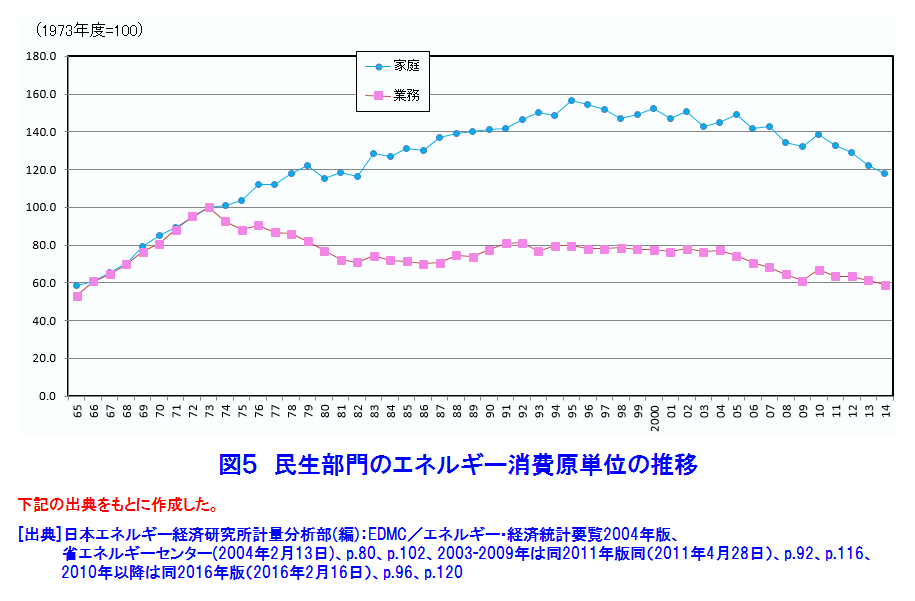
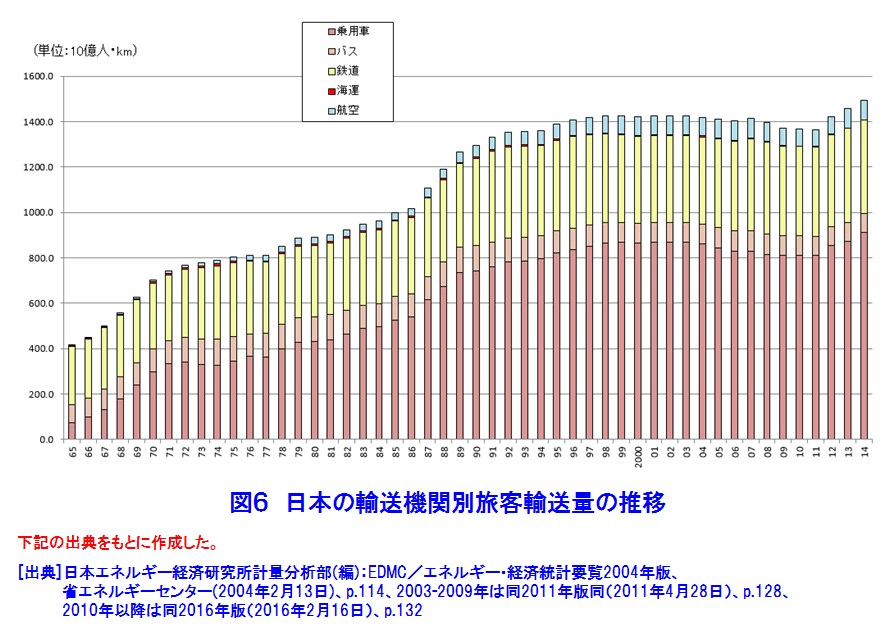
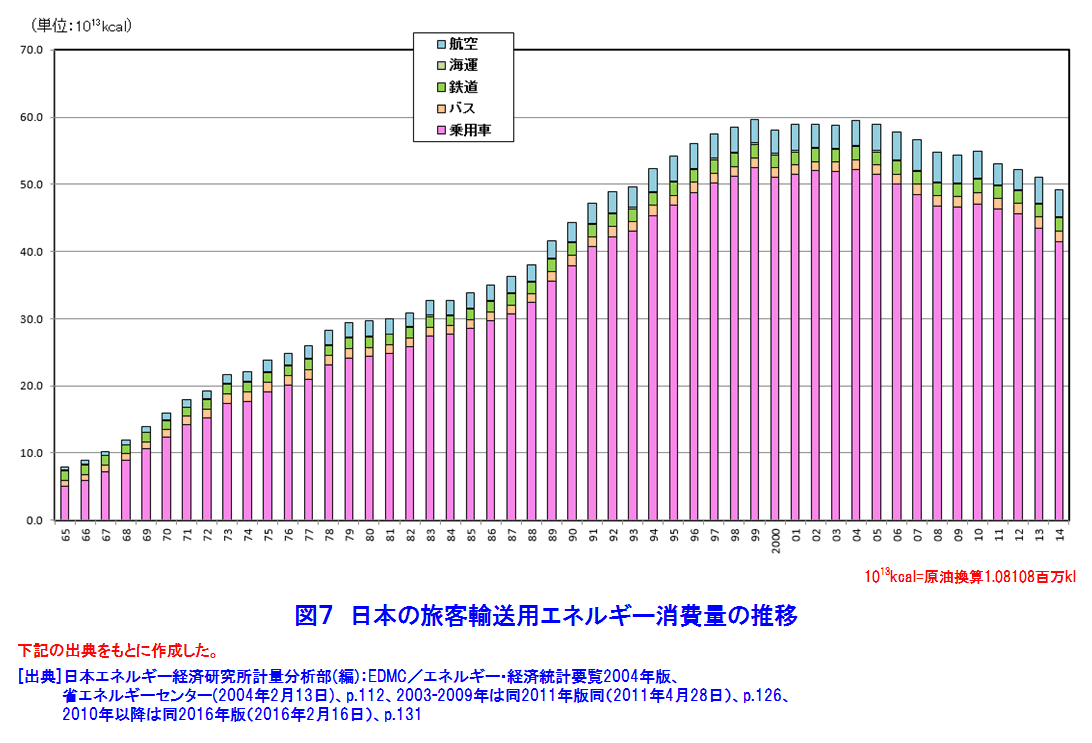
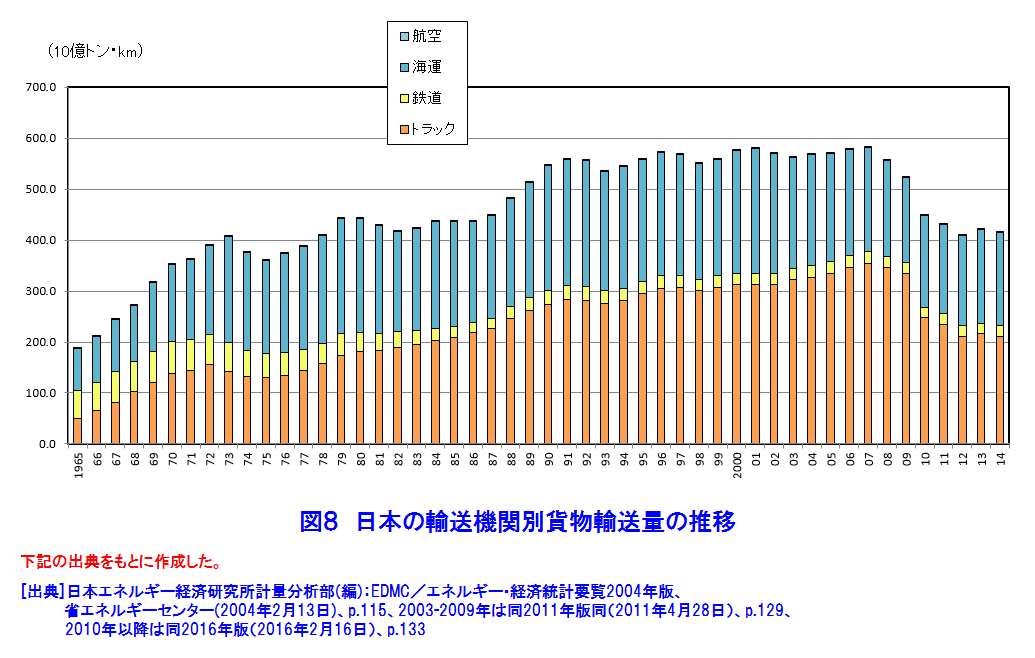
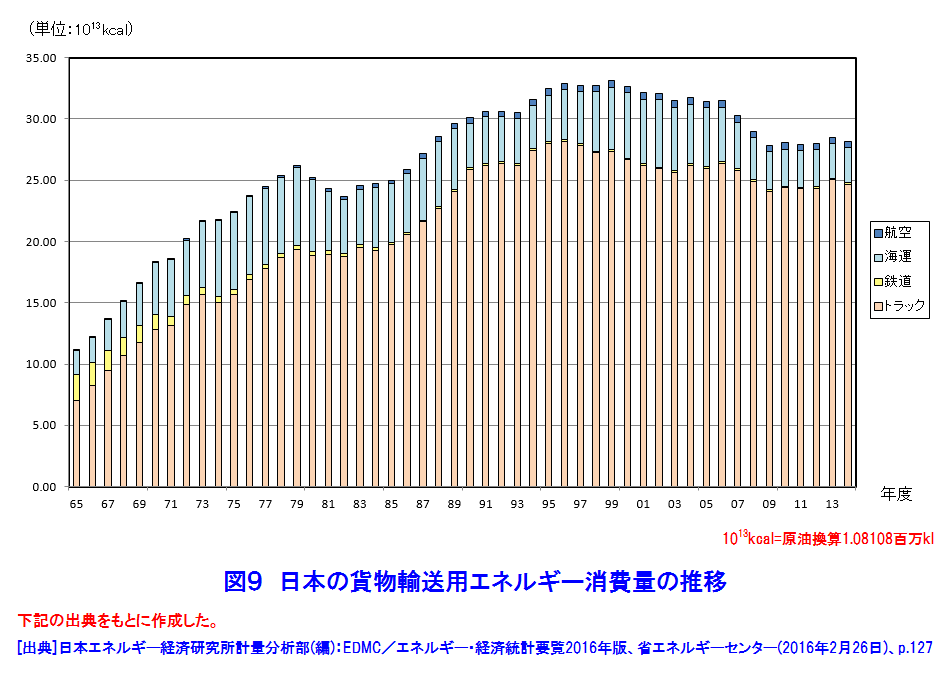
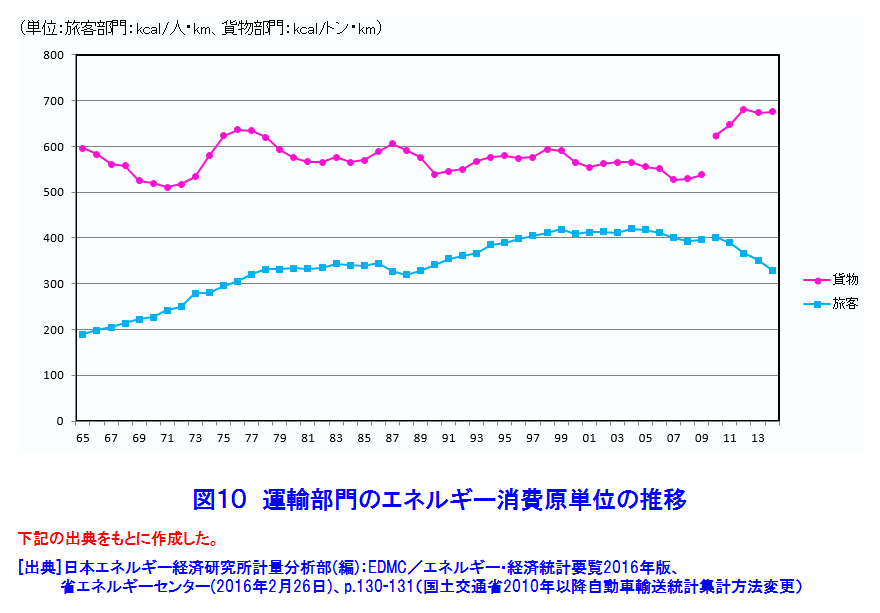
<関連タイトル> 日本の部門別エネルギー消費(産業部門およびエネルギー転換部門) (01-02-03-06) 需給構成とその推移 (01-07-02-07) 主要先進国のエネルギー需要の動向 (01-07-02-08) <参考文献> (1)日本エネルギ−経済研究所エネルギー計量分析部(編):EDMC/エネルギー・経済統計要覧(2004年版)、省エネルギーセンター(2004年2月) (2)日本エネルギー経済研究所エネルギー計量分析部(編):EDMC/エネルギー経済統計要覧(2011年版)、省エネルギーセンター(2011年4月) (3)日本エネルギー経済研究所エネルギー計量分析部(編):EDMC/エネルギー経済統計要覧(2016年版)、省エネルギーセンター(2016年2月) (4)資源エネルギー庁長官官房総合政策課(編):総合エネルギー統計簡易表平成27年版、(株)通商産業研究社(2016年11月) (5)電気事業連合会統計委員会(編):平成28年度電気事業便覧、日本電気協会(2016年12月) (6)資源エネルギー庁(編):エネルギー白書2016年版(2016年5月)
|

