|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
産業部門全体としては、第一次石油危機の後にエネルギー消費が大幅に減少したが、1980年代半ばから再び増加傾向となり、最近では第一次石油危機当時の水準より20%程度高くなっている。この間、素材系産業では鉄鋼業が近年横這い、化学工業の消費が増大、金属機械とその他製造業のエネルギー消費も増えてきた。これら業種では主に電力を利用するため、電力消費量が増大する要因となっている。鉱工業生産指数当たりでみたエネルギー消費量は、石油危機以降どの業種でも低下したが、1990年以降やや増加傾向はあるものの2000年以降横ばいとなり、最近では各業界効率改善により低下傾向となっている。エネルギー転換部門の中では、特に発電部門が重要となっている。発電部門では石油危機以降、原子力、LNG火力等の代替電源の導入を通じて脱石油が進められたが、2011年の東日本大震災以降、原子力発電の運転が困難となり、LNG、石炭、石油等による火力発電の効率向上が図られている。 <更新年月> 2017年02月
<本文>
経済成長とエネルギー需要との関係については、これまでの多くの専門家等による実証的分析により、以下のことが明らかにされている。 ・経済成長とエネルギー消費の間には、相関関係がある。 ・エネルギー需要の対GDP弾性値は、省エネルギー等の努力をしなければ、長期的には1に近くなる。 ・高度成長期には、弾性値は、高くなり、低成長期には低くなる傾向がある。 表1は、わが国の過去のGDP成長率とGDP弾性値を示したものである。これによると、四つの期間に分けることができる。第一期は、GDP弾性値がすべて1以上なっている期間、第二期はGDP弾性値が非常に低い、エネルギー消費の伸びが低い時期、第三期は、省エネルギー等の努力が全体として少なく、GDP弾性値が1に近い時期であるが、それ以降のGDP成長率が低く弾性値も概ね1以下の時期を第四期とした。 第一期から第二期への移行は、各消費部門でのエネルギー消費原単位を減少させる省エネルギー努力が行われたことによるが、大きな役割を演じたのは、産業部門である。 1. 産業部門のエネルギー消費の推移 一般に、産業部門は製造業、非製造業および第三次産業から成っている。最終エネルギー消費部門の区分においては、このうち第三次産業を民生部門(業務部門)として取り扱うために、産業部門では製造業と非製造業(農林水産業、建設業など)のエネルギー消費が対象となっている。 製造業と非製造業のエネルギー消費量の推移を、他の最終消費部門とともに、図1に示した。製造業のエネルギー消費は、高度経済成長期に急速に増加したが、1973年の第一次石油危機を契機に減少に転じ、1980年代半ばまでは減少傾向が続いた。しかし、その後再び増加し始め、現在は概ね第一次石油危機当時の水準に戻っている。非製造業のエネルギー消費も2度にわたる石油危機の直後は一時的に減少に転じたが、その後緩やかに増加し、1995年度頃にピークに達した後、年ごとにほぼ3%程度減少し、2014年現在ではピーク値の50%以下となっている。また、2000年頃にはエネルギー消費量は第一次石油危機当時の値よりは20%程度高くなったものの、1998年に導入されたトップランナー制度等も徐々に効果を発揮し、2014年現在、エネルギー消費は全般的にピーク値より15%程度改善されている。 製造業のエネルギー消費を部門別にみると(図2および図3)、高度経済成長期には鉄鋼、化学、窯業土石、紙・パルプの素材系4産業の消費が、素材生産量(図4)とともに急速に増大し、構成比も製造業全体の8割弱まで高まった。しかし、第一次石油危機の後は、素材生産量の減少、省エネルギー技術の開発導入等によって大幅にエネルギー消費が減少した。 その後、1980年代半ばからエネルギー消費全体が再び増加する中で、鉄鋼業では粗鋼生産が1億トン前後で推移したためエネルギー消費は横這いとなったが、2002年には増加に転じる傾向が見られる。化学工業ではエチレン等の基礎化学品の需要とともに1980年代以降大幅に増加してきたが、1999年以降横這い傾向にある。窯業土石と紙・パルプは緩やかな増加傾向となった。これらの結果として、産業全体に占める素材産業の比率は1980年代半ば以降はあまり低下していない。 一方、非素材系産業の中では繊維工業の消費が石油危機以降減少したものの、金属機械とその他製造業(衣服・身回品、家具、印刷・出版、ゴム製品等)の消費が、石油危機の影響をある程度受けながらも、増大してきている。これらの業種では、石油、石炭等の燃料に比べて電力の消費が多いため、産業部門全体の電力消費が増大する要因ともなっている。 2度にわたる石油危機によって石油供給の量、価格両面での不安定性が明らかとなり、省エネルギーに向けての官民あげての取り組みが展開された。鉱工業生産指数当たりのエネルギー消費量の推移(図5)をみると、第一次石油危機(1973年)の2〜3年後からこうした対策の効果が現れはじめ、どの業種でも1980年代半ばまで急速にエネルギー原単位が低下している。1973年度の原単位を100とした場合、1990年度には素材系平均で56.8、非素材系平均で68.1まで低下した。しかし、その後は石油価格の下落の影響が大きく、原単位は逆に悪化し、2002年度には素材系平均で約64、非素材系平均で約85まで上昇したが、製造業全般の効率改善により、2014年では素材平均で約55、非素材平均で約69に低下した。 2. エネルギー転換部門 エネルギー転換部門とは、一次エネルギーを産業、民生、および運輪部門で消費される最終エネルギーに転換する部門であり、石油精製、コークス製造、熱供給、発電等の事業から成っている。近年、産業部門における構造転換や民生部門のエネルギー消費の増大によって電力消費量の伸びが大きいため、エネルギー転換部門の中でも発電部門がとりわけ重要な位置を占めるに至っている。2000年度には、一次エネルギー供給全体の中で、電化率は22.5%、2014年度の段階では25.3%と電化率が上昇している。 わが国の電源別発電電力量(9電力会社)の推移(図6)をみると、発電用燃料としての石油の消費量は第一次石油危機をピークに徐々に減少し、1998年度以降、石油火力の発電量は全発電量の1割以下(9電力会社計での割合、以下同じ)にまで低下している。石油火力の代替となったのは原子力とLNG火力であり、2001年度における発電量のシェアはそれぞれ39.0%および32.5%にまで増加した。また、原子力と水力とを合わせた非化石エネルギーによる発電比率は、同年に47.4%に達している。2011年の東日本大震災の後、原子力の運転が困難となり、2014年度では原子力0%となり、代わりに火力による発電が石油、石炭、LNGを併せて91%となった。図7に9電力会社および自家用を合わせた電力量の発電方法別の割合を示す。 このように火力発電の占める比率が9割を超える段階となり、投入燃料の減少に向けて発電効率の向上が重要な課題となってきた。火力発電所の平均熱効率の推移(図8)をみると、1950年代初期には20%以下の水準であったが、蒸気の高温高圧化等の技術革新によって1970年度には発電端効率で38%弱の高水準を達成していたが、さらに改善が図られ、ここ数年複合サイクル発電技術の利用が本格的し、43%近くまで効率が上昇してきた。 将来的には、エネルギー全体の中でも特に電力の需要が増大すると予想されることから、今後とも発電部門での非化石エネルギー利用の推進と火力発電効率の向上とが重要な課題となっている。 (前回更新:2005年2月) <図/表> 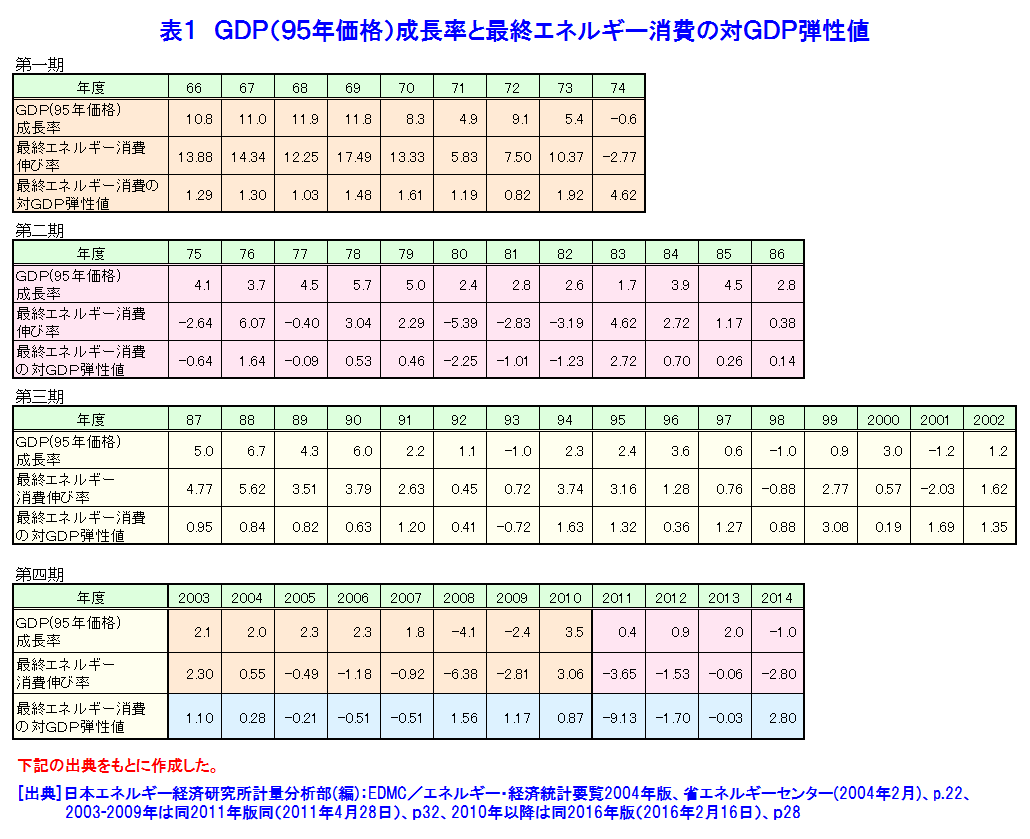
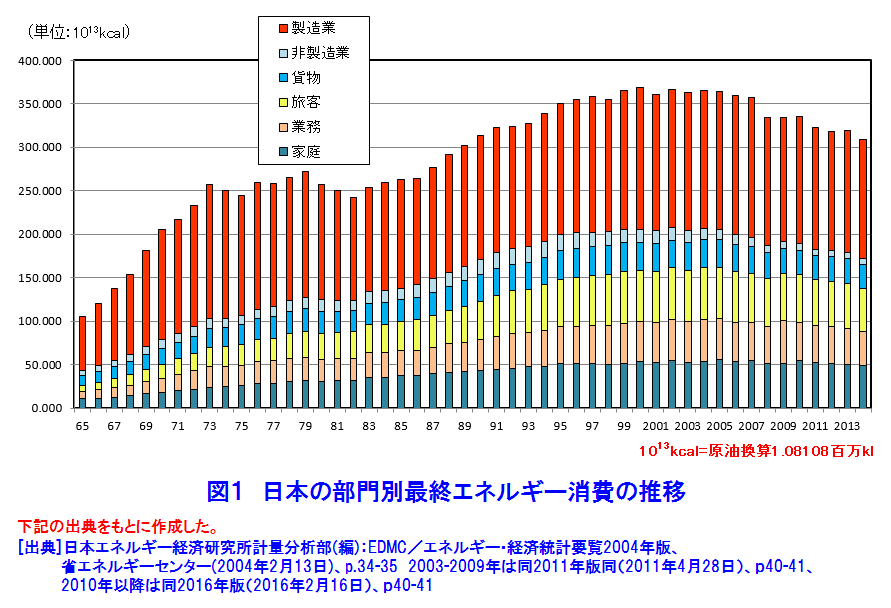
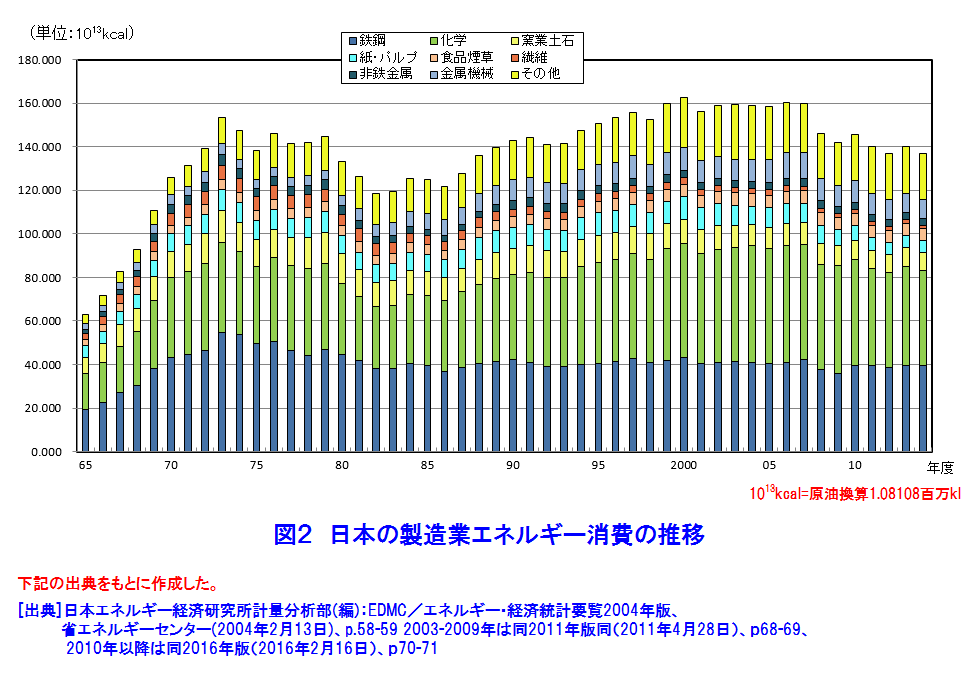
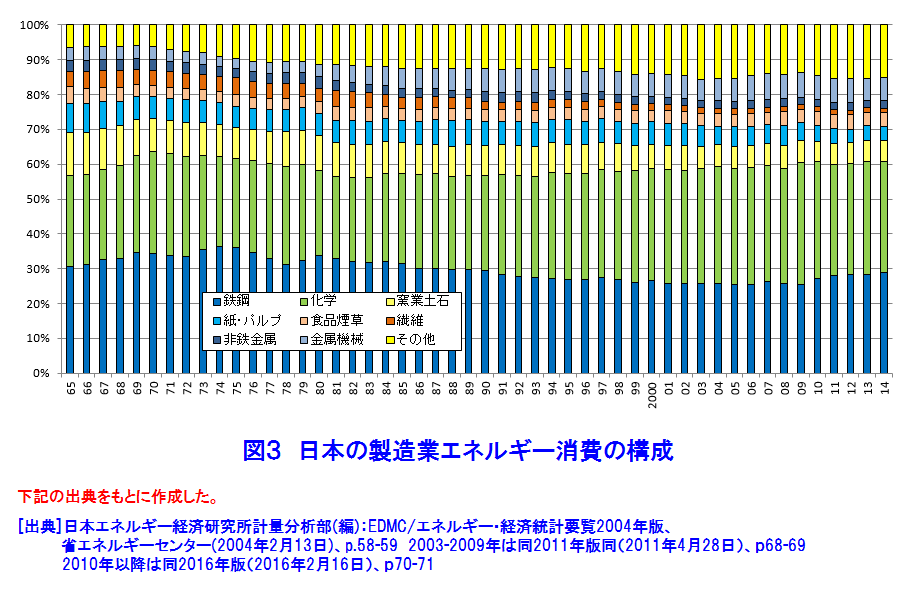
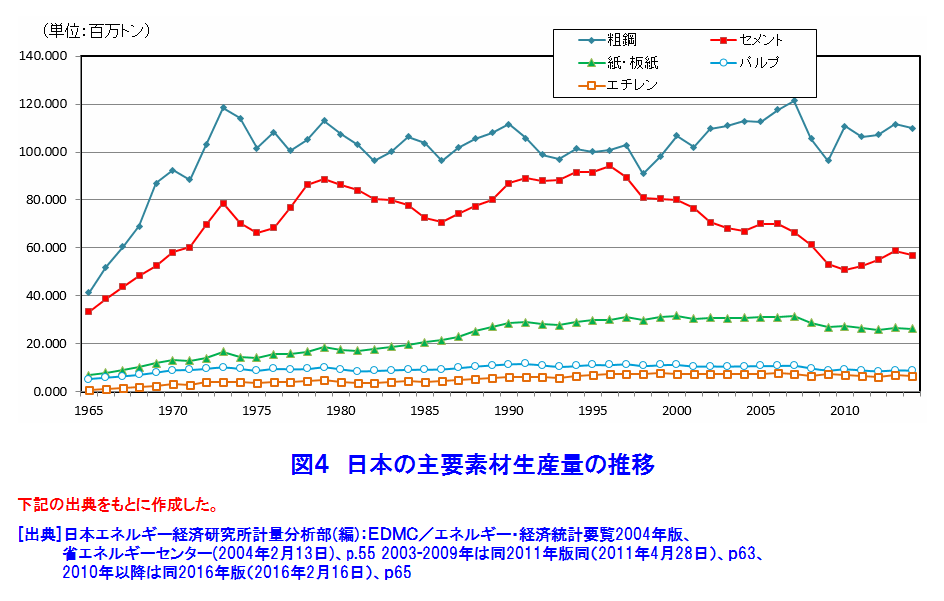
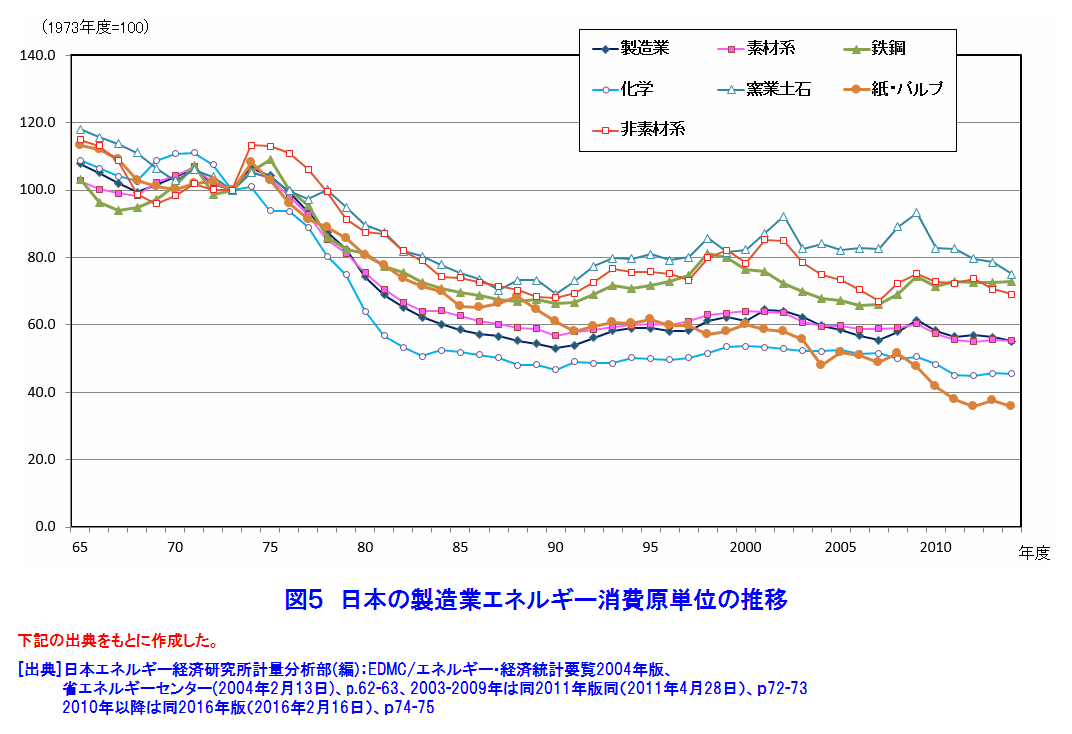
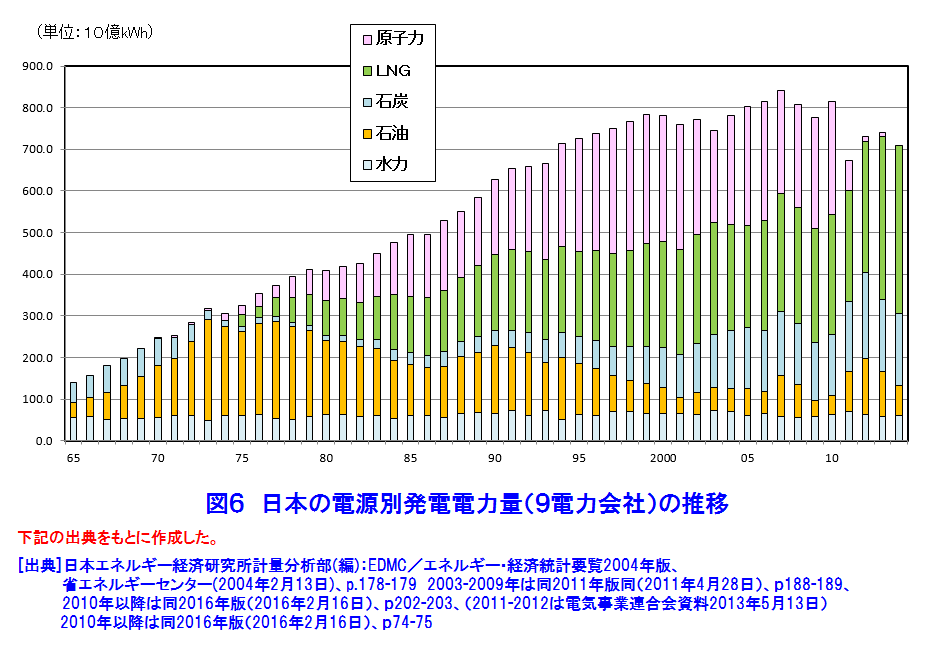
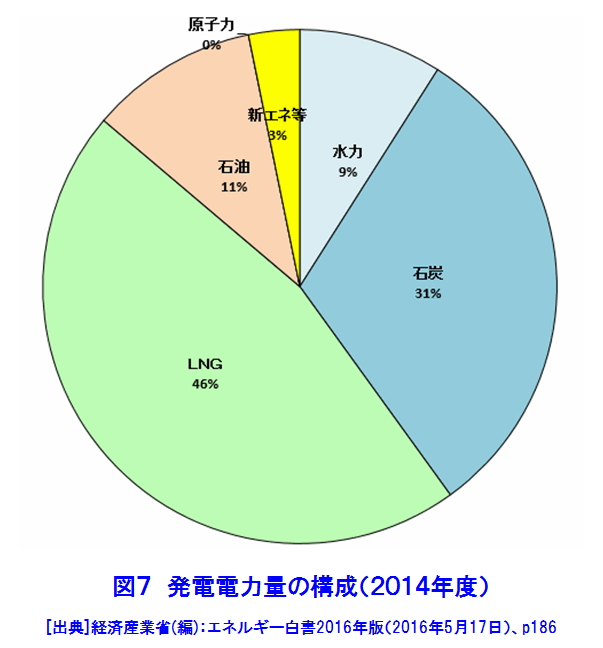
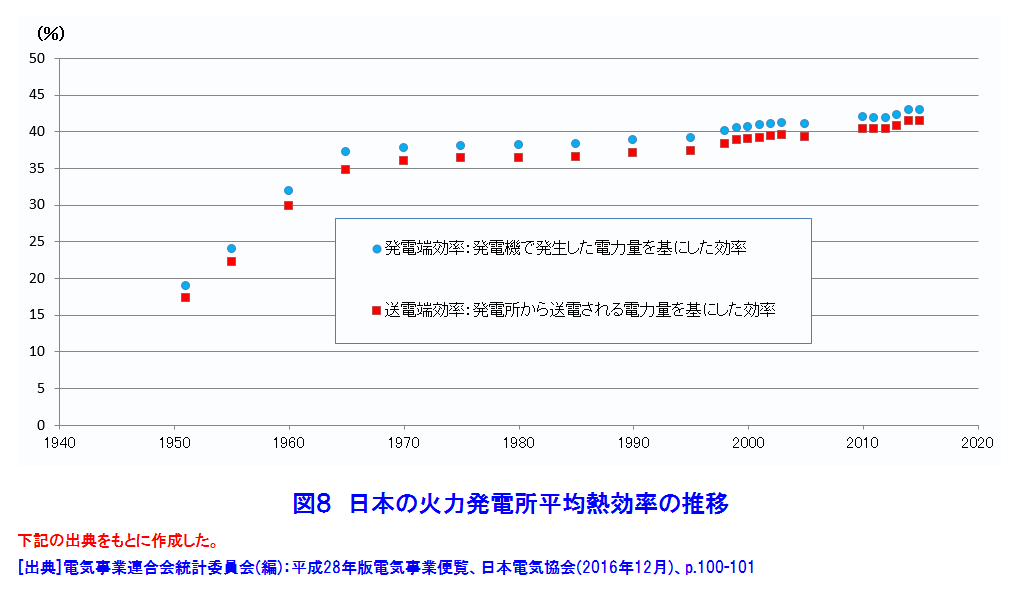
<関連タイトル> 日本のエネルギー供給とその推移 (01-02-02-01) 石油危機と日本 (01-02-03-04) 日本の部門別エネルギー消費(民生部門および運輸部門) (01-02-03-07) <参考文献> (1)日本エネルギ−経済研究所エネルギー計量分析部(編):EDMC/エネルギー・経済統計要覧(2004年版)、省エネルギーセンター(2004年2月) (2)電気事業連合会統計委員会(編):平成16年度電気事業便覧、日本電気協会(2004年10月) (3)資源エネルギー庁(編):エネルギー2004、エネルギーフォーラム(2004年1月) (4)経済産業省(編):エネルギー白書2004年版、(株)ぎょうせい(2004年6月)
|

