|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
原子力(放射線も含む)は社会システムとして、現代社会を支える重要なインフラを構成し人々の生活に欠くことのできないものである。しかしながら、事故、不祥事、隠ぺいそして地震災害などが相次いだことによって、原子力発電所等のシステムそれ自体のみならず、その研究・開発・利用を進める組織や構成員への不信感が、社会不安をひき起す要因にもなっている。このような状況のなかで、社会とのよりよい共存状態を構築していくためには、原子力エネルギーや放射線をつくり出し供給する側と需要する側の間に良好な関係があることが望ましい。原子力利用とその研究開発に従事する者に、近年特に社会にむけて果たすべき責任や社会への貢献が問われており、CSR(企業の社会的責任)あるいはSR(社会的責任)の考え方が、電力やメーカーには勿論のこととして、大学などの研究組織に対しても求められつつある。原子力の研究・開発そしてその利用において、SRを実施するための要求事項(要諦)と実践への道筋を示しつつその現状と課題を述べる。 <更新年月> 2007年10月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
21世紀の世界においては、価値観が多様化する中で、グローバル化、情報技術(IT)の発展、国際市場における競争の激化がよりいっそう進行してきた。国際連合が提唱するグローバル・コンパクト(GC、1999年)には、人権、労働、環境、腐敗防止など10の原則が掲げられている。そして、そのような取り組みを行っている企業に対しては、その内容の簡単な報告書をまとめ、公開することを推奨している。つまり、取り組みの評価が市場においてなされるような仕組みを作ろうとしているのである。このような背景のなかで、企業行動に対して、消費者・顧客、NGOおよび一般社会からは、以前にも増して厳しい批判が発せられるようになってきた。そして、とりわけ欧米諸国においては、宗教的価値基準と行動規範を基盤として、企業やその他の組織においてCSRへの関心が広範かつ急速に高まってきた。その傾向は日本にも徐々に浸透してきている。このような高まりを助長する動きに、「SR(Social Responsibility)規格(ISO26000)」の策定(2008年秋目処)がある。 原子力を推進する企業活動や研究活動にSRを取り入れ、その実践方法を導くために、以下の6項目にわたる要諦が挙げられている(Sawada et al.,2007)。すなわち、1)原子力におけるSRの位置づけ(特に安全文化や品質マネジメントシステムとの相互関係)の明確化、2)原子力版「SRイニシャティブ」の作成、3)原子力SR推進ツールの開発、4)SR対応事例の調査と分析、5)原子力SR行動憲章と行動基準の検証、6)SR適合性の評価手法の開発である。 原子力版SRイニシャティブは、原子力の研究・開発・利用活動に関わる「行動憲章(理念)」と「行動基準」からなる。SR推進ツールは、「SR主要要素マトリクス」と重要課題(イシュー:issues)ごとの「主要項目と参考事例」から構成される。一般的なSRのイシューには、環境、人権、労働慣行、公正取引、組織統治(ガバナンス)、汚職(腐敗防止)等々がある。 日本で特に重要視される要目に、“安全・安心”、“衛生管理”、“情報マネジメント(過剰報道への対応)”がある。これら日本の特異性が高い要目のSRイシューへの取り込みの必要性と意義を明らかにして、原子力SRイシューを規定し、主要項目と事例を可視化することが求められている(表1に例を示す)。 例えば、ひとつのイシューとして、「技術者倫理や研究活動規範に関する理解の促進」がある。このイシューつまり重要課題を実践するための主要項目としては、倫理ヘルプラインの設置や内部統制の強化が考えられる。事例は表に示した通りである。 原子力のSRを企業や研究現場で実戦する枠組みを構築する試みは一部で始まったばかりであるが、以下のような取り組みがこれまでになされている。 1)原子力研究行動憲章の作成(有冨他、2007)、 2)SR教育、 3)市民のエンゲイジメントの模索(「市民参加型フォーラム」の実施)。 また、今後の課題として次のものが挙げられる。 4)SRへの取り組みの広報、例えば行動憲章の携行、ポストイット・シールなどによる周知努力、 5)GRI(Global Reporting Initiative)に基づく原子力研究SRレポートの発行、 6)原子力従事者倫理ヘルプラインの設置、 7)一般社会に向けた原子力ヘルプラインの設置である。 「SRで原子力の世界的問題は解決できるか?」という問いかけに答えることはそう単純ではない。少なくとも、SRへの取り組みだけでは不十分である。特に、低開発国の経済的困窮つまり貧困の問題を解決する手段として、原子力がどのような力になり得るかを考えたとき、その解決は容易ではない。また、極度の貧困状態は「もうこれ以上失う物はないという考え方」を生む。そのような社会状態が、テロ、地域紛争、戦争を引き起こすことがあり得る。つまり、経済的な発展途上にある国が、地球総体として見た場合の持続的な発展(サスティナブル・ディベロップメント)を阻害する危険性がある。SRの考え方や実践に加えて、よりマクロな視点に立って地球総体の均衡を考えることとそこに原子力が果たせる役割について、SRの考え方を包み込むこれまでにない哲学が必要である。 <図/表> 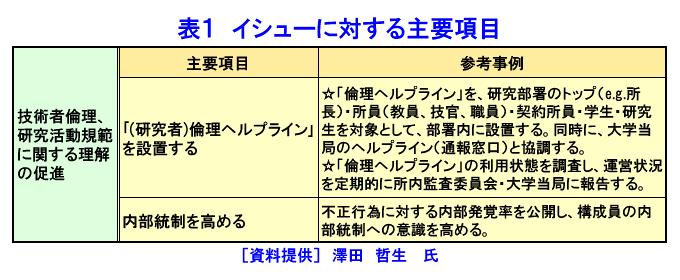
<関連タイトル> 技術者倫理概説 (10-08-01-01) 国際協力における環境倫理の視点 (10-08-01-02) 日本原子力学会における技術倫理活動 (10-08-01-03) <参考文献> (1)T.Sawada,et al.:Nuclear corporate social responsibility,International Journal of Nuclear Governance,Economy and Ecology 2007 − Vol.1,No.3,p.265-277 (2)田中宏司、澤田哲生、八木絵香、森本俊雄:原子力のCSRとガバナンス−原子力と社会の持続的関係−、東工大[COE-INES](2006) (3)水尾他:「原子力の社会的責任(NSR)に関するコミュニケーション啓発活動への一考察:?組織の持続可能な発展の視点から?」、日本原子力学会2007年秋の大会予稿集、A02 (4)有冨他:東工大原子炉工学研究所のSRイニシャティブ、日本原子力学会2007年秋の大会予稿集、A03 (5)水尾順一、田中宏司:CSRマネジメント、生産性出版(2004) (6)水尾順一、田中宏司他(編):CSRイニシャティブ、日本規格協会(2005) (7)小野桂之介:CSR入門、日本規格協会(2004) (8)A.B.Carroll and A.K.Buchholts,:“Business and Society −Ethics and Stakeholder Management−”6ed(Thomson,2006) (9)N.H.Jacoby:“Corporate Power and Social Responsibility −A Blueprint for the Future−”(Macmillan,1973)
|

