|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
材料や構造物の強度評価に必要な残留応力の測定法である。特性X線を多結晶材料に照射し、反射回折線の情報から応力を求める。結晶面の格子面間隔が応力によって変化するのを、ブラッグの条件を満足する回折角から格子面間隔の変化、さらに計算によりひずみや応力を求める。写真フイルム法と計数管方式がある。 <更新年月> 1996年03月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.はじめに 各種機械や構造物さらにその材料を評価して設計を行う場合、一般にその形状が複雑であり実際に使用される負荷条件などの環境の把握や変化の予測が難しいため、材料力学や弾性学で合理的に評価・解析できないことが多い。事実、予想もしなかったところに、しばしば事故が生じ、対策に苦慮する場合がある。 放射線透過試験や超音波探傷試験によりきずや損傷などが検出されても、破壊力学的な概念を考慮してそれがどの程度危険な状況なのかを総合的に判断する必要がある。 最近は、電子計算機による3次元有限要素法等による強度計算を加味して信頼性を増すことができるが、当初に仮定した条件が実際とどの程度合うか等が問題である。したがって、実験によって計算結果を確認しなければならない。 材料や構造物の強度や安全性を非破壊的に評価するためには、これらが負荷されたときの力(応力)やひずみを知っておく必要がある。特に鋼材の溶接構造物や熱処理を受けた材料では、強度評価をするに当たり溶接部分や母材の持つ残留応力が大きく問題になっている。残留応力の測定法としていくつかの方法があるが、広く用いられているのがX線応力測定法である。 工業材料としての金属材料は多結晶からなり、これに応力が加わると一般に力の方向に伸び、直角方向に縮む。したがって結晶格子面間距離の伸縮などの変化をX線回折法で測定し、弾性力学の諸公式、弾性定数を用いて内部応力を求めることができる。多くの残留応力測定法の中で、X線応力測定は非破壊的測定であり、絶対測定法である。最近の新素材であるセラミックスにも適用されている。 2.X線応力測定の原理 ある方向から特定の波長のX線(特性X線)を材料の表面に投射すると、X線は結晶の各格子面によって散乱する。 図1 に示すように、波長λの入射X線と結晶格子面の角度をθ、その格子面間距離をd, nを正の整数とすれば、 2d sinθ= n λ の関係が成立するとき、隣接する格子面からの散乱X線の位相が等しくなり、干渉して強めあう。即ち角θの方向に強い回折現象が認められる。上式をブラッグの回折条件、θをブラッグ角という。 X線が照射される材料が多数の微結晶粒子で構成され、さらにそれぞれの向きがばらばらであれば、上式を満足する回折X線は円錐状の方向に反射される。このとき、図2のように入射X線の反対側に垂直に写真フイルムを置けば、デバイ環と呼ばれる円形の回折像が得られる。 試験材料に応力が作用したり、内部応力があると、X線の入射角度を変えた場合、デバイ環のプロフィルに変化が生じる。即ち、材料が一様に弾性変形を受け内部応力が存在すると、材料を構成している結晶粒の格子面間隔が変化し、X線回折線は応力のない状態の反射位置から移動するとともにその幅が広がる。この変化を精度よくとらえて材料のもつ応力を知る方法がX線応力測定法である。 X線による応力測定の基礎理論としては、厳密には、x,y,z座標に対して働く応力の方向余弦をもつ6個の伸縮率(ひずみ)を求めて、これらを代数的に解き、応力を計算する。しかし特殊な場合を除き、一般にはX線応力測定法では、X線の侵入深さは 100ミクロン以下という極めて薄い表面層のひずみを測定するため、表面の法線方向の応力成分は零と考えて、2次元応力状態の弾性力学として扱って計算する。 3.X線応力測定の実際 1)特性X線とフィルタ X線応力測定では、材料に適した波長のX線を用いる。 図3はCuをターゲットとしたときのX線スペクトルで、連続的な白色X線(連続X線)のほかに、波長 1.392オングストロームと 1.540オングストローム近傍に鋭い線スペクトルがある。両波長は励起電圧に無関係な元素固有の値である。 実際の応力測定では、短い波長のKβ線(1.392 オングストローム)は邪魔になるためフィルタを用いてカットする。このCu線の場合は、10ミクロン程度のNi箔を用いその吸収端を利用する。 したがって、材料のK吸収端より短い波長のK線を持つターゲット元素では、材料自身による吸収が著しくて使用できない。最適な組合せとして、CoターゲットにFeフィルタ(Co-Fe)は、鋼材・アルミ・銅に適しており、Cr-Vは鋼材・アルミに、Cu-Niはアルミ・銅・ニッケルの測定に用いる。 2)フイルム法(写真法) フイルム法は、回折線の連続環を撮影し、試料・フイルム間距離、回折環の中心からの距離などから、ブラッグ角θを求める。あまり実用化されていないのは、格子定数のわかっている比較試料の箔、粉末などを表面に張り付け、その反射線を同一フィルム上に写し込んで、フイルム距離のチェックをしたり、測定時間(露出ー現像ー定着ー水洗ー乾燥ーミクロホトメータ)・精度(X線回折写真の鮮鋭度)などの問題がある。 その点で計数管法の方がよいが、写真法は回折環の連続性、一様性のチェックに適している。 しかし、セラミックスと金属の接合体の残留応力分布を測定する場合などは、ミクロンオーダの領域の応力が必要となる。最近写真フイルムの代わりにイメージングプレートを使い、電算機の援用による画像処理技術を用いるデータ処理により、デバイシェラー環全体から応力を測定することもできるようになった。 3)計数管法(ディフラクトメータ法) 計数管法によるときは、まず第一に回折環が一様な濃度で連続な環となっていることが必要である。 計数管法では、ゴニオメータとG-M計数管で回折角、回折線の強さ分布を直接求められ、迅速に測定でき、比較物質を使用しない特徴がある。ただ計数管の感度に制限があり照射面積として、最低1から2ミリ平方が限界であり、それ以下のミクロな部分(100ミクロンまで)の測定には、結晶粒度が細かい場合は写真法で可能である。なお結晶粒の粗い場合は、試料を揺動させる方法をとる。 計数管法でのX線ビームとしては、平行X線が普及しており、使用目的に応じ、種々の改良が行われている。 比較的測定し易い反射線の得られやすい場合は、一般に平方ミリ当たり1から2キログラム程度の誤差範囲内で応力測定ができる。 X線の侵入深さの関係から表面層(0.02から0.1ミリ)の応力測定という限定があり、特に被測定物の表面処理が重要である。 4.おわりに 残留応力測定には、本X線応力測定法が最適であるが、軟鉄やニッケルなど強磁性体には磁気ひずみ測定法がある。応力分布を知るのには、モアレ法、ひずみ塗料による方法、光弾性皮膜法等がある。現在主として用いられているのは、電気抵抗ひずみ計である。 <図/表> 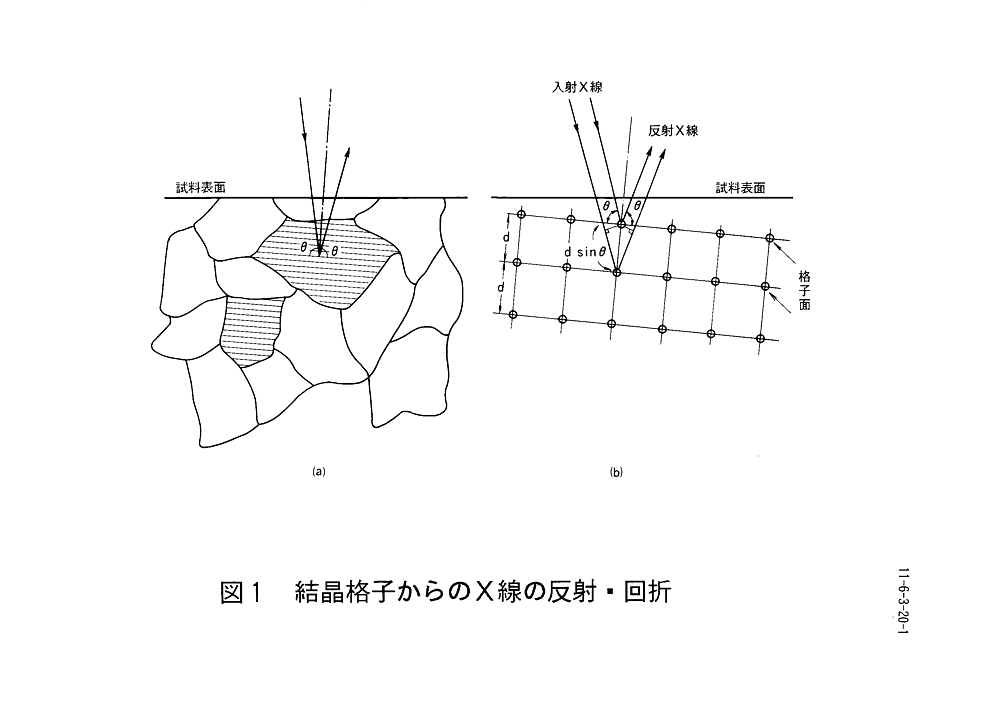
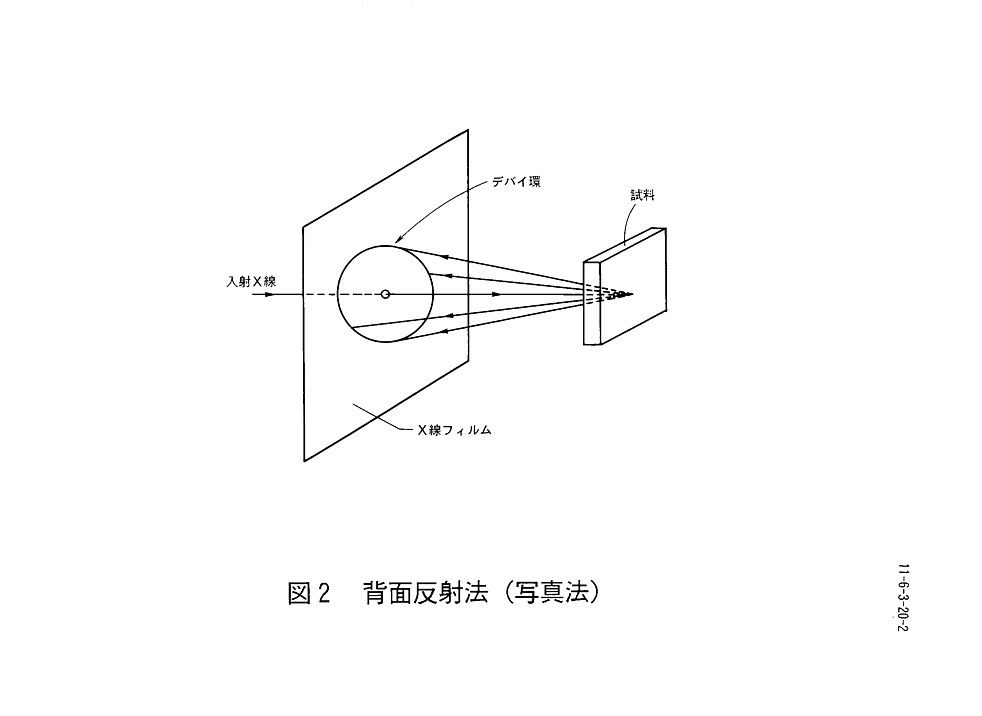
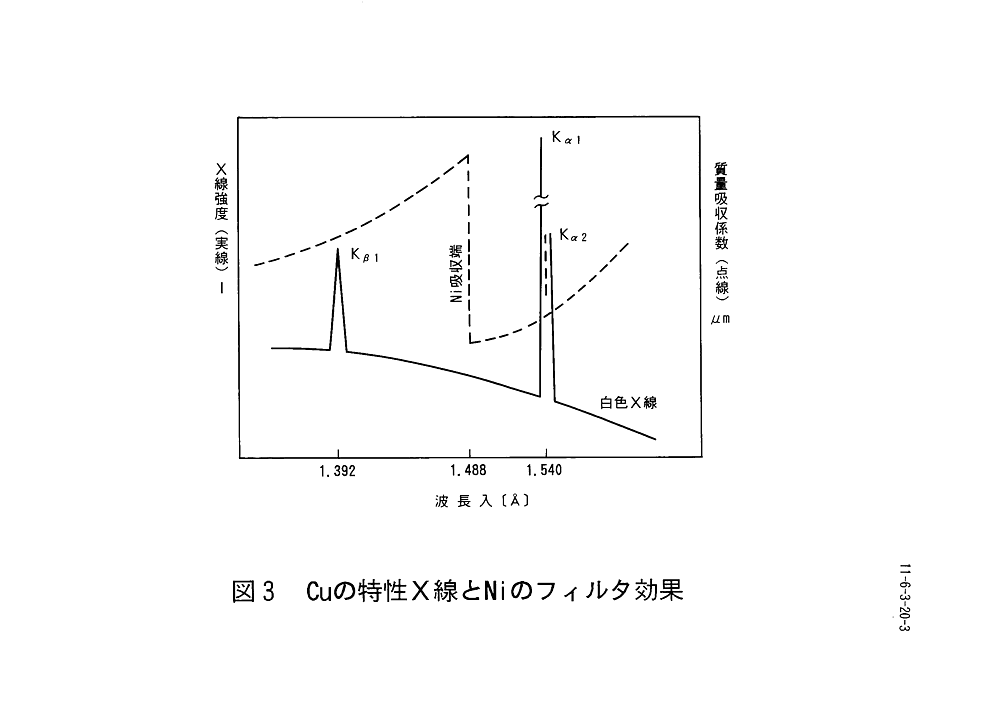
<関連タイトル> 蛍光X線分析の原理と応用 (08-04-01-26) X線反射率法と”埋もれた”界面の科学 (08-04-01-33) <参考文献> (1) 日本材料学会(編):X線応力測定法、養賢堂(1981年) (2) 日本非破壊検査協会(編):非破壊検査便覧(1978年) (3) 石搏顕吉ほか:放射線応用技術ハンドブック、朝倉書店(1990年) (4) 菅野 昭ほか:応力ひずみ回析、朝倉書店(1992年) (5) 吉岡靖夫ほか:イメージングプレートによる微小領域のX線応力測定、非破壊検査、Vol.42、No.12(1993年)
|

