|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
放射光X線が研究のツールとして一般的に利用されるようになって25年近くが過ぎた。当初は基礎研究のための「夢の光」としての利用が大半を占めていたが、SPring-8のような第三世代大型放射光源が出現し、X線の輝度やエネルギーがより高くなったため材料研究においても実環境下での材料の様子をその場観察する技術や、基礎研究おいてもこれまで観測することのできなかった物理量が観測できるようになり、物質・材料研究が大きく発展してきている。ここでは、SPring-8のX線を利用して実際のデバイス開発に役立った例として、半導体LSI電子デバイス界面の原子層の様子、Li二次電池の特性と構造との相関、自動車排ガス浄化触媒特性と構造との相関、および基礎研究として高温超伝導発現機構解明を目指した格子振動の研究を紹介する。 <更新年月> 2006年08月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.はじめに 我々の生活は物質・材料に支えられている。現在の文明社会では、車、電子デバイスなどハイテクノロジーが生活の中に溢れており、これらはすべて物質・材料の研究開発、技術開発の成果である。すなわち、物質・材料を抜きにしては我々の生活は成り立たないのである。今後もよりよい生活、便利で快適で安全な生活を実現するためには、物質科学・材料科学の進歩に負うところが大きい。 材料には、絶縁体、伝導体、超伝導体、磁性体、誘電体、など様々な性質(物性、機能)を持ったものがあり、我々の生活の中で利用されている。これらの物性や機能は原子構造によって決まるので、物質・材料研究にとってそれらの原子構造情報は、最も重要な事項の一つである。物質が持つ物性・機能と構造との関係の解明は、物性・機能の制御、新機能物質創製へとつながっていく。原子の並びである構造情報は、X線、中性子線、電子線などで得られ、物質との相互作用の種類がそれぞれ異なるので、得られる情報は厳密には異なっている。このため、得たい情報によってプローブを選ぶ必要がある。ここでは放射光X線が材料研究にどのように生かされているかを具体的な例を挙げることによって、放射光の利点を示す。 多くの研究機関には、X線発生装置があり、それを使って構造解析の研究が進められている。この発生装置から取り出されるX線強度と比較して広いエネルギー範囲にわたって6〜7桁、あるいはそれ以上のX線強度が得られるのが放射光源である。一般にある物理量が3桁変化すれば革命が起こったといわれるが、この定義からすれば科学の分野に2〜3回の革命が一度に訪れたようなもので、放射光の魅力、威力を想像することができよう。特に日本では世界最大の第三世代放射光源であるSPring-8(Super Photon Ring with 8GeV)が稼動しており、多くの研究者、技術者が放射光の利点を享受している。放射光の利点は、(1)高強度、だけでなく、(2)連続したエネルギー、(3)100%偏光していることが上げられ、これらを利用してこれまで不可能であった実験が可能となっている。このため、物理学、工学、医学、生命科学、農学、薬学、地球科学、これらの分野の応用といえる産業利用と、非常に幅広い分野に利用され本格的な利用フェーズを迎えている。 SPring-8では現在、国が設置し誰でも同等に利用できる共用ビームライン(25本)、利用者が自ら設置し優先的に使用する専用ビームライン(14本)、それとSPring-8建設者である理研ビームライン(7本)(2005年9月までは原子力機構ビームラインもこのカテゴリーであったが、10月以降は専用ビームラインとなった。)、加速器診断ビームラインの4種類のビームラインが稼動している。14本の専用ビームラインの内、4本が産業利用であり、これ以外に共用ビームラインでは平均約15%が産業利用に供されている。 2.放射光X線 放射光の発生原理を簡単に述べる。電子が光の速さに近い速度で円弧軌道(電子蓄積リング)を走ると、その接線方向に非常に指向性のよい光を放射する。これが放射光で、得られるエネルギーは電子のエネルギー、電子軌道を曲げる電磁石の磁場の強さに依存するが、赤外からX線、γ線に及ぶ連続スペクトル光である。最新の放射光源は第三世代と呼ばれ、電子軌道の断面積が小さく(高輝度)、さらに電子軌道の直線部分に永久磁石を規則正しく並べ、この磁場の中を電子ビームを通過させることにより、より高輝度の放射光やエネルギーの高い放射光を発生できる挿入光源(アンジュレータやウイグラーと呼ばれる)が設置されている(参考文献1)。兵庫県西播磨に建設されたSPring-8は、まさに世界最大の第三世代放射光源を持つ施設である。図1(a)に放射光リングの概念、図1(b)、(c)にそれぞれ偏向電磁石、アンジュレータからの放射光発生の概念を示す。放射光の特長は、上に述べた3つのほかにパルス性を持っていることが上げられ、今後この特長を利用した研究が盛んになることが期待される。 3.SPring-8の産業利用 放射光の産業利用は、ほとんどが評価分析・解析で、いわゆる“観る”ためのツールとして放射光が利用されている。このため製品化や事業化へ直接繋がる成果が見えにくい。また、SPring-8では世界でも最高性能を有する放射光X線を利用できるため、これまでは産業利用といっても比較的基礎研究フェーズのものが多かった。しかし、製品開発に直接繋がった成果もある。その例として、ここでは、半導体電子デバイスに関する研究成果、電池電極に関する研究成果および自動車排ガス浄化触媒に関する研究成果を紹介する。 3.1 半導体電子デバイス LSIのゲート絶縁膜は、まもなく1.0nm以下の厚さが要求され、SiO2では限界を迎えている。1.0nmという膜厚はSi原子にして僅か5層程度の厚さであり、アモルファス層を原子レベルで制御しなければならないところまできている。このため新しい材料として酸窒化膜や高誘電体薄膜材料の開発が企業を中心に大学でも盛んに行われている。このような開発競争の中で放射光は、ナノ薄膜の界面構造、積層構造、電子状態、酸化物組成の定量などの評価に威力を発揮している。一例としてX線反射率測定によって1.0nmのSiO2薄膜が一様ではなく膜垂直方向に密度分布を持つことが明らかになった研究を紹介する。測定方法は放射光X線反射率測定法で、薄膜の厚み方向に密度分布があれば、薄膜の表面および界面から反射したX線が干渉することによって反射X線強度に振動や構造が現れ、これを解析することによって膜厚、密度、表面や界面の凹凸を評価できる。図2に富士通研究所の淡路らによって観測された実験データとその解析結果を示す(参考文献2)。これは、Si基板上に熱酸化によって形成された1.0nm膜厚のSiO2を試料としたX線反射率測定である。この解析結果は、均一と考えられていた1.0nmのSiO2は3つの異なった密度にピークを持つ“不均一“な構造を持っていることを示しており、プロセス開発の余地がまだ残されていることが明らかとなった。 3.2 電池電極 電池は今後のエネルギー問題に関わる重要なキーデバイスとして位置づけられ、企業や国研、大学等で研究開発が活発に行われている。例えば、Li二次イオン電池は、充放電が繰り返し可能な電池として既に多くの機器に利用されている。しかし、問題は、充放電が無限にできるわけではなくそれらを繰り返すと充放電能力の低下が観測されている。この原因を明らかにするために、豊田中央研究所のグループは放射光X線を利用した詳細な局所構造解析から劣化原因を究明し、サイクル寿命向上を実現させた(参考文献3)。この方法は、入射X線エネルギーを注目する元素の内殻電子の吸収エネルギーに選び(今の場合はNiのK−吸収端エネルギー)試料の吸収係数を入射X線エネルギーの関数として計測するもので、X-ray Absorption Fine Structure(XAFS)と呼ばれ、吸収元素の周りの局所構造が解析される方法として多くの分野で利用されている(参考文献3)。図3(a)は、充放電をパラメータとした正極材料であるCoNiOのXAFS測定の解析から得られたNi原子を原点とした動径構造関数を表している。図から読み取れるのは、NiO6からなる8面体構造が、劣化前は歪んだ構造を呈しており(Ni-O,Ni-Niの相関を表すピークが、515回充放電を繰り返したものに比べてブロードである)、これがLiの出入りを助けていたが、劣化後はこの構造が正8面体に凍結しLiの出入りを阻害するようになることが明らかとなった。この結果が長寿命化につなげる指針に繋がったようである。(図3(b)に概念図を示す。) 3.3 自動車排ガス浄化触媒 現代社会においては、車なしでは生活できないであろう。しかし、一方で地球温暖化問題、これを含む環境問題が世界的な問題となっており、車がこれら問題の根源の一つとしてその利用形態が問われている。研究者、技術者は、この問題解決のために燃料電池の開発や排ガス触媒の開発に多くの時間、研究費を投入し人類の社会福祉向上に役立ちたいと日夜努力している。ここでは放射光X線による構造研究が、実際のガソリンエンジン車排ガス触媒の開発に役立った例を紹介する。 自動車を動かすとマフラーから排ガスが放出される。自動車排ガス触媒に求められる機能は、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)の酸化、窒素酸化物(NOX)の還元作用能力であり、これらを同時に浄化することが要求されている。Pd金属の触媒機能が高いことは良く知られており、従来はPdの表面積を増やすためにPd微粒子を例えばAl2O3に担持させている。しかし、触媒がさらされる環境は、800℃という高温、かつ酸化と還元雰囲気が振動している状況である。このような環境では、Pdは徐々に酸化や結晶粒成長により、触媒機能が低下してしまう。ここで紹介するのは、触媒機能が低下しない半永久的に使える触媒である(インテリジェント触媒と呼ぶ)。時間とともに変化する触媒機能の概念を図4に示す。この触媒は、ペロブスカイト酸化物のLaFe0.54Co0.36O3とPd0.1を複合化したものである。なぜこれがインテリジェンス性をもつのか結晶構造を詳細に調べることで明らかとなった(参考文献4、5)。 構造解析は、放射光X線のエネルギーを自由に選べるために、異常分散を利用した回折法とXAFS法を利用した。参考文献4によると、触媒として働くPd原子が、酸化、還元の環境変動に応じて動くことが明らかとなった。すなわち、酸化環境では、Pdはペロブスカイト構造(ABO3と表現される)のB-siteを占めているが、還元環境ではペロブスカイト構造の外に出、環境変動に応じてほぼ100%可逆的に出入りしている。(概念を図5に示す。)このためPdの結晶粒成長が抑えられ、いつまでもPdが微粒子のまま存在することができるため半永久的に触媒機能が持続することがわかった。今回の研究結果によって、科学的に機能持続機構が証明され、2002年の秋以降、実際の車に搭載されることになった。 4.超伝導体 超伝導現象は1911年にカマリン・オンネスによって発見された電気抵抗がゼロで電流を運ぶことのできる状態である。これが不思議であるのは、マイナスの電荷を持った電子同士がお互いに引き付けあってペアーを作り共に行動するからである。超伝導現象が発見されて40年以上経ってから電子同士がペアーを作るのは、格子振動が媒介となっているというBCS理論(理論を創ったBardeen、Cooper、Schriefferの3人の頭文字をとって名づけられた)が発表され、今ではこの理論が確立されている。しかし、超伝導状態を実現するためには、金属を低温に冷やさなければならず、BCS理論でも約40Kより高くなることはないと予言されていた。ところが、1986年に超伝導転移が38Kという銅の酸化物が発見され、数年で液体窒素温度である77Kをはるかに超える超伝導体が発見されている。しかし、酸化物高温超伝導体が発見されてすでに17年以上経ち、非常に多くの研究がなされているが、未だに超伝導機構に関しては統一された理論はない。 SPring-8では、これまで不可能であったX線非弾性散乱が可能となり、これを利用して超伝導体の格子振動が測定できるようになった。超伝導体の機構を解明するには、超伝導特性と一対一に対応する物理量を発見することが重要である。それがX線非弾性散乱で発見された。これは、X線ビームサイズが100μ程度で実験が可能であるために超伝導転移温度の異なる単結晶試料を多数用意でき、一番高い格子振動エネルギー(約80meV付近)の縦光学振動のCu-O bond stretching modeのSr濃度依存性を系統的に測定するのに成功した(参考文献5)。結果は図6に見るように、このモードの「異常ソフト化」のSr濃度依存性と超伝導転移温度TcのSr濃度依存性との様子が定性的に一致していることが発見され、超伝導発現に格子振動が関与しているらしいことが結論された。この結果を基に、より高い転移温度を持つ超伝導体が設計されれることが期待される。 5.おわりに 大型施設の産業への利用拡大を目指して国が様々な試みを始めており、放射光の産業利用への展開が拡大してきている。今後、上で述べた自動車触媒研究のように放射光で得られた結果が直接製品開発に関係する例が多く輩出されよう。 <図/表> 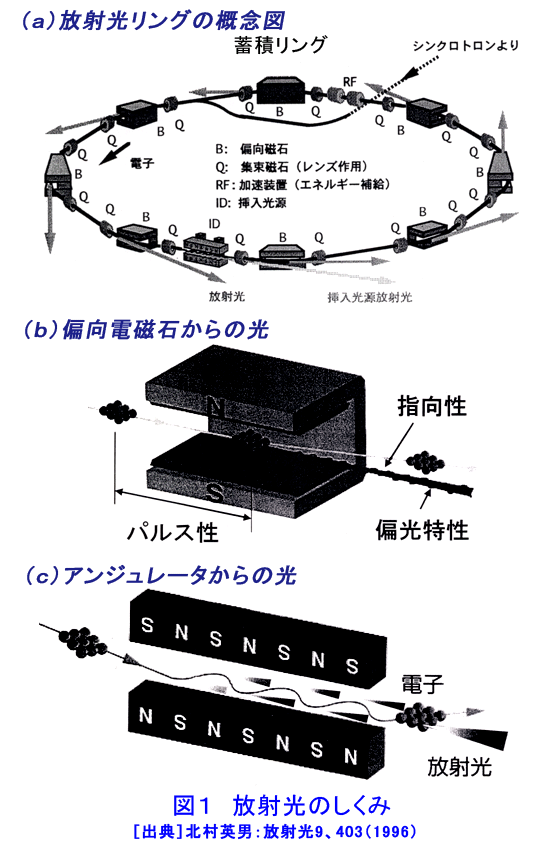
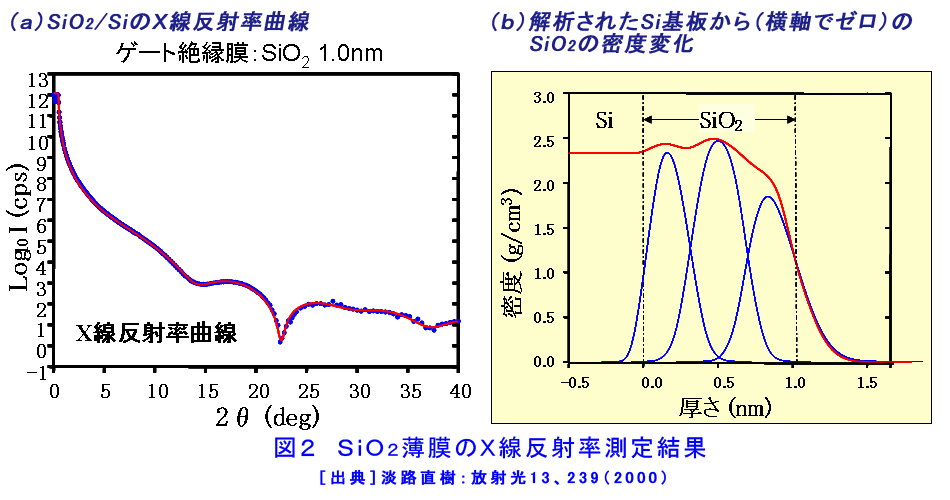
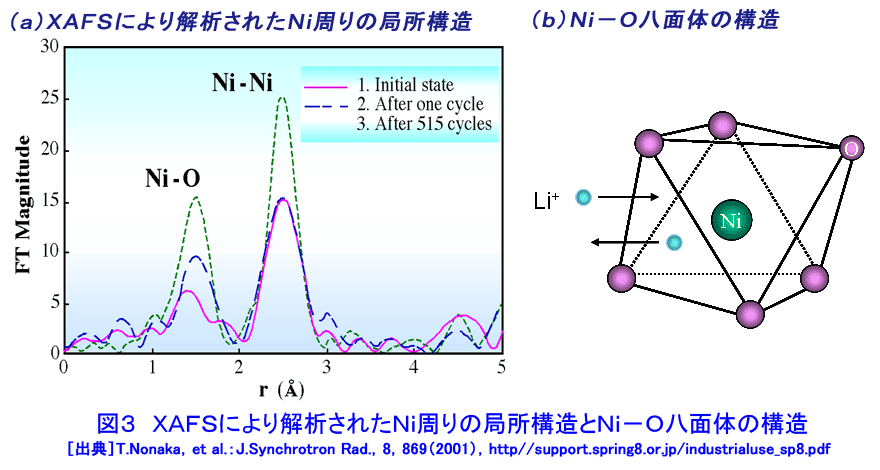
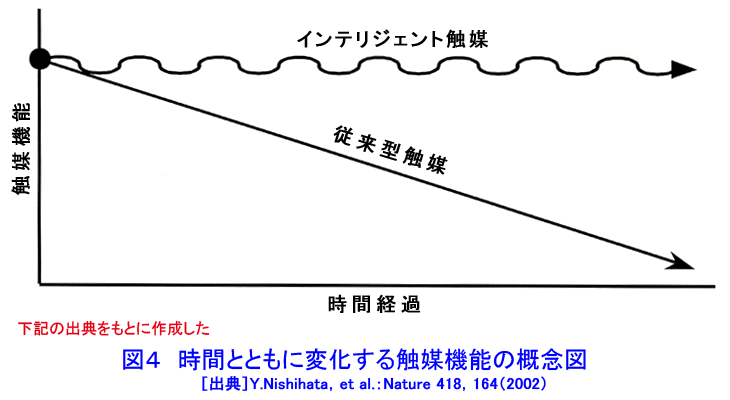
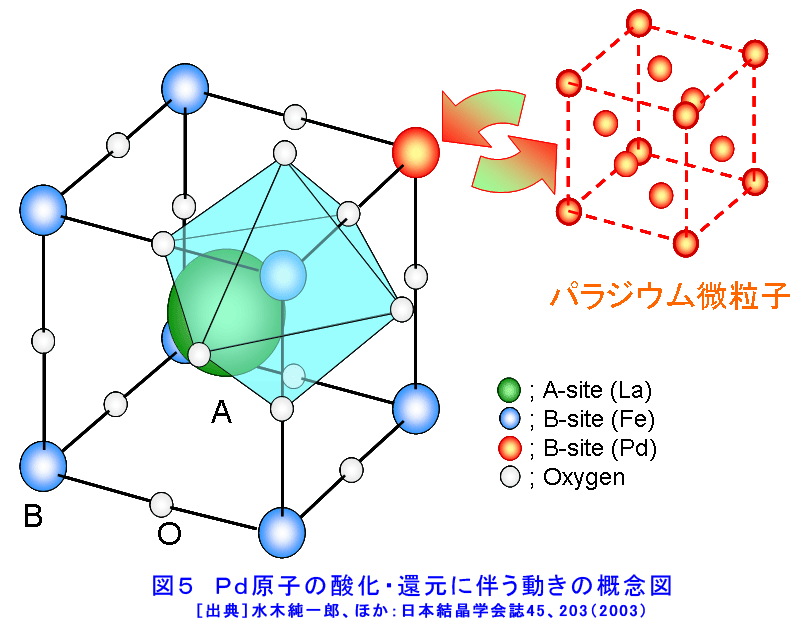
![図6 [100]Cu-O bond stretching modeのソフト化のSr濃度依存性](../pict/08/08040142/06.gif)
<関連タイトル> SPring-8計画 (08-04-01-06) SPring-8(放射光)施設による放射線利用 (08-04-01-07) <参考文献> (1)北村英男:放射光9、403(1996) (2)淡路直樹:放射光13、239(2000) (3)T.Nonaka,et al.:J.Synchrotron Rad.,8,869(2001), (4)Y.Nishihata,et al.:Nature 418,164(2002) (5)水木純一郎、他:日本結晶学会誌45、203(2003) (6)T.Fukuda,et al.:Phys. Rev. B71,060501(2005) (7)K.Ikeuchi,et al.,Jpn.J. Appl. Phys. 45,1594(2006)
|

