|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
太陽電池は、太陽光を直接電気エネルギーに変換する半導体であり、太陽光を受けている間だけ電気を発生する一種の発電装置である。太陽電池には、結晶系シリコン太陽電池、アモルファス・シリコン太陽電池および化合物半導体太陽電池がある。このうち、結晶系シリコン太陽電池およびアモルファス・シリコン太陽電池の一部は既に実用化されている。光エネルギーを直接電気エネルギーに変換する変換効率の理論的限界値は、シリコン単結晶の太陽電池で約30〜35%、アモルファス太陽電池で25%、化合物半導体の場合で20〜40%である。しかし、実際には24%程度の変換効率しか得られていない。太陽電池および発電システムの研究開発により、太陽電池製造コストの低減化、発電単価の低減化、効率の向上等多くの成果を得ている。また、宇宙で発電し、地球へ送電する宇宙太陽発電の構想もある。 <更新年月> 2004年02月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.太陽電池(PV:Photo Voltaic)とは 太陽電池は、太陽光を直接電気エネルギーに変換する半導体であり、乾電池と同じ働きをする電池ではなく、太陽光を受けている間だけ電気を発生する一種の発電装置である。太陽電池の歴史は19世紀半ばまで遡るが、実用化が始ったのは1954年ベル研究所でシリコン太陽電池が開発されてからである。現在では、約15%程度の変換効率をもつものが開発され実用に供されるようになった。 図1にシリコン太陽電池の発電の原理、図2にシリコン系太陽電池の写真を示す。太陽電池は、図1に示すような機構により電気を発生するもので、電気伝導を支配する多数担体(キャリア)が電子であるn型半導体と多数担体が正孔であるp型半導体を接合(p-n接合)して作られる。太陽光を照射すると、光量子が原子に衝突し電子と正孔との対が発生する。この電子と正孔とが内部電界および拡散により相互に逆方向に流れ、電流が発生する。このときp領域とn領域を結び外部回路を設けることによってp領域からn領域に向かって流れる電流を取り出せる。このような現象を「光起電力効果」という。電圧は通常0.5Vと小さいため、この太陽電池を直列に接続しモジュールを、また更にモジュールを直並列に接続し、アレイを構成する。 このように光エネルギーを直接電気エネルギーに変換する太陽電池の性能の良否はそれらのエネルギー比、すなわち太陽電池の出力電気エネルギーの入射する太陽エネルギーに対する比によって示され、この比は太陽電池の性能の指標を与えるものであり、通常「エネルギー変換効率」、単に「変換効率」と呼ばれている。変換効率の理論的限界は太陽電池を構成する物質によって定まり、太陽光エネルギーのスペクトルと太陽電池の感度スペクトルとの整合に支配される。例えばシリコン単結晶の太陽電池で約30〜35%、アモルファス・シリコン太陽電池で25%、化合物半導体の場合で20〜40%である。しかし、実際の太陽電池の効率は現状では実験室レベルで24%程度である。原因は表面反射光損失、生成キャリアのうち表面または電極界面での再接合により失われる損失、キャリアが光電池内部の再接合により失われる損失、太陽電池の内部低抗による損失、太陽電池の開放起電力が光子のエネルギー以下のための損失の5成分に分類できる。 太陽電池の種類は大きく分けて結晶系シリコン太陽電池、アモルファスシリコン太陽電池および化合物半導体太陽電池の3種類がある。シリコン太陽電池については一部すでに実用化がなされているが、結晶系は効率が高く、さらに高くできる可能性を有しているものの製造コストの低減には限界があり、逆にアモルファスは効率が結晶系に比べて低くかつ使用時の水素による光劣化があるものの、低温作業が可能なため製造コストについては大幅に安くできる可能性を有している。 化合物半導体系は、元素の組み合わせに自由度を有する。III−V族系(GaAs、InPなど)は35%を超える超高効率を達成できる可能性があり、また、II−IV族系(CdTe、CISなど)では比較的高い効率と低コストを両立できる可能性がある。 これら各々の特徴を活かした太陽電池の実用化のため、太陽電池の技術開発では、低コスト化を主眼に、一層の高効率・高品質化を図ることとしている。薄型多結晶太陽電池では、入手しやすい高純度金属シリコンを出発原料とした太陽電池用シリコンの製造開発に取り組むとともに、実用化を踏まえた基板およびセル・モジュールの低コスト化のための技術開発を進めている。 また、薄膜太陽電池のアモルファス太陽電池は、大量・連続生産が可能であり、シリコンの使用量も少ないことから低コスト化が期待されており、一層の高品質化、高信頼性化、大面積化を図り低コスト化を目指している。 CdTe太陽電池についても、これまでの研究成果を活かし変換効率を維持しつつ、低コスト化、薄膜多結晶太陽電池およびCIS太陽電池(CuInSe2)については、高品質化、高効率化等の要素技術開発を進めている。さらに電力用をめざした超高効率太陽電池についても要素技術等の研究開発を進めている。表1に各種太陽電池セルの変換効率を、図3にわが国の生産量の推移を示す。 2.太陽光発電システム技術開発 太陽の日射は一定していないため、太陽電池を用いた発電装置には通常蓄電池が設けられている。太陽電池発電システムの構成例を図4に示す。 太陽電池は、コストが高い、大容量化が難しい、変換効率が低い等のため、商用電力の供給が困難な無人灯台、山小屋の電源、山間僻地の気象データのテレメータリング装置の電源、テレビ・ラジオ等の無人中継局の電源、科学衛星・通信衛星等の人工衛星用電源等に小規模に利用されているに過ぎない。しかし、クリーンな発電システムであることから、大容量化・低コスト化・高効率化を目指した研究開発が盛んに行われている。わが国でも、通産省(現在、経済産業省)工業技術院のサンシャイン計画以来、研究が進められている。 (1)システム評価技術 太陽電池の導入普及の拡大のため、太陽電池を各種気候下に曝露することで、太陽電池の長期にわたる挙動・性能に関するデータを収集し、短期問の試験で長期信頼性を確認する「加速劣化試験手法」の開発と、多様化する太陽電池の性能を統一的に評価するため、長波長まで近似度の高いソーラーシミュレータの開発を行っている。また、太陽光発電システムの最適設計を行うため、静岡県浜松市に系統連系型や独立型の各種実証システム(出力合計100kW程度)を建設し、エネルギーフローからインバーター損失や最大電力点からのずれ、システム構成機器の劣化等の各損失を解析することで、設計を行う際に評価する必要のある各種パラメータ・補正係数を明らかにする研究を行っている。また、全国各地域で既に導入されている住宅用太陽光発電システムから、システム運転データの収集・解析・評価を行っている。 (2)利用システム・周辺技術の研究開発 電力変換装置の評価、長寿命・低コストの蓄電池等の開発等、周辺装置の研究開発を進めている。また、建材と太陽電池とを一体化することで、太陽電池モジュールコストと設置工事費の低減を可能とする建材一体型太陽電池モジュールの開発を進めている。建材一体型太陽電池モジュールの開発では、個人住宅等に対応する太陽電池モジュールと屋根建材を一体化した住宅用屋根一体型太陽電池モジュールを2方式、また膜構造建築物等広範囲な用途に対応するビル等建築物一体型太陽電池モジュール3方式の研究開発を行っている。 (3)実証研究 離島用電源として、太陽光発電システムと風力発電システムおよび既存電源を連係したマルチハイブリッドシステムの適用可能性の研究や、配電系統へ高密度に太陽光発電システムが系統連係した場合の問題の把握・対策技術の実証研究を、1997年度から行っている。 海外においても広範な研究開発がすすめられるとともに、 実用化をめざした普及導入プログラムも開始されている。特に、米国、欧州において積極的に推進されており、1997年度の開発予算では米国が6,000万ドル、ドイツが8,850万マルクとなっている。 3.わが国の導入実績 日本における太陽光発電電力システムの設置容量は2001年で、122,010kW、世界の設置容量の47.5%を占めている。また、累積の設置容量も452,230kWで世界の46%となっている。2001年の太陽電池モジュールの生産量は170MWで、アメリカの104MW、ヨーロッパの62MWを大きく引き離している。 これまでサンシャイン計画およびムーンライト計画において開発が進められてきた各種新エネルギー技術、省エネルギー技術のうち、特に太陽電池および燃料電池については近年の技術開発の飛躍的な進展により、技術開発によるコストダウンと需要の増大とが相互に促進し合う「良循環」の見通しが得られる段階に至りつつある。しかし、これら技術開発成果の本格的導入を図る上で製造設備の能力面および需要面の拡大には、一定のリードタイムが必要である。したがって「地球温暖化防止行動計画」の目標を裏打ちする「石油代替エネルギーの供給目標」の達成を確実なものとするためには、太陽電池および燃料電池の技術について研究開発の加速的推進を図り、早急に供給ポテンシャルの増大に努めることが極めて重要である。 太陽電池製造コストの推移について図5に示す。太陽電池の製造コストは1974年の約2万円/Wから1997年時点では約440円/Wまで下がった。実際の生産規模の約3倍にあたる100MW/年の工場規模を仮定すると、現状では約190円/Wであり、2000年初頭には150円/W前後まで下がると予想され、発電コストは現在の56円/kWhから20円/kWh程度まで大幅に低下する。これにより、需要が離島・遠隔地から公共・農漁業分野、民生・業務自家発電、電気事業へと拡大していくため、生産規模拡大により一層のコストダウンが期待され、「良循環」が期待される。 4. 宇宙太陽発電(SPS:Solar Power Satellite) 宇宙太陽発電衛星の概念は、1968年に米国のPeter E. Glaser博士が考案したシステムで、基本的な考え方は、地球周回軌道に太陽電池を貼り付けた大きな構造物を打ち上げて、大電力を発電し、地球に送電しようというものである。1970年代には米国エネルギー省とNASAにより大がかりな研究が行われ、1979年にSPS Reference Systemが提案されたが、経済的に成立しないことから研究は中止された。図6に概要を示す。宇宙太陽発電所(Solar Power Satellite/Station:SPS)は、宇宙空間で超大型の太陽電池パネルを広げ、太陽光発電によって得られる直流電力をマイクロ波に変換して、地球や宇宙都市や宇宙工場の受電所に設置されるレクテナと呼ばれる受電アンテナへ伝送し、再び直流電力に戻す方式の発電所である。SPSは上空3万kmの静止衛星軌道にあり、常に地上から見えている。受電側ではマイクロ波をレクテナと呼ばれる整流アンテナでマイクロ波エネルギービームを受電し、再び直流の電気エネルギーに再変換して利用する。マイクロ波は産業、科学、医療用で使われているISMバンドである2.45GHzや5.8GHzの周波数を用いることが検討されている。昨今のエネルギー問題、発電の安全性の問題、CO2排出の問題等を解決する手段として注目されつつあり、世界的に検討が急速に進んでいる。メリットは以下のようなものである。 (1)発電時に化石燃料などの燃焼反応を利用しないため、クリーンなシステムである。 (2)太陽エネルギーを利用しているので、無限のエネルギー源を有している。 (3)地上太陽発電と異なり、雨や雲といった天候の影響がない。 実現に至るまでの課題としては、 (1)低電力密度送電による受電設備の巨大化や設置上の制約 (2)マイクロウェーブによる人体や環境に対する影響の評価と国民的合意 (3)経済的妥当性の定量的評価 宇宙太陽発電は、大きなメリットを有しており、今後の発電需要の上昇と地球環境への低インパクト性から考えても有力な代替電力源であると期待されている。1993年には新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が、1GWクラスの太陽発電衛星のグランドデザインを発表した。また、宇宙航空研究開発機構では、マイクロ波による宇宙太陽発電システムの概念検討を進めている(図7)。 <図/表> 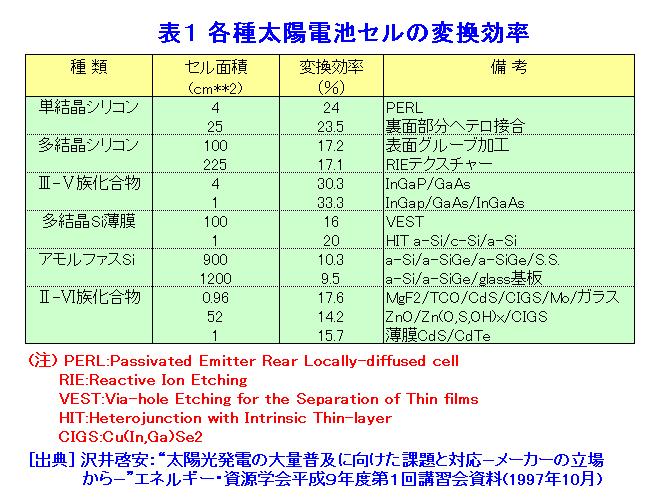
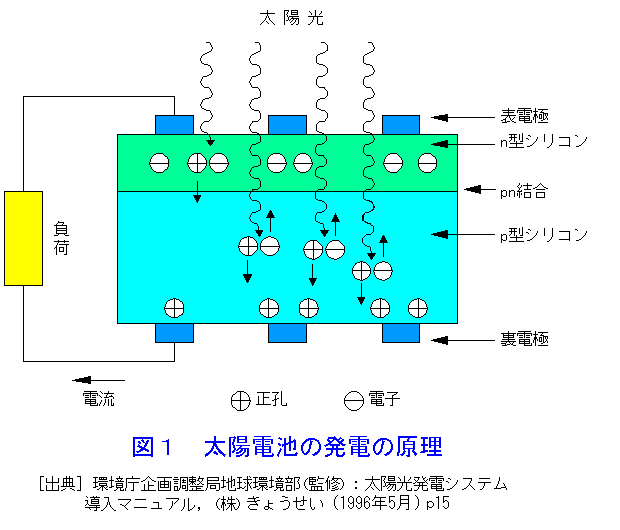
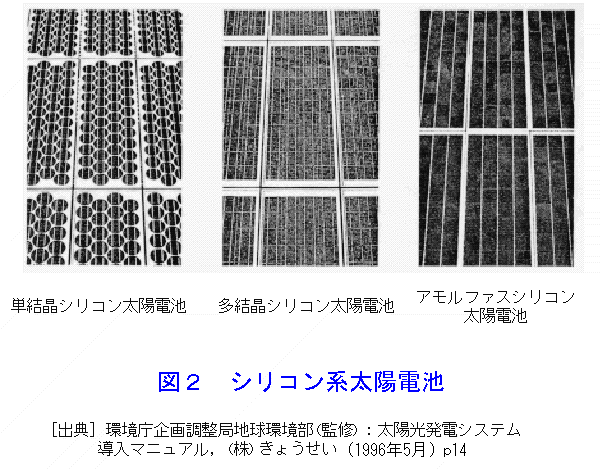
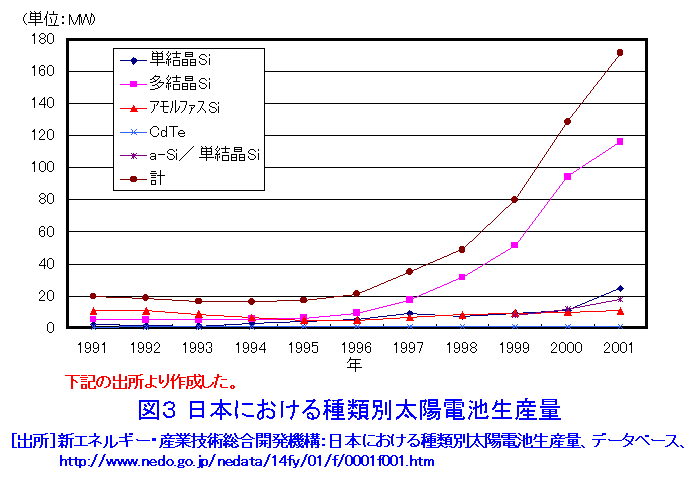
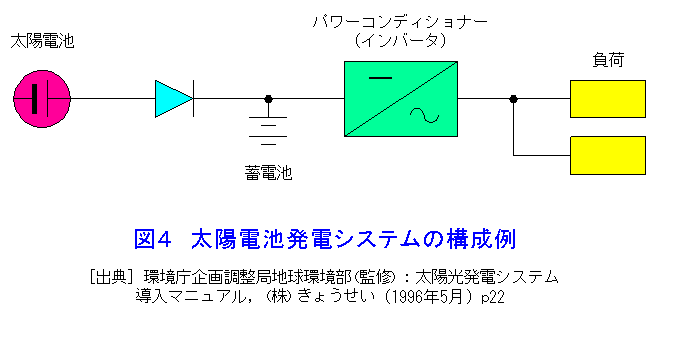
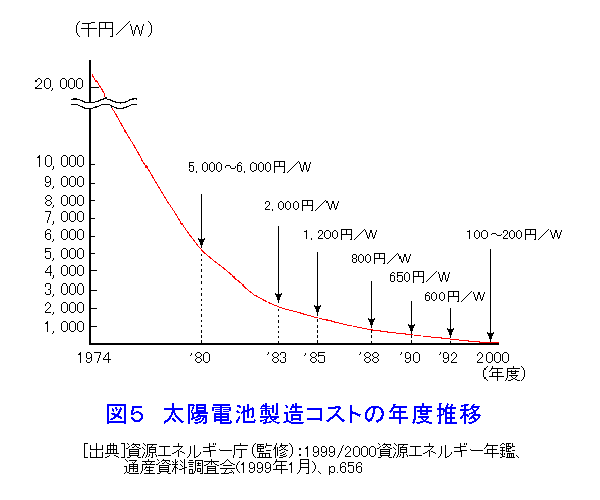
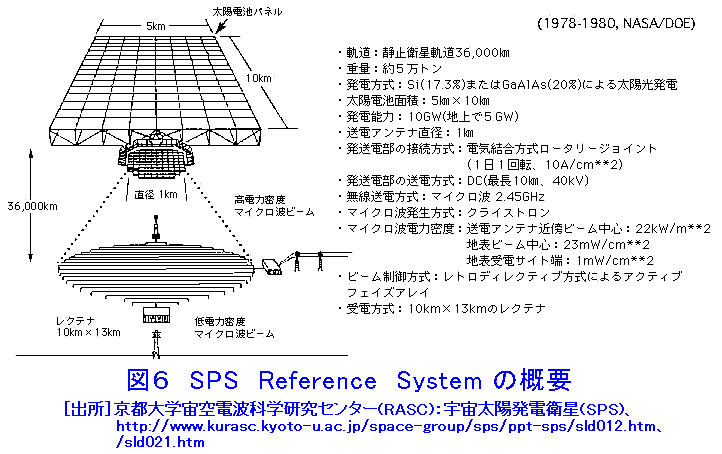
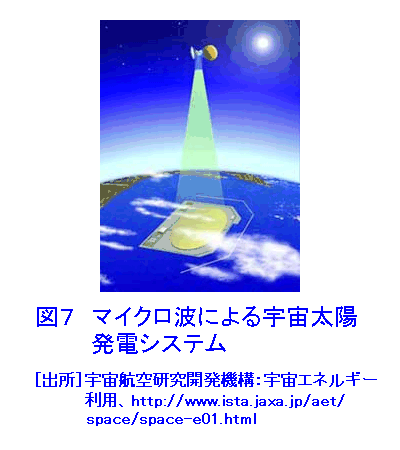
<関連タイトル> ソーラーシステムのしくみ (01-05-01-04) 新エネルギー開発における国際協力 (01-09-07-03) 太陽熱発電システム (01-05-01-02) 太陽光発電システム (01-05-01-01) <参考文献> (1)日本太陽エネルギー学会(編):太陽エネルギー読本、オーム社(1981) (2)資源エネルギー庁(監修):1999/2000資源エネルギー年鑑、通産資料調査会(1999年1月)、p.644-646、p.654-659 (3)資源エネルギー年鑑編集委員会(編):2003/2004資源エネルギー年鑑、通産資料出版会(2003年1月)、pp.182-186 (4)資源エネルギー庁(編):新エネルギー便覧 平成10年度版、(財)通商産業調査会(1999年3月)、p.21-26 (5)環境庁企画調整局地球環境部(監修):太陽光発電システム 導入マニュアル、(株)きょうせい(1996年5月)、p.12 (6)鳥山 芳夫:発電技術の将来展望、宇宙太陽発電、火力原子力発電(2001年10月)、p.156 (7)新エネルギー・産業技術総合開発機構:データベース>新エネデータ>fy14>過去一年間の当該技術の動向 (8)宇宙航空研究開発機構:総合技術研究本部>宇宙利用の研究>宇宙エネルギー利用
|

