|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
経済産業省は2002年3月19日、第28回総合エネルギー対策推進閣僚会議に、わが国のエネルギー需給の現状を報告するとともに、2010年度の石油代替エネルギーの供給目標(案)を提出し、了承された。現在それに従ったエネルギー対策が実施されている。わが国の1990年代のエネルギー需要は、1998年度に対前年度比でマイナスとなった以外は、増加基調で推移してきた。2004年度の最終エネルギー消費は、約16000PJ(ペタジュール、10の15乗ジュール)で対前年度比0.9%増であった。部門別に見ると、産業部門と民生部門が増加し(各々、1.0%増、1.3%増)、運輸部門は横ばいであった。2004年度の一次エネルギー国内供給は約23000PJで、対前年度比2.6%増であった。運転再開された原子力発電所があったため、原子力は前年度比18.1%の増加、石炭も9.4%増加した。石油と天然ガスが各々、2.2%、0.3%減少した。 <更新年月> 2006年08月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.経済成長とエネルギー消費 1.1 エネルギー需要の動向 わが国のエネルギー需要(最終エネルギー消費)は、高度成長期といわれた1960年から1970年にかけて、経済成長率(実質国内総支出)が年率10.2%と未曾有の伸びを記録してきたことを背景に、年率12.5%と極めて高い伸びで推移した。しかし、2度の石油危機を契機としてエネルギー利用の効率化が進み、産業構造が変化したこと等を背景に、1979年度以降1986年度までの7年間では、最終エネルギー消費全体で年平均−0.4%の伸び率で推移した。しかしながら、1987年度以降の内需主導型の経済成長、加えて低水準で推移するエネルギー価格等を背景に、エネルギー需要は増勢に転じ、1986年度から1990年度の4年間で年率4.4%の伸び率で推移した。景気が調整局面となった1992年度は2.0%、1993年度は0.5%と伸び率が鈍化したものの、1994〜1996年度は、景気が緩やかな回復基調で推移したことに加え、一部産業における輸出の急増(為替相場の円高傾向による)や記録的な猛暑による電力需要の急増等もあり、増加傾向で推移した。特に、1995年頃までは、快適さや利便性を追求するライフスタイルの浸透による民生、運輸部門のエネルギー消費の伸びが顕著である。産業部門のエネルギー消費の年平均伸び率は、1990〜1995年度に既に0.56%まで低下しているが、1995〜2000年度、2000〜2004年度では、各々、年平均伸び率は0%に留まった。民生、運輸部門の年平均伸び率は、それぞれ2.2%、0.5%(1995〜2000年度)、1.0%、0.0%(2000〜2004年度)であり、産業部門と同様、伸び率は低下している。(表1) 2001年度は、実質国内総生産が−0.8%とマイナスであったこと等により、最終エネルギー消費は約15800EJ(ペンタジュール、10の15乗ジュール)、対前年度比で−1.2%と減少に転じた。しかし、2002年度以降は産業部門と民生部門が若干増加する一方、運輸部門はほぼ横ばいとなっている(図1、図2)。 1.2 エネルギー供給の動向 わが国では、第一次石油危機以降、脆弱なエネルギー供給構造の改革に取り組んできた。その大きな柱として、1)石油依存度の低減、22)準国産エネルギーたる原子力の開発利用、の二つがあげられる。1)に関しては、1973年度の77.4%が1985年度には56.3%まで低下した。その後は原油価格の低水準での推移等を背景としてほぼ横ばいで推移したが、2000年度以降、約50%まで低下し、2004年度には48%台になった。2)の原子力の構成比については、1973年度の0.6%から1987年度には10.0%まで上昇した。その後、1998年度の13.7%をピークに、約10%から13%で推移している(図3)。 1.3 一次エネルギー総供給の対GDP原単位 エネルギー利用効率化の尺度の一つに「一次エネルギー総供給の対GDP原単位」という指標がある。1億円のGDPを創出するのに、原油換算でどれだけのエネルギーを消費したかを示し、産業の省エネルギーの度合いを測る指標として使われる。日本の一次エネルギー総供給のGDP原単位は、第1次石油危機時の1973年度には7035GJ/億円、1990年度以降は、4300GJ/億円から4700GJ/億円で推移し、対GDP原単位は改善した(図4)。(GJ:10の9乗ジュール) 1.4 エネルギー需要の対GDP弾性 1)わが国のエネルギー消費の対GDP弾性値 わが国の経済成長とエネルギー消費との関係を次に示す。表1は過去のデ一タを5つに区分けし、最終エネルギー消費の対GDP弾性値の推移を示したものである。弾性値とは、結果を表す要因の変化率(ここでは、エネルギー消費の年平均伸び率)をその原因となる要因の変化率(実質GDPの年平均伸び率)で割った値である。 2)対GDP弾性値変動の分析 第I期から第II期へ、対GDP弾性値が大幅に低下したのは、技術的な省エネルギーの進展、産業構造がエネルギー多消費型産業からエネルギー少消費型産業やサービスへとシフトしていったことが理由と考えられる。また、第III期で対GDP弾性値が1に近づいたのは、技術的な省エネルギーの一巡等によるエネルギー原単位の下げ止まり、安定化、産業構造の変化の度合いが第I期と比べて、鈍化してきたこと等があげられる。第IV期にかけて弾性値が上昇し、再び1を超えるようになったのは、(1)産業部門において、省エネルギーの一巡や景気低迷による稼働率の低下、多品種少量生産等により原単位が逆に悪化に転じたこと、(2)情報化の進展、家庭用機器の高機能化や旅客車両の大型化等によりエネルギー多消費型のライフスタイルヘの変化が見られたこと、等があげられる。 第IV期の後半および第V期には、省エネルギーや産業構造の変化から対GDP弾性値は再び減少に転じている。 2.産業部門のエネルギー消費 2.1 エネルギー消費の概況 他の先進諸国と比較した場合のわが国エネルギー需給構造の特徴の一つとして、最終エネルギー消費に占める産業部門の比率が高いことがあげられる。これにはわが国がエネルギー多消費型の重化学工業を中心に経済成長を達成してきたこと、また国土が狭く運輸部門が小さいこと、気侯に恵まれ民生部門が小さい等の理由が考えられる。この特徴により、産業部門における省エネルギーは、エネルギー・セキュリティの確保の上で重要であると指摘できる。 2.2 エネルギー消費の推移 このようにエネルギー消費において重要な位置付けを有する産業部門であるが、1973午の第1次石油危機以降はエネルギー利用の効率化進展、産業構造の変化(産業の中心が基礎素材産業から加工組立産業、電子・情報産業ヘシフト)により、1973年度から1986年度までの13年間の年平均伸び率は、−1.1%と減少傾向で推移した。1986年度以降は内需主導型の景気拡大による生産活動の活発化、また省エネルギーの改善傾向の頭打ち等によりエネルギー消費は顕著な伸びで推移し、1986年度から1991年度までの5年間では、年率3.5%と再び増勢に転じた。 1992年度以降は、景気が調整局面に入り、製造業の生産指数も落ち込み、エネルギー消費量も減少で推移した。しかし1994〜1996年度は、景気が緩やかな回復基調で推移したことから、対前年度比プラスと再び増加に転じた。1997年のアジア通貨危機を契機とした景気後退により1998年度のエネルギー消費は減少したが、1999年度には景気が回復し、2000年度には7534PJの消費となった。しかしながら、2001年度には再び景気が悪化し対前年度比−2.2%の7368PJの消費となった。しかし、2002年度、2003年度と消費は漸増し、2000年度の水準を超えている(図5)。 3.民生部門のエネルギー消費 3.1 エネルギー消費の概況 民生部門は、運輸関係(自家用乗用車等)を除く家計消費部門におけるエネルギー消費(冷暖房用、給湯用、厨房用、動力・照明用等)を対象とする家庭部門と、企業の管理部門等ビル・事務所、ホテル、百貨店等第3次産業(運輸関係事業、エネルギー転換事業を除く)等におけるエネルギー消費(内容は家庭部門同様)を対象とする業務部門に大別される。2004年度の民生部門エネルギー消費は4964PJ、対前年度比1.3%増となっており、最終エネルギー消費の約30.9%を占める。内訳は、家庭部門13.0%、業務部門17.9%となっている(図6)。 3.2 エネルギー消費の推移 1)家庭部門 家庭部門のエネルギー消費は、世帯数の増加や高齢者比率の上昇等の杜会状況との相関が高く、また生活の利便性、快適性、豊かさを追求する国民のライフスタイルの変化により、2000年度頃まで、ほぼ一貫して増加してきた。1973年度の家庭用エネルギー消費量を100とすると、2004年度には212となっている。用途別構成を見ると、近年においては家電製品の普及や大型化/多機能化により、動力・照明用の需要の増加が顕著である。また冷房用が増加しし、相対的に暖房用・給湯・厨房用需要が減少した。2004年度には、動力・照明(37%)、給湯(28%)、暖房(25%)、厨房(7%)、冷房(2%)となっている。2004年度は猛暑により冷房用が特に増加したと考えられている。夏季の短期間に需要が集中する冷房用は、ピーク時の電力不足の問題を引き起こす原因となっている(図7)。 2)業務部門 業務部門のエネルギー消費は経済活動との相関関係の高さが指摘されているが、1965年度から1973年度までは年率15.0%の伸び率、石油危機以降の1973年度から1985年度までは、消費原単位の改善等により年率1.3%増と低い伸び率で推移した。以降は、延床面積の増加、オフイスの情報化・OA化の進展や空調設備需要の高まり等を背景に顕著に増加し、1990年度から2004年度までの年率2.5%の伸びを示している。動力・照明用が業務部門エネルギー消費全体に占める割合は、2004年度、約35%である。またエネルギー源としては電力が顕著な伸びを示している。用途別構成をみると給湯用、動力・照明用、暖房用で8割以上を占めているが、近年の傾向としては給湯用のシェアが小さくなり、動力・照明用がシェアを伸ばし、冷房用の比率が家庭部門に比べ大きい(図8)。 4.運輸部門のエネルギー消費 4.1 エネルギー消費の概況 運輸部門は、乗用車、バス等の旅客部門と陸運、海運、航空貨物等の貨物部門に大別される。運輸部門のエネルギー消費はエネルギー消費全体の24.1%(2004年度)を占めている。このうち、旅客部門が約6割、貨物部門が約4割である。 4.2 エネルギー消費の推移 2004年度における運輸部門のエネルギー源の構成比を見ると、ガソリン等の石油系燃料がほぼ全量を占め、電力は2%程度のシェアである。運輸部門のエネルギー源構成比の年次推移を図9に示す。 1)旅客部門 旅客部門のエネルギー消費は、1965年度から1973年度まで年率13.4%、1973年度から1986年度まで年率3.8%、1986年度から1992年度までが年率5.7%と石油危機以降若干伸び率が低下した時期があったものの、1993年度以降は、輸送需要の増大、自動車保有台数の増加、実走行燃費の悪化等により、1999年度まで旅客部門のエネルギー消費量は、GDPの伸び率を上回る伸びで増加してきた。しかし、2000年度以降、消費量は頭打ちの傾向にある。なお、旅客部門は、輸送量・エネルギー消費量ともに、貨物部門を上回って推移している(図10)。 2)貨物部門 貨物部門のエネルギー消費は、1979年度から1982年度まで減少傾向にあった。以後1992年度まで上昇傾向に転じている(1986年度から1992年度まで年率2.9%の伸び)。1993年度以降は、景気の後退局面の長期化に伴う貨物輸送需要の減少等によりエネルギー消費は減少した。その後、鉱工業生産指数の上昇等の影響により輸送量が増加し、エネルギー消費も増加した。1997年度は不況の影響でエネルギー消費は減少し、その後も輸送効率の高い営業用トラックが増加する一方、自家用トラックが減少するという貨物物流の動向変化を受け、エネルギー消費量は、僅かながら減少傾向を続けている(図10)。 なお、貨物部門のエネルギー消費の内訳では、大部分が自動車である。2004年度の実績では、トラック約90.0%(営業用44.0%、自家用46.0%)、鉄道0.3%、海運8.0%、航空2.0%である。 <図/表> 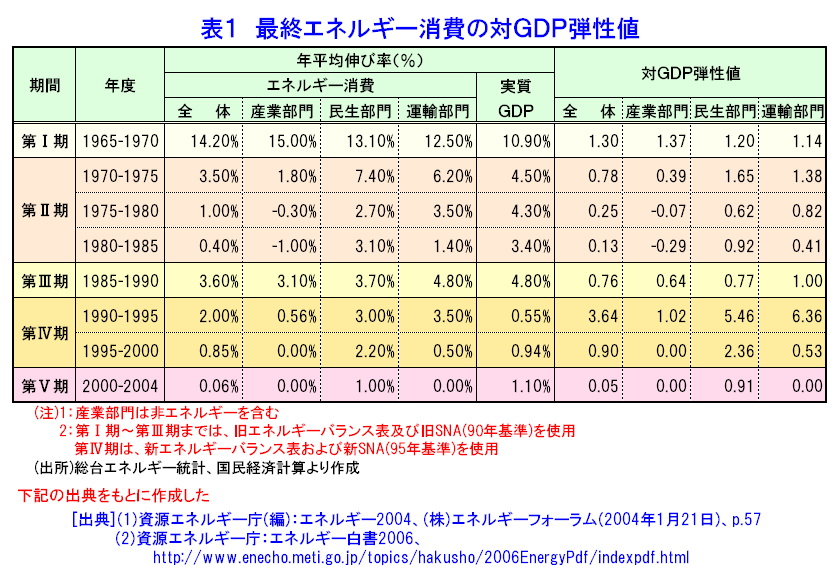
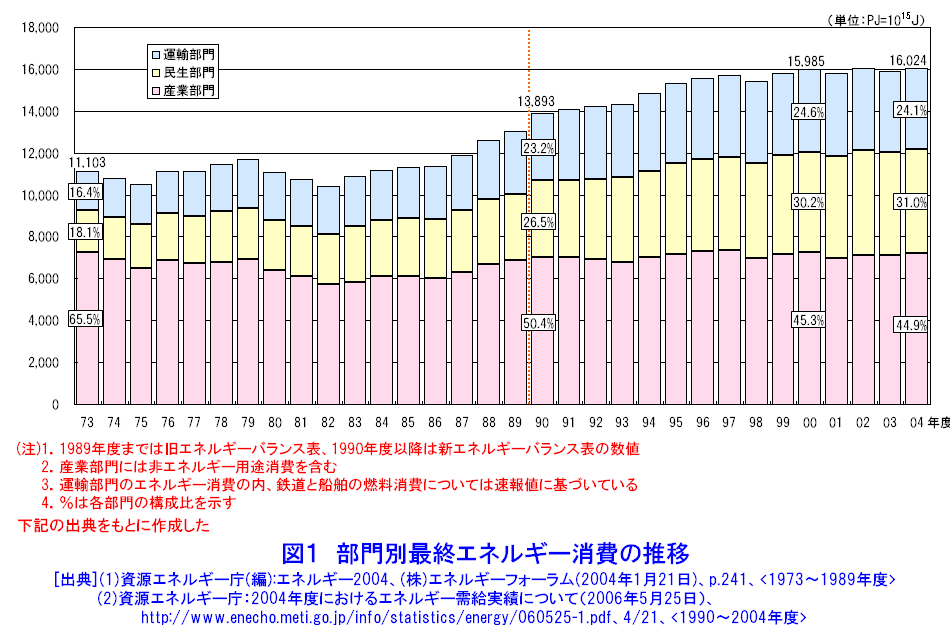
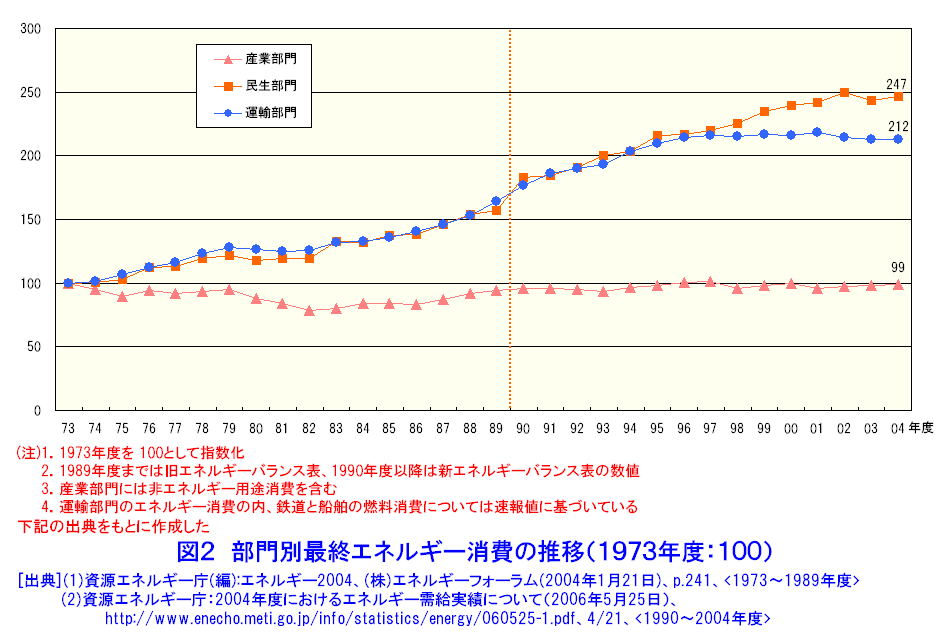
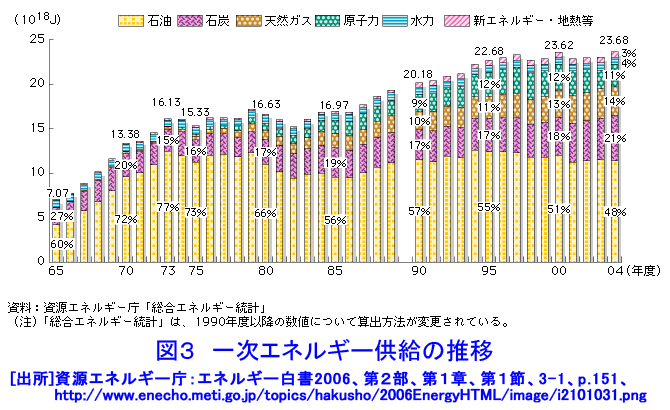
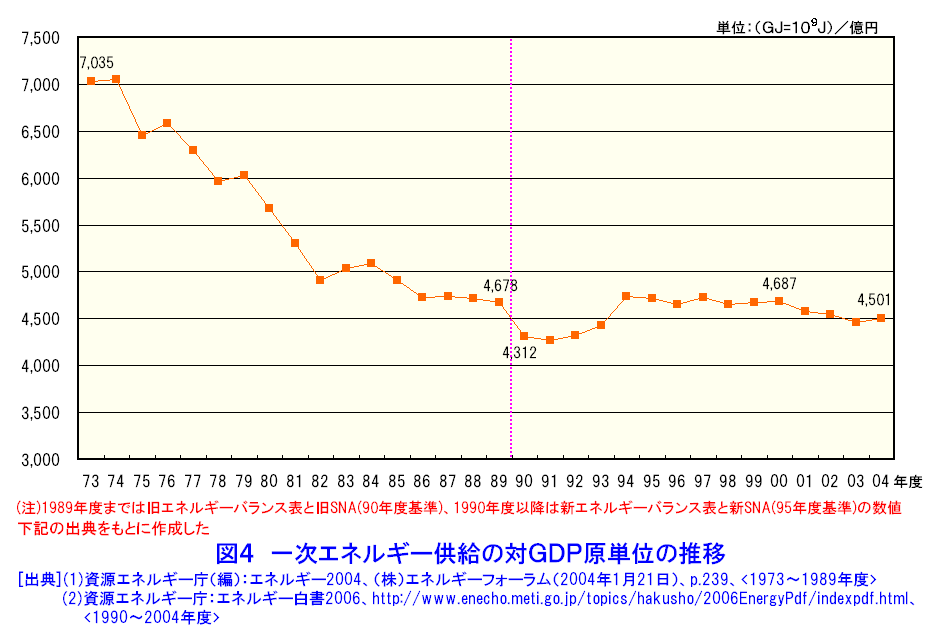
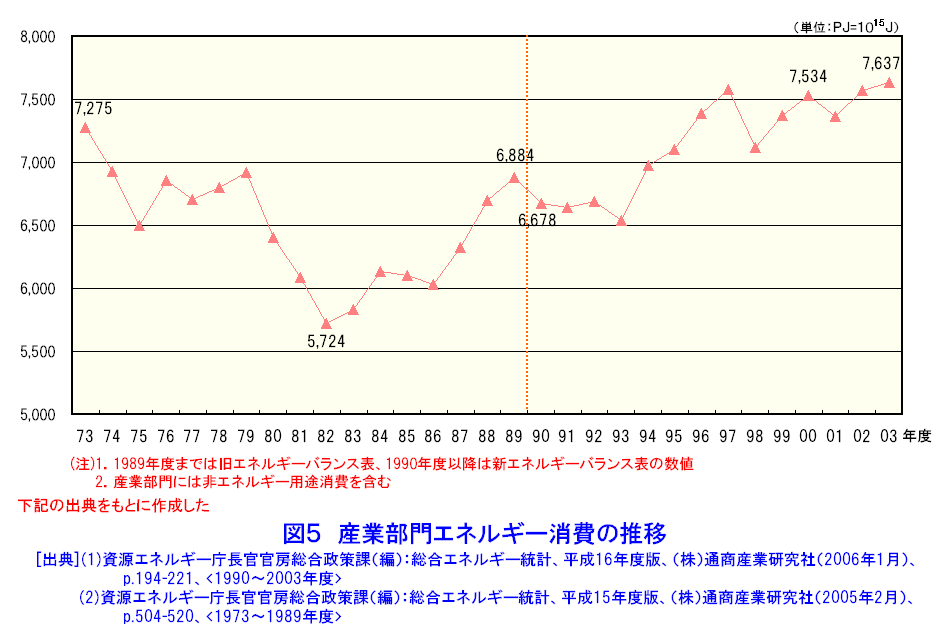
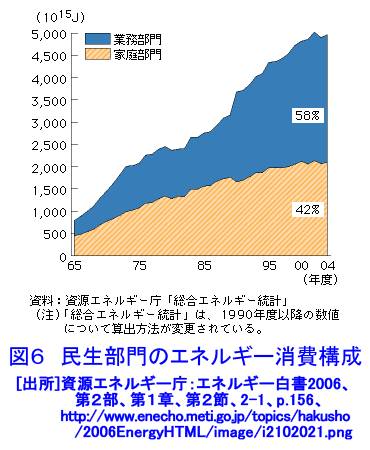
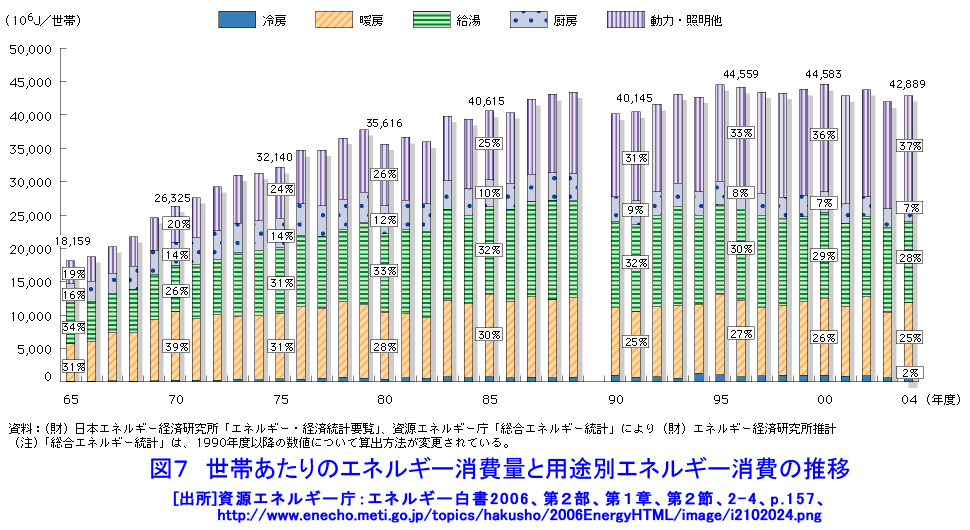
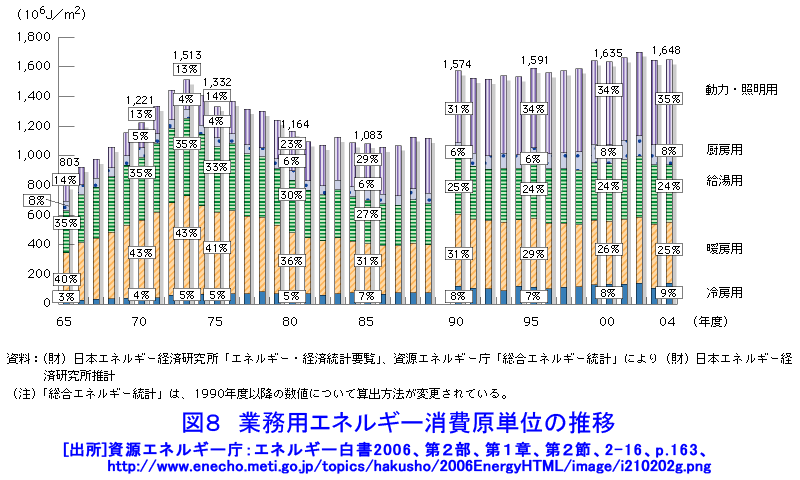
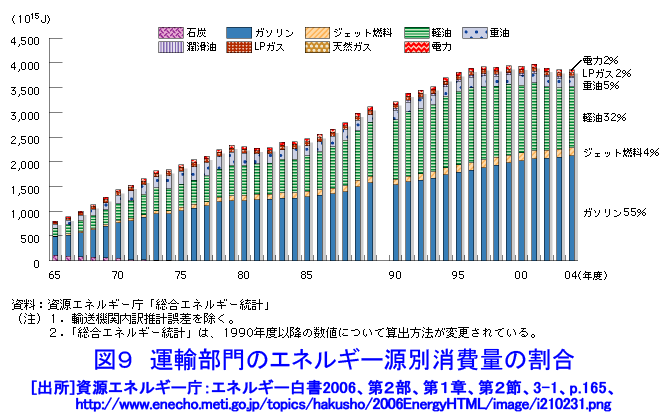
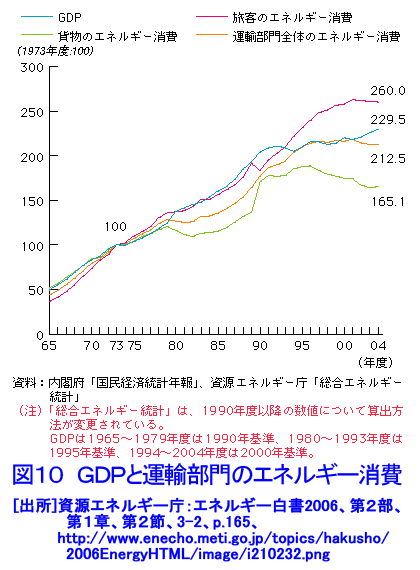
<関連タイトル> 日本のエネルギー供給とその推移 (01-02-02-01) エネルギー需給実績(2000年度) (01-02-02-12) エネルギー需給実績(2001年度) (01-02-02-13) <参考文献> (1)資源エネルギー庁(編):エネルギー2004、(株)エネルギーフォーラム(2004年1月21日) (2)総合資源エネルギー調査会:長期エネルギー需給見通し(2001年7月)の概要及び最近のエネルギー需給の推移について、総合資源エネルギー調査会需給部会(第1回)(2003年12月8日)配付資料6 (3)資源エネルギー庁:2004年度におけるエネルギー需給実績について(2006年5月25日) (4)資源エネルギー庁長官官房総合政策課(編):総合エネルギー統計、平成16年度版、(株)通商産業研究社(2006年1月) (5)日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット(編):エネルギー・経済統計要覧2006(2006年2月) (6)資源エネルギー庁:エネルギー白書2006 (7)資源エネルギー庁長官官房総合政策課(編):総合エネルギー統計、平成15年度版、(株)通商産業研究社(2005年2月)
|

