|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
わが国のエネルギー需給は、1970年代までの高度経済成長期に国内総生産(GDP)より高い伸び率で増加した。同時に「エネルギー革命」と呼ばれた、石炭から石油への主役の交替が進行した。その後、エネルギー政策の大きな転機となった2度にわたる石油危機(1973年、1979年)を経て、エネルギー消費の低成長、エネルギー源の多様化、省エネルギー製品開発の進展がみられた。その結果、エネルギー消費を抑制しながら経済成長を果たすことができた。1990年代には原油価格が低水準で推移する中でエネルギー消費は増加した。2000年代には再び原油価格が上昇したこともあり、2004年度をピークにエネルギー消費は減少傾向にある。2010年度は景気回復や気温の影響により最終エネルギー消費は大幅に増加したが、2011年度からは東日本大震災以降、再び減少傾向となった。2013年度はGDPが過去最大となる一方、最終エネルギー消費は2012年度より1%減少した。 <更新年月> 2017年02月
<本文>
1. わが国のエネルギー需給実績 表1および図1に部門別最終エネルギー消費の推移を、表2にエネルギー源別一次エネルギー総供給の推移を示す。なおエネルギー量の単位の関係は、1013kcal=1.08108百万kl=42PJである。 1.1 エネルギー需要 最終エネルギー消費は、高度成長期といわれた1960年から1970年にかけて経済成長率(実質国内総支出)が年率10.2%と未曾有の伸びを記録したことを背景に、年率12.5%と極めて高い伸びで推移し、1973年度では287百万kl(265×1013kcal=11,150PJ)、1979年度では302百万kl(279×1013kcal=11,700PJ)に達した。しかしながら、二度にわたる石油危機を契機としてエネルギー利用の効率化が進み、産業構造が変化してきたこと等を背景に、第二次石油危機の1979年度以降1986年度までの7年間では、最終エネルギー消費全体で年率平均マイナス0.4%の伸び率で推移した。その後、1987年度以降の内需主導型の好調な景気、さらに低水準で推移するエネルギー価格等を背景にエネルギー需要は増勢に転じ、1986年度から1990年度の4年間で年率4.4%の伸び率で推移し、1991年度の消費量は358百万klに達している。調整過程に入った景気を背景に1992年度、1993年度は、それぞれ対前年度比0.4%増、0.7%増と伸びが鈍化したものの、1994年度は、景気が緩やかな回復基調で推移したことに加え、一部産業における輸出の急増や記録的な猛暑による電力需要の急増等もあり、対前年度比3.7%の高い伸びとなった。1995年度も景気の緩やかな回復傾向での推移等を背景として、対前年度比3.2%の伸びを示した。1998年度以降は景気の停滞を反映してエネルギー消費はマイナスないし低い伸びになっている。全体的には、石油危機以降、GDPは2.4倍に増加したにもかかわらず、産業部門はエネルギー消費量が1割近く減少している。一方、民生部門は2.2倍に増加している。産業部門は全体の5割近くを占めている。 部門別にエネルギー消費の推移をみると、2つのタイプに分けることができる。1つは、景気にあまり左右されないで安定的にエネルギー消費が増加している民生部門や旅客部門である。もう1つは、景気の後退とともにエネルギー消費が減少した製造業や貨物運輸といった部門である(表1、図1および図2)。2000年以降、産業部門、民生部門(家庭+業務)、運輸部門の比率は、2014年度まで大きな変化が見られない。図3に2014年度までの部門別最終エネルギー消費の推移を示す。 1.2 エネルギー供給 この間の供給構造の推移をみると、1955年頃から石油がエネルギー需要の増分を賄う形で導入され、1962年には石炭と石油の比率が逆転し、以後は石油依存の度が年ごとに高まった。 第一次石油危機直前の1973年度の一次エネルギー総供給、417百万klに対する石油依存度は77.4%と過去最高に達し、石油の78%を中東諸国に依存していたわが国は、第一次、第二次石油危機によって、そのエネルギー供給構造の脆弱さをもろに露呈するところとなった。しかし、その後省エネルギーに努め、石油への依存は低下していった。第二次石油危機以降、電力部門におけるLNG(Liquefied Natural Gas:液化天然ガス)、原子力、石炭への転換、セメント、鉄鋼等、エネルギー多消費産業における石油消費量低減化、エネルギー多消費産業から寡消費産業へといった産業構造の変化等が急速に進展し、第二次石油危機直後の数年間(1980年代前半)はエネルギー需要の伸びが低い(図1)にもかかわらず、3.5%の経済成長を遂げるような需要構造に変化した。その結果、石油依存度はピーク時(1973年度)の77%から1985年度には57%と低下した。この時点から円高、石油価格の急落等により、内外の経済情勢、エネルギー情勢は大きく変化し、原油価格の低水準での推移等を背景として、石油依存度はほぼ横這いに推移し、2002年度は51%となり、2013年度まで漸減の傾向となっている(表2、表3参照)。 石油需要の内訳をみると、他のエネルギーに代替されたのは主に電力用C重油等の重質留分に対する需要であって、ガソリン、灯・軽油等中軽質留分に対する需要は増加の傾向を示した。これは石油代替資源の存在しない運輸・民生部門において、車両台数の増加や生活水準の向上が進んだからである。わが国の石油需要は、量の低下のみならず、質的にも中軽質油化という構造変化が表れた。 この間にあって原子力のシェアは1973年度の0.6%から1987年度の10%を経て、1998年度の14%まで上昇し、2000年度は12%、2005年度は11%となり、2010年度までほぼ横ばいであったが、2011年の福島第一原子力発電所事故により、それ以降、実質的に0%となった。また、天然ガスのシェアは1970年度の1.5%から2014年度には23%まで上昇した。石炭は1998年度以降2013年度まで毎年度0.5〜1%程度増加している。 2. 産業部門のエネルギー消費 他の先進諸国と比較した場合のわが国のエネルギー需給構造の特徴の一つとして、最終エネルギー消費に占める産業部門の比率が高いことがあげられる。これにはわが国がエネルギー多消費型の重化学工業を中心に経済成長を達成してきたこと、また国土が狭く運輸部門が小さいこと、気候に恵まれ民生部門が小さい等の理由が考えられる。 産業部門のエネルギー消費は、1973年の第一次石油危機以降エネルギー利用の効率化が進み、1973年度から1986年度までの13年間の年平均伸び率は、マイナス1.4%と消費が抑えられた(図4)。これについては、次のことが考察されている。 A.個別業種毎のエネルギー原単位(単位生産額当たりのエネルギー消費)の変化(低下)が1973年度以降ほぼ一貫してエネルギー消費の伸び率に寄与している。 B.産業構造が基礎素材産業から加工組立産業へ、そしてさらに電子・情報産業へとエネルギー寡消費型産業に中心がシフトしたことも、エネルギー消費の抑制に貢献してきた。しかしながら原単位の低下に比べ、その寄与度は小さい。 1986年度以降は内需主導型の好景気により、生産活動が活発化し、エネルギー消費は堅調な伸びで推移してきており、1986年度から1991年度までの5年間では、年率3.5%の伸びとなった。1980年代半ば以降1990年度までのエネルギー消費の増加要因は、原単位の低下と産業構造の変化が消費抑制に寄与しているものの、1980年代前半ほどの寄与度はなく、他方で生産活動要因がそれをはるかに上回るくらいプラス要因に働いたことによるものといえる。 1992年度、1993年度のエネルギー消費については、景気が調整局面に入ったこともあり、製造業の生産指数(IIP:Index of Industrial Production)がそれぞれマイナス6.0%、マイナス4.0%(生産額ベース)と落ち込んだことが影響し、対前年度比マイナス2.0%、プラス0.4%と円高不況以来6年ぶりの低い伸びとなった。しかし1994、1995年度においては、景気が緩やかな回復基調で推移したことから、製造業のIIPがプラス3.0%、プラス1.6%となり、エネルギー消費は、対前年度比プラス3.5%、プラス2.2%の伸びとなった。1999、2000年度においては、IIPの伸びは対前年度比プラス3.5%、プラス4.0%となっている。対応するエネルギー消費の伸びは、それぞれは5.1%、1.4%となっている。 最近の産業部門エネルギー消費の増減要因に関して分析してみれば、1990年度までは生産活動要因がエネルギー増加要因として働き、原単位と産業構造変化が減少要因として働いていたが、1991年度でその傾向が崩れ、1992年度、1993年度では寄与の方向が逆転した。原単位の増加要因の背景として、設備の稼働率の低下、製品の高付加価値化等が考えられる。産業構造変化による増加要因として、業種別にみると化学工業における生産活動が比較的活発だったことがあげられる。全産業においてIIPが停滞している中、エネルギー多消費産業の化学工業の落ち込みの程度が小さく産業構造上のウェイトが高まったためと考えられる。また、1994年度には、生産活動、原単位、産業構造の変化全てにおいて増加の寄与となっている。1995年度では産業構造が4年ぶりに減少要因として働いたけれども、生産活動原単位は引き続き増加に寄与している。 1996年度以降は産業用エネルギー消費量の伸びも減少し、1998年度はマイナスに転じている。1996年度は生産活動、原単位、の変化は増加の寄与となっている。これに対して、2000年度においては、生産活動の変化を除いてマイナスの寄与に転じており、これがエネルギー消費に反映されている。8,500PJ付近で推移している。 3. 民生部門のエネルギー消費 民生部門は自家用運輸(マイカーなど)を除く家計消費部門でのエネルギー消費を対象とする家庭部門と企業の管理部門等ビル・事務所、ホテル、百貨店等第三次産業(運輸関係事業、エネルギー転換事業を除く)等におけるエネルギー消費を対象とする業務部門に大別される。2000年度および2002年度の民生部門エネルギー消費は各々107百万kl(=100×1013kcal=4,200PJ)、110百万kl(=102×1013kcal=4,300PJ)で、最終エネルギー消費の26〜27%を占める。内訳は、家庭部門約14%、業務部門12〜13%となっている(表1、図4)。家庭部門の比率は2014年度もほぼ同様であるが、業務部門は18%程度まで上昇している(表4)。 3.1 家庭部門のエネルギー消費の動向 家庭部門のエネルギー消費量は、世帯当たりの消費量の増減と世帯数の増減に依存する。家庭部門におけるエネルギー消費の推移を図5に示す。1995年度以降、消費量の伸び率は鈍化傾向にある。家庭用エネルギー消費は、冷房、暖房、厨房、動力・照明他の5部門に分類される。1965年度では給湯、暖房が各々、30%を越えるシェアであったが、近年エアコンの普及により動力・照明用が30%を越え、2014年度は約38%であった。図6に用途別エネルギー消費の推移を示す。 3.2 業務部門のエネルギー消費の動向 業務部門のエネルギー消費は、事務所・ビル、デパート、卸小売業、飲食店、学校、ホテル・旅館、病院、劇場・娯楽場、その他のサービスの9業種に大別される。これら9業種のエネルギー消費を見ると、かつてはホテル・旅館や事務所・ビルがエネルギー消費の多くを占めていたが、近年では事務所・ビルが最も大きなシェアを占め、次いで、卸・小売業となっている(図7)。業務部門のエネルギー消費量は、「延床面積当たりのエネルギー消費量原単位×延床面積」で表すことができる。その推移は1965年度から1973年度までは高度経済成長を背景に年率15%増であったが、第1次オイルショック後の省エネの進展によりほぼ横ばいで推移、しかし、1980年代後半から再度増加傾向に転じて、1990年度から2012年度まで年率1.6%で増加した。 4. 運輸部門のエネルギー消費 運輸部門は乗用車、バス、鉄道等の旅客部門と陸運、海運、航空部門等の貨物部門に大別される。運輸部門はエネルギー最終消費全体の23%を占めており、このうち旅客部門のエネルギー消費量が運輸部門全体の63%、貨物部門が37%を占めた(2012年度)。 4.1 旅客部門のエネルギー消費 旅客部門のエネルギー消費量は、GDPの伸び率を上回る高い伸び率で推移してきたが、2001年度をピークに下降傾向に転じた。1965年度から1973年度までは旅客部門エネルギー消費の年平均伸び率は13.4%であったが、1973年度以降の伸び率は2.1%程度となった。その結果、2014年度のエネルギー消費は1965年度比約7倍となった。乗用車は保有台数の増加等により、1965年度から2014年度まで年平均約4.8%増であり、旅客部門全体の伸び率4.0%を上回った。旅客部門全体のエネルギー消費に占める乗用車の割合は、1965年度の約64%から2014年度約83%に増加している。同期間のエネルギー消費量に占める公共交通機関の割合は、バスが11%→約3%、鉄道が18%→約3%と低下した(図8参照)。 4.2 貨物部門のエネルギー消費 貨物部門のエネルギー消費量は、第二次オイルショック後の1980年度から1982年度、バブル経済崩壊後の1992年度に前年度実績を割り込むことがあったが、基本的には拡大し続け、1996年度にピークに達して、それ以降は減少に転じている。2014年度はピーク期に比較して約3割の減少である。貨物部門は経済情勢、価格の変動、産業構造の変化および省エネ技術の普及等に影響を受けやすく、旅客部門に比較して、消費量の伸びは穏やかであり、より早い段階で減少に転じ、減少幅もより大きい。貨物部門のエネルギー消費の内訳では、営業用トラックと自家用トラックで約9割のシェアとなっている(図9)。図9には、船舶と航空機のエネルギー消費の動向も示されている。 (前回更新:2005年2月) <図/表> 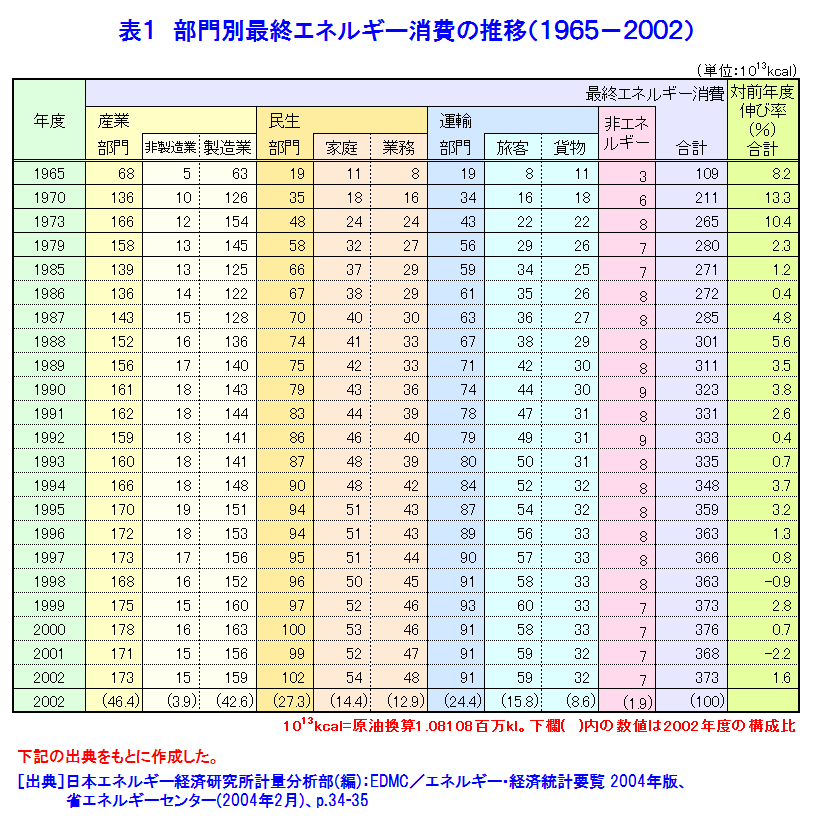
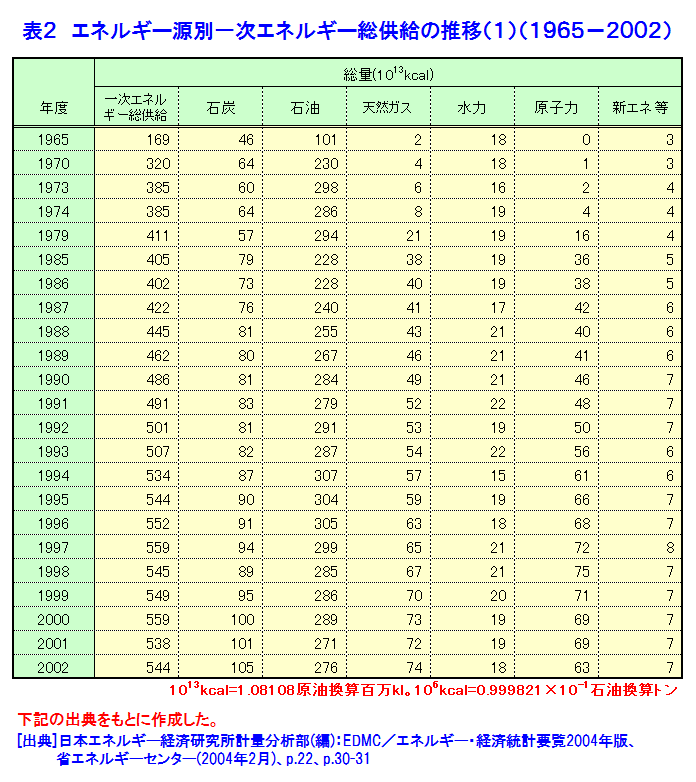
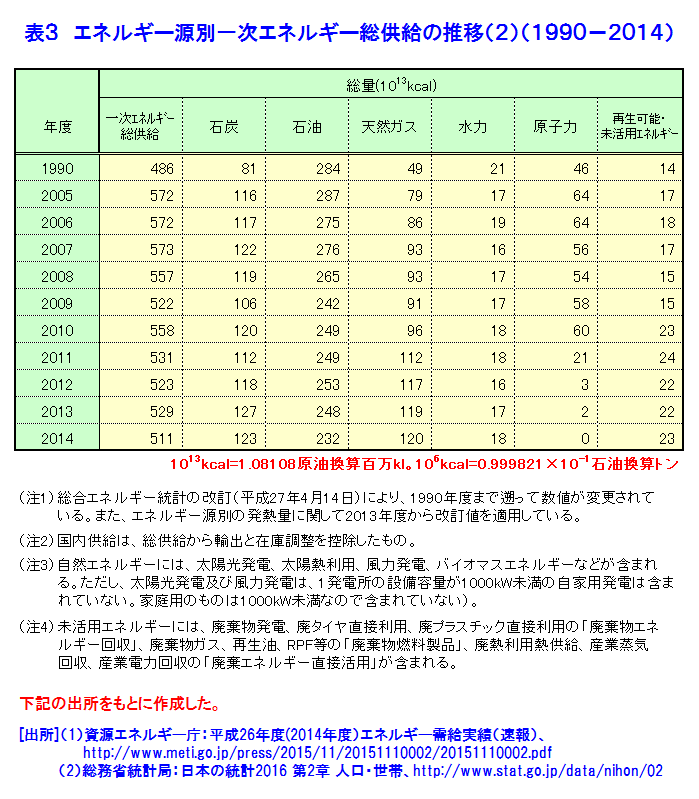
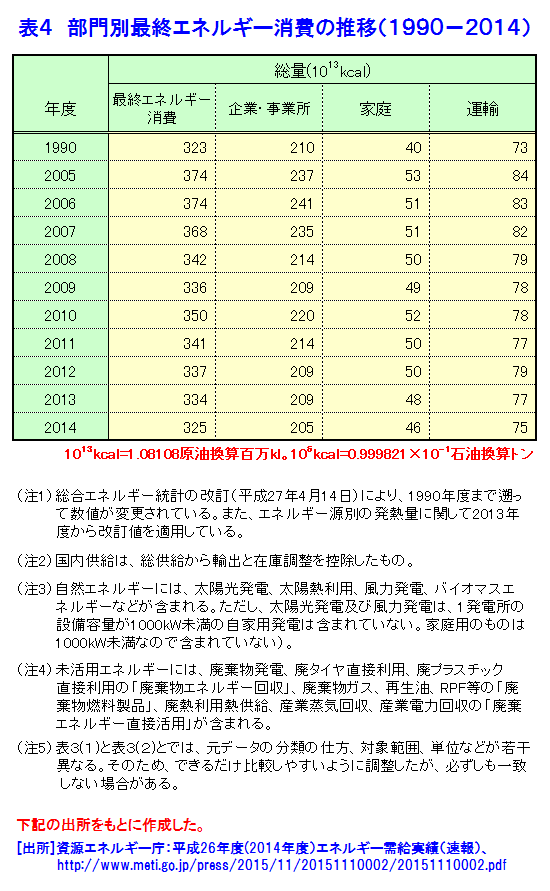
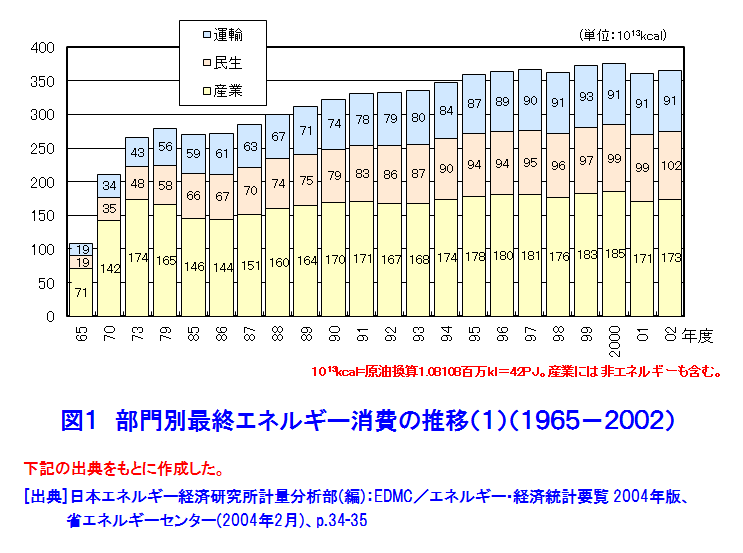
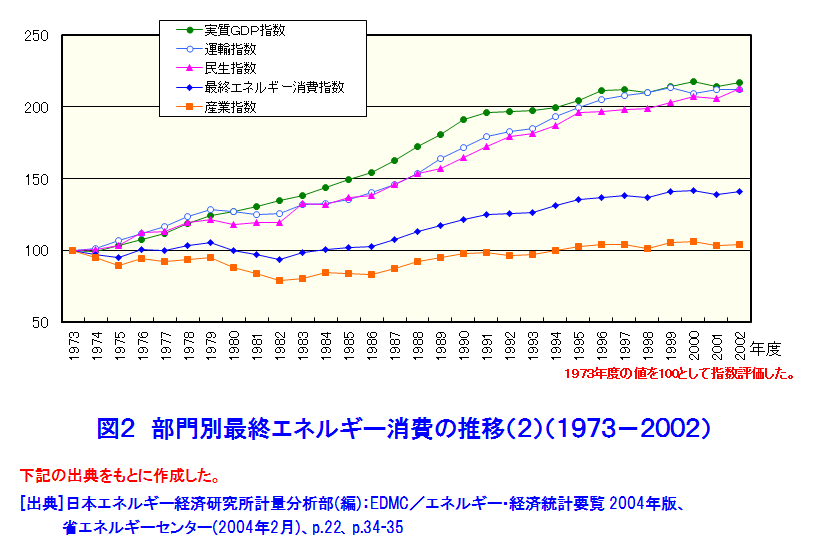
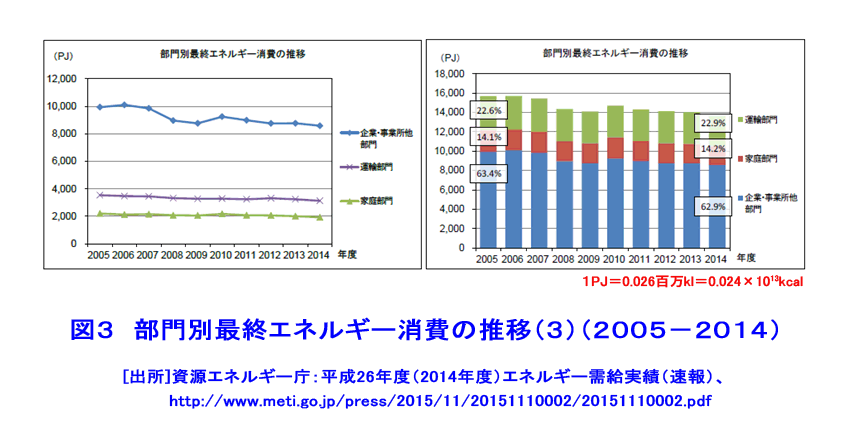
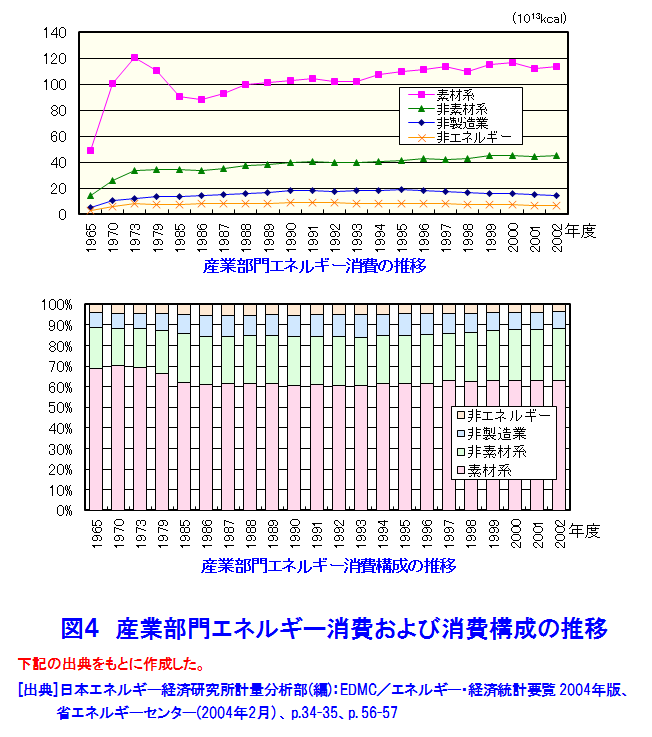
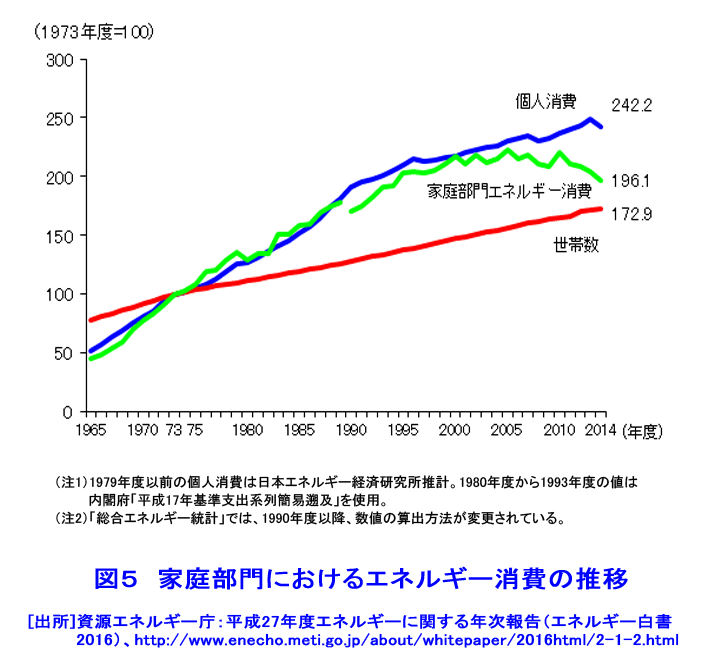
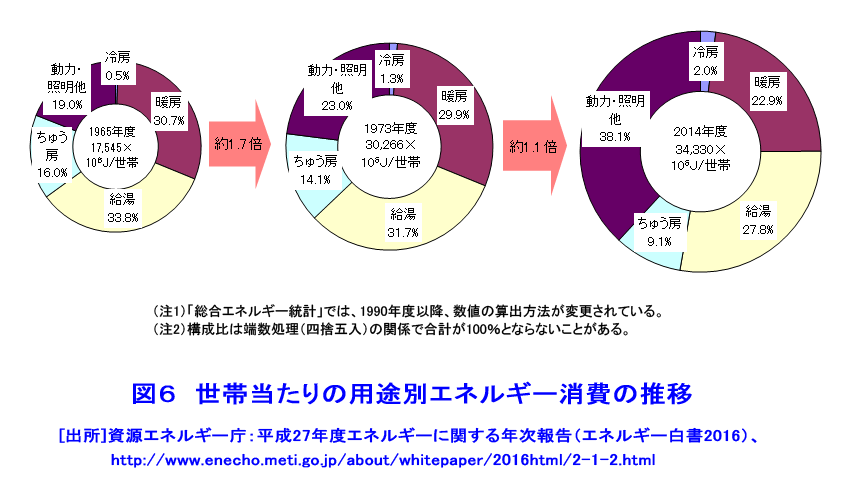
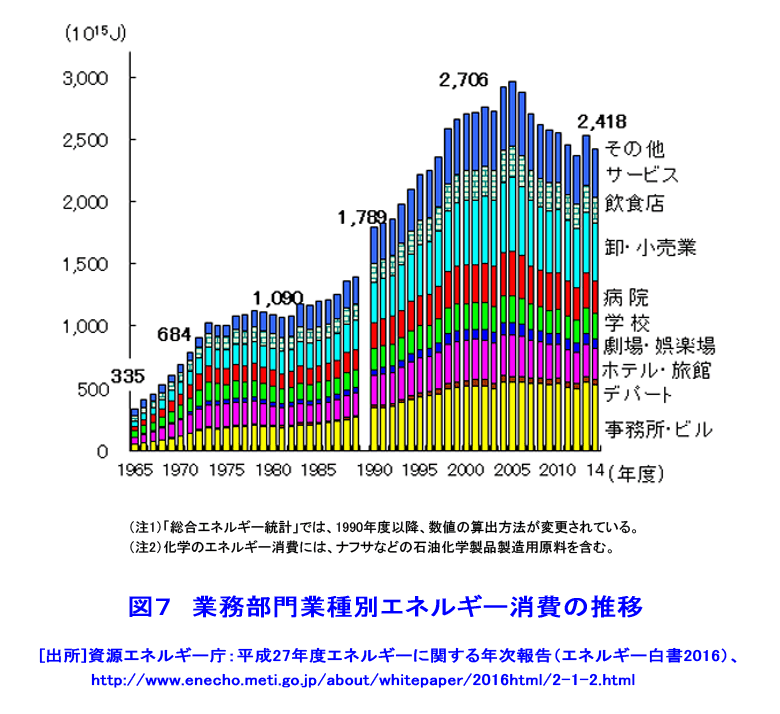
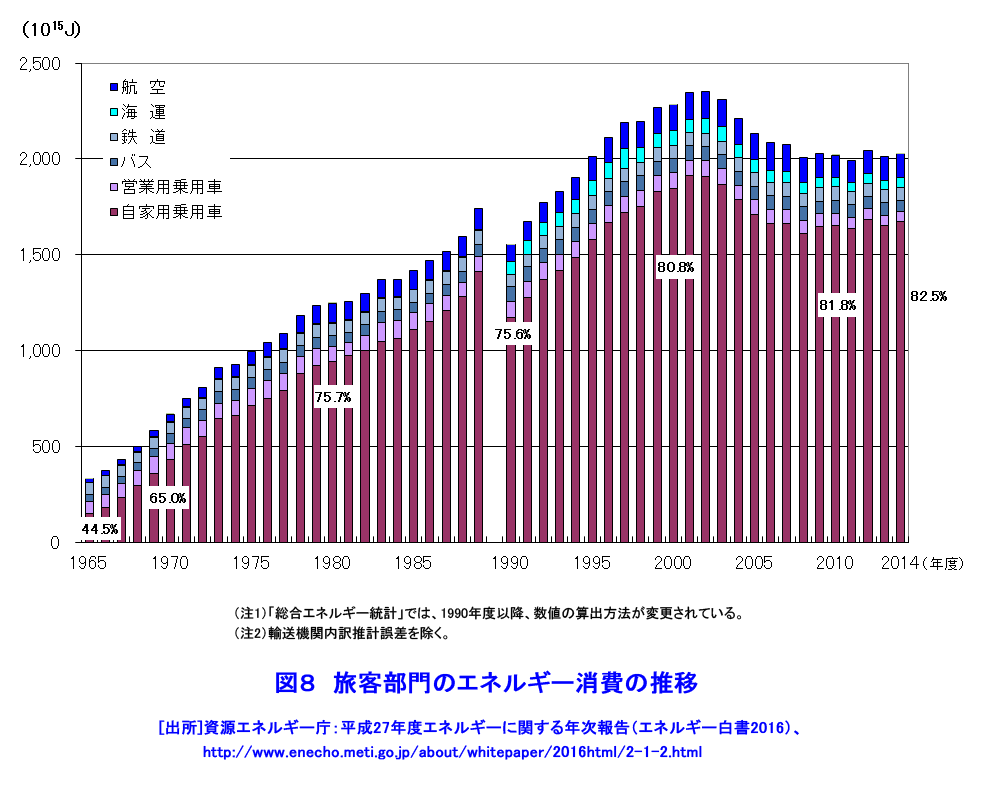
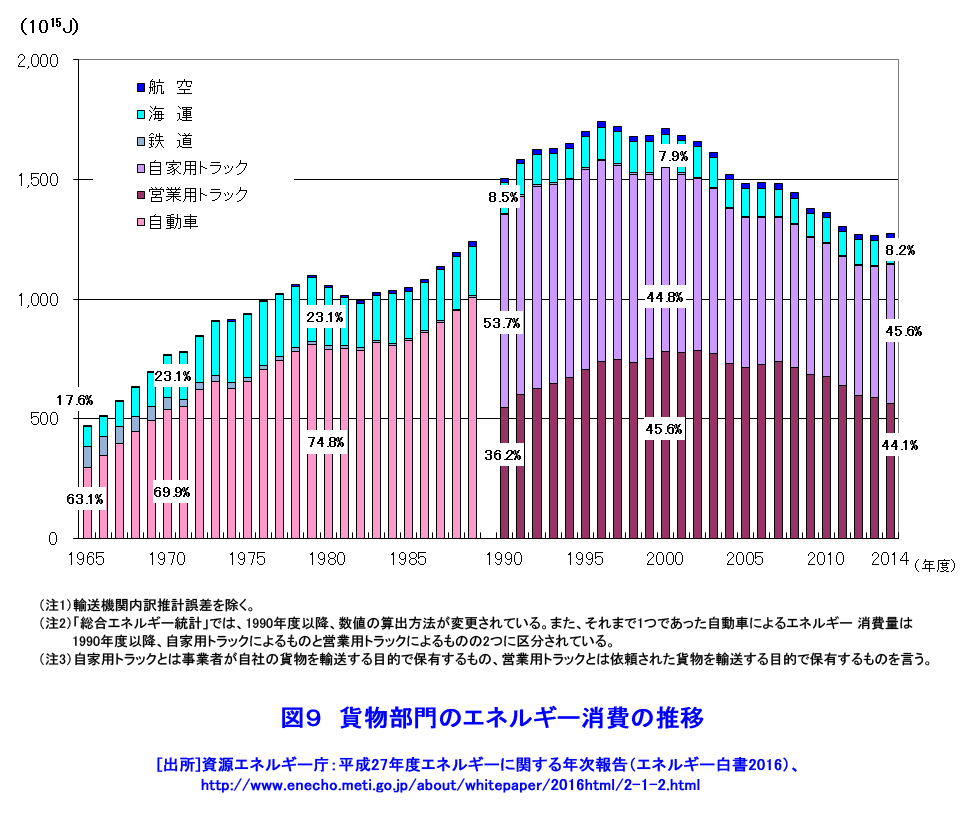
<関連タイトル> 国別一人当たりの一次エネルギー消費量 (01-07-03-03) <参考文献> (1)資源エネルギー庁(編):エネルギー2002、(株)エネルギーフォーラム(2001年11月) (2)資源エネルギー庁長官官房総合政策課(編修):総合エネルギー統計 平成13年度版、通商産業研究社、(2002年7月) (3)資源エネルギー庁(編):エネルギー2004、(株)エネルギーフォーラム(2004年1月) (4)日本エネルギー経済研究所計量分析部(編):EDMC/エネルギー・経済統計要覧 2004年版、省エネルギーセンター(2004年2月) (5)エネルギー需要見通しに関する基礎資料、総合エネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小委員会(第2回会合)資料2(2015年2月) (6)資源エネルギー庁:平成25年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2014)HTML版、http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2014html/ (7)資源エネルギー庁:平成26年度(2014年度)エネルギー需給実績(速報)、http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151110002/20151110002.pdf (8)総合資源エネルギー調査会:資料2、エネルギー需要見通しに関する基礎資料(平成27年2月) (9)資源エネルギー庁:平成27年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2016)HTML版、http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2016html
|

