|
<解説記事ダウンロード>
<概要>
昭和56年3月7日から8日にかけて日本原子力発電株式会社敦賀発電所において、廃棄物処理旧建屋内のフィルタースラッジ貯蔵タンク室から放射性廃液が一般排水路へ漏洩した。配管の洗浄作業において洗浄系弁を開状態のまま放置したため、洗浄に伴って生ずる廃液が同室の床にあふれ出し、大部分は地下の廃液中和タンクに回収されたものの、一部が電線管床埋込部周辺の細孔等を経て床下に埋設されていた一般排水路へ漏洩したものである。 <更新年月> 1998年05月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
1.放射性廃液漏洩事故の経緯の概略 (1) 敦賀発電所においては、昭和56年3月7日、20時20分ごろから、フィルタスラッジをサージタンクから貯蔵タンク(D) に移送する作業が行われた( 図1 参照)。 この移送作業の終了後の同日21時35分ごろ、移送配管の洗浄作業が開始された。 洗浄系弁の操作スイッチがある廃棄物処理旧建屋内の制御盤及び洗浄系弁設置場所それぞれで、この洗浄作業を担当していた運転員らは、同時に別の作業をしいるうちに直引継(交替勤務の引継)を行う時間となったので、洗浄作業中であることを失念し、そのまま直引き継ぎのため中央制御室に戻ってしまった。 なおかつ、廃棄物処理旧建屋内( 図2 参照)の制御盤にある洗浄系弁の開閉の状態を示す表示灯は、故障したまま放置されていたため、この洗浄作業に際し、洗浄系弁が開かれ、元来は赤色点灯にならなければならない表示が、「閉」の状態を示す緑色点灯のままとなっていた。 (2) このように、洗浄系弁が「開」状態のままであったため、洗浄水は、貯蔵タンク(D)へ流入し続け、貯蔵タンク(D)、更にはドレンタンク(A) 及び(B) がいずれもオーバフーし、オーバフローした廃液は、配管を通して貯蔵タンク室のサンプ(タンクからオーバフローした場合を考慮して同室内に設けられている廃液収集のための埋込型の水溜)に流入し、更にこのサンプから建屋の床面にあふれ出たものと推定される。 この間、翌3月8日8時ごろには、廃棄物処理旧建屋内の制御盤における貯蔵タンク(D) の水位計に水位の異常を示す指示が示されていたものと推定されるが、同時刻ごろに行われた巡視においては、運転員がこれに気付かなかった。 また、同日8時25分ごろには、廃棄物処理新建屋内の制御盤には、貯蔵タンク室のサンプに溜まった廃液を回収するサンプポンプの作動状況が表示されるとともに、サンプの水位が異常に高くなったことを知らせる警報が鳴っていたものと推定されるが、この新建屋内の制御室には運転員がいなかったため、この表示及び警報は気付かれなかった。 (3) 貯蔵タンク室においてサンプから床にあふれ出た廃液は、床面に沿って広がり、壁を貫通していた埋込み管路を通って、いったん隣接の洗濯廃液ろ過装置室に流れ込んだが、そのほとんどは更に建屋内の通路を経由して床ドレンファネル(じょうご型のドレン受皿)に至り( 図3 参照)、階下の廃液中和タンクに回収された。しかし、洗濯廃液ろ過装置室に流れ込んだ廃液の一部が、同室の内側の壁面に沿って設置された4本の電線管の床埋込部周辺に生じていた細孔及び同室の壁面に沿って存在する側溝の一部に生じていた微細なひび割れ( 図4 参照)を通して、床下に埋設されていた一般排水路へ漏洩することになった。 (4) 同日11時ごろにおける運転員による巡視の際に、ようやく、廃液の漏洩が発見され、洗浄系弁が閉じられるとともに、廃液漏洩の拡大を防止するための措置が講じられた。 なお、この廃液の廃棄物処理旧建屋床面へのオーバフロー量は、14.5ないし15立方米であり、そのうち回収量は約14立方米、一般排水路への漏洩廃液0.5ないし1立方米中に含まれていた放射性物質の量は、多めに見積もっても十数ミリキュリーであって、環境への特段の影響は与えなかった。 2.放射性廃液漏洩事故の原因 放射性廃液の漏洩事故は、種々の原因が重なって発生したものであるが、総合的に評価すれば、放射性廃棄物処理旧建屋の設計、施工管理上の問題に主たる原因があり、これに運転管理面における人為的なミスが加わって発生したものということができる。 <図/表> 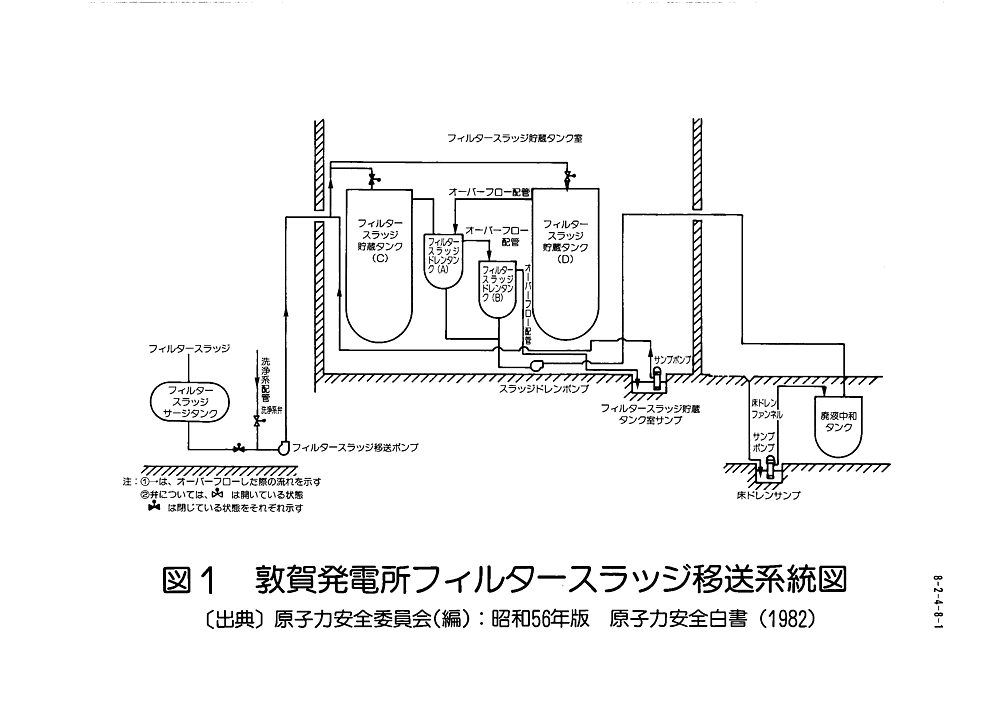
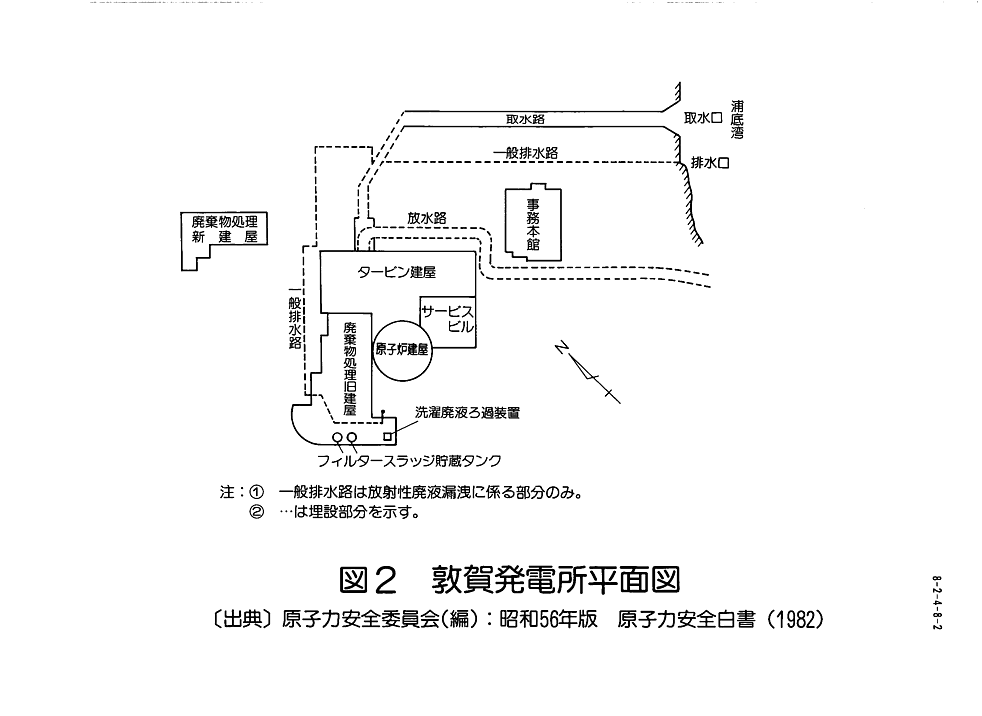
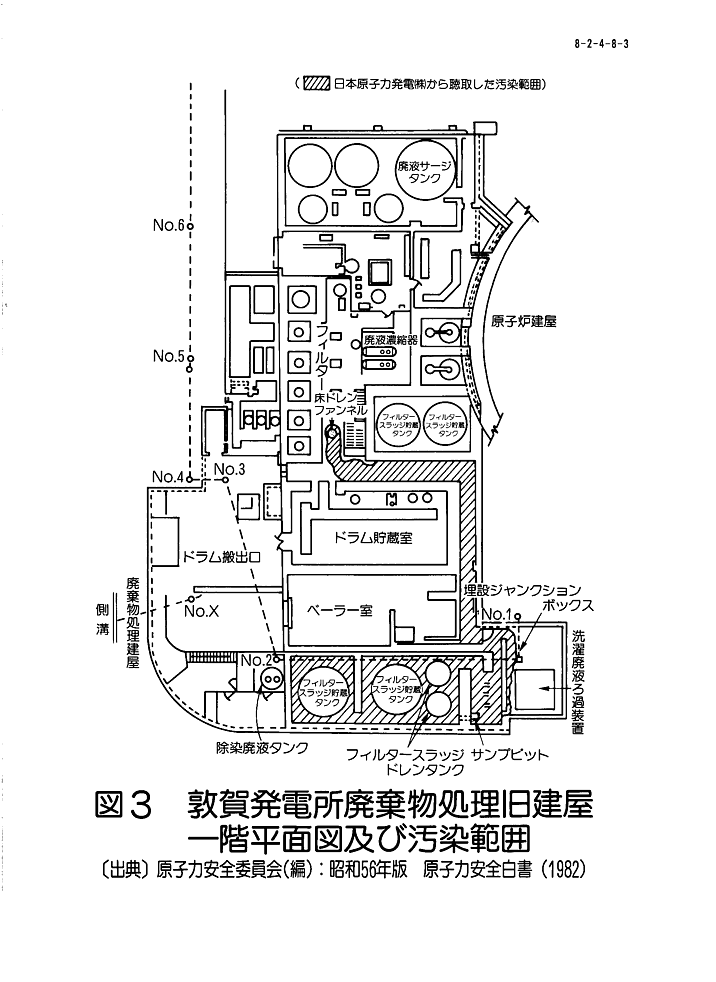
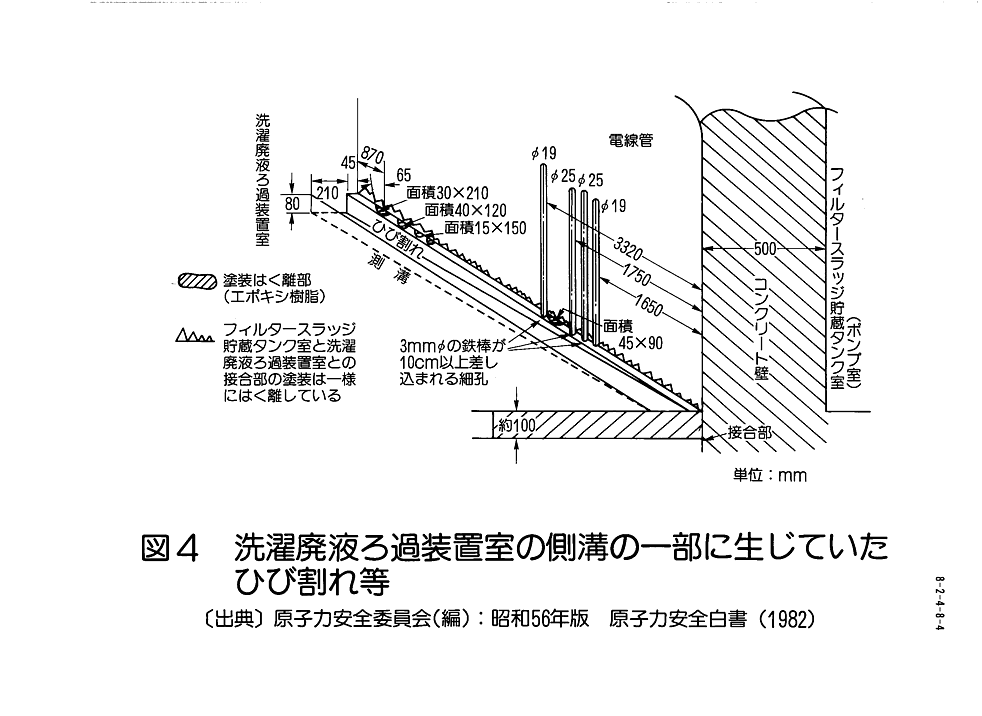
<関連タイトル> 敦賀発電所における放射性廃棄物処理施設からの放射性廃液漏洩事故の環境への影響 (02-07-02-12) 敦賀発電所1号機放射性廃液漏洩事故関連資料(汚染範囲) (02-07-02-11) 敦賀発電所1号機放射性廃液漏洩事故関連資料(指標海産生物及び海水の放射能測定値) (02-07-02-10) 敦賀発電所1号機放射性廃液漏洩事故関連資料(海産食品及び海底土の放射能測定値) (02-07-02-09) <参考文献> 原子力安全委員会(編):昭和56年版 原子力安全白書 (1982)
|

